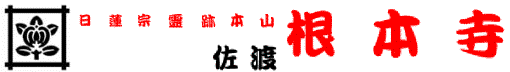
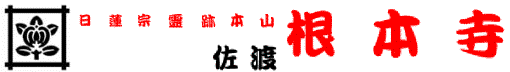
開目抄(かいもくしょう)・・・日蓮宗電子聖典より
〔第一章〕 儒教・外道と仏教
一切衆生(生きとし生ける者)がかならず尊重しなければならないものが三つある。すなわち〈主徳〉と〈師徳〉と〈親徳〉の三つがそれである。また、かならず学ばなければならない精神文化が三つある。すなわち〈儒教〉と〈外道〉(仏教以外のインドの宗教思想)と〈内道〉(仏教)がそれである。
(第一に)儒教では、水を治めて理想的な政治を行なった伏羲(ふくき)・神農(しんのう)・黄帝(こうてい)の三皇、これにつぐ少昊(しようこう)・〓〓(せんぎよく)・帝〓(ていこく)・堯・舜の五帝、さらに夏(か)の禹(う)王・殷の湯(とう)王・周の文王(または武王)の三王を天尊と申し上げ、仰ぎみている。諸臣にとっての頭脳であり、万民を幸福な世界に渡す橋だからである。三皇以前は子が自分の父を知ることがなく、人間でありながら動物となんら変わることがなかったといってよい。五帝の時代以後になると父母を尊敬し、孝の倫理が行なわれるようになった。具体的に言うと、(後に舜王となった)重華は過失の多かった父瞽叟(こそう)に敬いの心を忘れなかったし、(漢の高祖となった)沛公は帝王となっても父の太公に孝養をつくした。(周の)武王は父の文王の木主(ぼくしゆ)(位牌)を兵車にのせ(軍を率いて悪王である殷の紂王を伐ち)、(後漢の時代に、十五歳のとき)丁蘭は母の木像を造り、生前同様に給仕をした。これらは〈孝〉の手本というべきである。比干は、甥である殷の紂王の〓乱を諫めて、かえって怒りにふれ、その妃の妲己(だつき)の讒言(ざんげん)によって殺された。(衛の懿公の侍臣であった)公胤(弘演)は他国から帰国し、北狄(ほくてき)に捨てられた主君懿公の肝を見て、自分の腹を割いてそこに収めた。これらは〈忠〉の手本というべきである。(道徳経を説き、無為の道を教えた)尹伊(尹寿)は堯王の師であり、務成は舜王の師であり、太公望は文王の師であり、老子は孔子の師である。これら四人の聖人に対しては、天尊も頭をうなだれ、万民は合掌して尊敬の心をあらわすのである。
これらの聖人には、それぞれ伏羲・神農・黄帝の三皇の〈三墳〉、少昊・〓〓・帝〓・堯・舜の五帝の〈五典〉、夏の禹王・殷の湯王・周の文王の三王の〈三史〉などの三千余巻の書物がある。そして、その主張は〈三玄〉に集約される。〈三玄〉というのは第一には〈有の玄〉で、周公旦らの主張。第二には〈無の玄〉で、老子などの教え。第三には〈亦有亦無の玄〉で、荘子のいう玄がこれである。父母から生まれる以前を考究すると、もともと人間の存在は〈万物生成の根本となる精気〉から成立するという説、貴賤や苦楽や是非や得失等は皆、〈もって生まれた本性〉のままだという説もある。このように、たくみにさまざまな説を立てるが、しかし、いまだかつて過去世や未来世のことをほんの少しも知らずに、玄であるとか、黒であるとか幽であるとか言う。そして、「だから〈微妙で深遠〉というのだ」という。それでは、ただ現在だけを知っているにすぎないのと同じである。現在世で仁・義を立てて自分の身を守り、国の安泰を図るのである。これに相違すれば一族が滅び家が亡びるなどというのである。これら賢人・聖人として尊敬される方々は、過去世を知らないし、未来を洞察することがない。凡人が自分の背中を見ることがなく、光を失った人が前を見ることができないといわれるように。ただ、ひたすら現在世で、家を治め、孝養を尽くし、一生懸命に仁義礼智信の五常を行なえば同僚から尊敬を受け、名声も国中に知られることであろうし、賢明な王から召し出されて臣下とされたり、精神的指導者としてあがめられることであろうし、さらには国王の位を譲られることもあるかもしれないし、天もお出ましになって守って下さることであろう。例えば周の武王の家臣として仕えた周公旦・召公〓(せき)・太公望・畢高公・蘇忿生は五帝星の化現であるといわれているし(呂氏春秋二十五)、また光武帝に仕えて後漢の中興に功績のあった二十八将は二十八宿の応現である(後漢書、十八史略)と記録されているほどである。
(前述の通り、儒道はひたすら現在世で家を治め、孝養をつくし、五常を行なうように勧めて来たが)しかし、この方々は実際のところは過去世も未来世も知らないために、父母や主君や師匠が生を喪って後の世界での安楽に寄与することができない、恩知らずの者だけである。だから、本当の賢人・聖人とはいえないのである。孔子が「この中国の地にはまだ賢人・聖人はいないのであって、西方インドの国の仏陀(ぶつだ)こそが聖人として尊敬せねばならぬ方である」として、儒道は仏教の教えに入る入口であると言ったのはこのような意味なのである。「礼律節度には尊卑の序があるのであって、戒を扶(たす)ける。楽は心を和やかにし、風(ふう)を移し、現実の世界から魂を遊ばせる。これは禅定(ぜんじよう)を助けることになる」(摩訶止観巻六下)という。その礼楽を教えたのは、仏教が渡来して来たときに仏教の根本である〈戒〉〈定〉〈慧〉に入りやすくさせるためである。すなわち、王と臣下との関係を教えて尊いものと卑しいものの違いを納得させ、父母の存在の意味を教えて孝というものがいかに大切であるかを知らしめ、師匠に帰依し教えを乞うことの大切さを知らしめたのである。中国の天台大師から数えて第六祖の妙楽大師は「中国に仏教が伝わったのは、実にこのような地ならしがあったおかげである。礼楽の思想が先に伝わってこそ、真の道である仏道が後から人々を啓発したのである」と摩訶止観弘決に述べている。天台大師は摩訶止観に言う。「金光明経には、この社会に備わっている善は、皆この経(金光明経)をもととするのであり、もし深く一般倫理を深めて行けば、とりもなおさずそこに仏法がある」と説かれている、と。また、「私は三人の聖人を中国に遣わして、かの国を教化する」という仏陀の語を挙げている。妙楽大師が同書を注釈した摩訶止観弘決に、清浄法行経では「月光菩薩は中国に出現して顔回と名乗り、光浄菩薩は中国で仲尼(孔子)と称し、迦葉菩薩は中国では老子と称している。このように天竺(インド)からこの中国を指して彼(かしこ)といっている」と述べている。
第二に、インドの外道である。(外道=インドの宗教では)三つの目・八本の臂をもつ大自在天(マハー・イーシュバラ)とヴィシュヌの二天をすべての人々の慈父・悲母であるとし、また天尊・主君と称している。数論(すろん)派の開祖・カピラ、勝論(かつろん)派の開祖・ウルソーギャ、ジャイナ教の開祖・ロクシャバ、この三人を三仙と呼ぶ。これらの人々は釈尊出世以前八〇〇年前後の仙人といわれる。この三仙のおしえを四ヴェーダといい、六万蔵あるといわれている。その後、釈尊がこの世にお出ましになった頃には、これら外道の代表である六師外道たちは外道の聖典を学んで、インド全体、すなわち東・西・南・北および中インドの諸国の〈師〉(精神指導者)となり、その分派は九十五、六にも及んだ。
これらの流派がさらに分流し、それぞれがわれこそはと主張を高く掲げる様子は、欲界・色界・無色界の三界のうち、欲望や形のとらわれから脱却した無色界で最高の第四天の非想天(有頂天)にいるようであり、頑(かたく)なに自分の流派に執着する心は金や石より固かった。けれども、その思想が深く論理的に勝れている点では儒教の遠く及ぶところではない。すなわち、過去世の一生どころか、二生、三生、あるいは七生、さらにいえば八万劫を見通すことができ、また未来世について八万劫の先まで知ることができるという。そこに説かれる教えの根本は、(1)因(原因)の中に果があるという数論派の説、(2)または因の中には果がないとする勝論派の説、(3)因の中に果があったりなかったりするという尼乾子の考え方の三つであり、これを外道の極理とすることができよう。
外道の中でも善い外道は、五戒(不殺生戒・不偸盗戒・不邪婬戒・不妄語戒・不飲酒戒)と、十善戒(五戒のうち不飲酒戒を除き、不綺語・不悪口・不両舌・不貪欲・不瞋恚・不邪見を加える)などを実践し、まだ煩悩を断ち切るには至らない禅定(瞑想)を修行し、上を見ては色界(しきかい)・無色界を確かめ、また上の世界に涅槃があると目標を定めてちょうど尺取虫のように攻めのぼって行くが、逆に非想天(有頂天)から地獄界や餓鬼界や畜生界に堕ちてしまうのが実情なのである。実際にはこうした教えによって一人として天に留まる者はいないのだが、人々は天に到ったから再び地上に戻ることはないのだと思い込んでしまっている。それぞれが自分の師匠の教えることが正しいと信じ込んでいるから、ある者は一日に三度も冬の寒い日にガンジス河に水浴する、頭の髪の毛を抜いてしまう者もある、石の上に身を投げる者もある、身体を火に投じる者もある、頭と両手・両足を火で焼いて修行する者などがあった。さらに無所有の精神を実践するために(ジャイナ教のように)全裸で生活する者があり、馬を数多く殺せばそれだけ福を受けることになるという者もあり、草木を焼く者、すべての木に礼拝する者もあった。こうした邪悪な思想が数限りなくさまざまに行なわれたのである。そして、それぞれに指導者として師を恭(うやま)う姿は、あたかも諸天が世界中の動向を把握する帝釈天(インドラ)を敬う姿、臣下が皇帝を伏拝する姿のようであった。
しかしながら、九十五種にも及ぶこれら外道の流派の教えによって、善きにつけ悪しきにつけ、一人も生まれたり死んだりという苦悩を克服してはいない。善い師のもとで修行すれば、二度、三度と生まれ変わって悪道に堕ちることとなり、悪い師のもとで修行すれば生まれ変わる度毎に悪道に堕ちてしまう。外道の意義は、仏教に入るために肝要な思想であることにあるのである。たとえばある外道は「千年の後に仏陀が世に出現するであろう」と言い、ある外道は「百年の後、仏陀が出現する」などと言っている通りである。大涅槃経第八巻の如来性品(によらいしようほん)には「すべてこの世の外道の経典は皆、仏陀の述べた考えであって外道の考えではない」などと言い、法華経の五百弟子受記品には「人には貪(とん)(むさぼり)・瞋(じん)(いかり)・痴(ち)(無智)の三毒があることを指摘し、また邪(よこし)まな思想をもっている様相を現わす。私(釈尊)の弟子たちはこのように方便によって人々を救う」と外道と仏教の関係について述べている。
第三には大いなる覚(さと)りを実現して、世間のみならず出世間からも尊ばれる釈尊。釈尊こそ、すべての衆生の大いなる導きの師・精神を見つめさせる大眼目・人々を覚りの世界に渡す大きな橋梁・人々を覚りの世界に運ぶ大船師・人々の善い心を育てる大福田とよばれる方である。儒教の四聖(尹伊・務成・太公望・老子)やバラモン教の三仙(数論学派の開祖・カピラ、勝論派の開祖・ウルソーギャ、ジャイナ教の開祖・ロクシャバ)らは、聖人(せいじん)の聞え高いのであるが、よくよく検討すると見思(けんじ)の惑(道理上の迷いと感情的な迷い)、塵沙(じんじや)の惑(人を導くうえの障(さわ)りとなる惑(まど)い)、無明(むみよう)の惑(真理を見る目をくもらせる根本の惑い)という三つの煩悩をいまだ断ちきっていない凡人である。名前だけは賢人として聞えているが、実は因果の道理を充分に体得することのできない赤子のような存在である。そのような凡人の教えるところに従って生死の海を渡ろうとするであろうか。そのような教えを橋として六道(地獄・餓鬼・畜生・修羅・人・天)という迷いの世界から〓れることはできない。大いなる我が師・釈尊は、欲界・色界・無色界の三界の煩悩を超越した聖者として生死を脱却しておられるから、まして六道の迷いの世界に輪廻する凡夫の生死(それぞれの業因(ごういん)にしたがって寿命に限りがあり、形体に段別がある)などは完全に超越していることは言うまでもない。生死を流転する根本の無明(無知)を完全に超越なさっておられる。まして見惑(けんなく)(道理上の迷い)や思惑(しわく)(感情的な迷い)という派生的な煩悩を超越していることはあらためていうまでもない。
この覚者釈尊は三十歳で成道し、八十歳で入滅なされるまで、五十年間にわたってその一代の教えをお説きになった。それらの教えの一字一句のすべてが真実の言葉である。一文一偈が皆、虚妄(こもう)の言葉(そらごと)ではない。外典(儒道の聖典)や外道(インド宗教の聖典)の中で語られる聖人・賢人の言葉ですら誤りがあるわけではない。行ないと、理念のもととなる心とは照らし合っているのである。まして仏陀釈尊は遥かにはるかに遠い昔から虚妄の言葉を語らない方であるから、仏陀が一代・五十余年の間に語られたことは、外典や外道と比較するとあまりにも偉大な教えであることは言うまでもない。大いなる聖者の真実の言葉なのである。釈尊が初めてブッダガヤの菩提樹の下の金剛宝座でおさとりを開かれてから、涅槃(入滅)の夕べに至るまで、お説きになった教えはすべて真実なのである。
しかしながら仏陀が説いた五十余年の諸経典、すなわち八万四千の法門を語った全経典について考えてみると、小乗(小さな教え)もあれば大乗(大きな教え)もある。権経(真実を説くための過程として説かれた経典)があり実経(真実を明らかにした経典)がある。顕教(言語文字に説き明かした教え)があり、密教(秘密の教え)がある。またさらに穏やかな言葉があり、荒々しい言葉がある。真実の言葉があり、虚妄の言葉がある。正智を表わした見解があり邪智の見解を表わした内容がある、というようにさまざまな違いがある。そうしたなかで、ただ法華経のみが教主釈尊の正しい言葉である。過去世・現在世・未来世の三世を一貫し、十方の世界にましますもろもろの仏陀の真実の言葉なのである。大いなる覚りを得、世間・出世間から尊敬される釈尊は、法華経以前の四十余年間に説かれた数多くの経典を指して「未だ真実を説いていない教えである」とし、一代五十余年のうち、最後の八年間に説かれた法華経方便品には「かならず真実を説くであろう」と定められたが、すると多宝如来が大地から出現して「今説かれている法華経は皆真実である」と証明なされた。さらに十方の世界から来集された釈尊の分身の諸仏はその広く長い舌を梵天にまで届かせて、法華経が真実の教えであることを讃えた。この言葉は赤々と輝き、明らかな上にも明らかに轟いた。晴れあがった天空に輝くお日様よりも明らかであり、夜の空に輝く満月のようである。この教えを仰いで信じなさい。伏して考えなければなりませぬぞ。
〔第二章〕 法華経の根幹にある一念三千の教え
ただし、この法華経には二十の大切な特色がある。それについては(奈良仏教六宗のうち)倶舎宗・成実宗・律宗・法相宗・三論宗などはその名前すらも知らない。(奈良仏教のうち)華厳宗と(平安仏教のうち)真言宗という二宗には、元来その教義がなかったのに、ひそかに盗み取ってそれぞれの宗旨の重要な教義としてしまった。しかし、「一念三千の法門(教義)」はただ法華経の本門・如来寿量品第十六の経文の文底(奥底)に深く秘められている教えである。大乗仏教の始祖の竜樹や天親はそれを知っていながら、しかもまだ経文の文底に秘められた一念三千の教えを取り出さなかった。そして、ただ我が天台智者大師だけがこの一念三千の教えを心に抱いていた。
一念三千の法門は十界互具ということから展開される。法相宗と三論宗とは、十界の中の仏界・菩薩界の二界を知らないで、八界を立てるのみであるから十界を知らないのである。まして十界のそれぞれの界が、それぞれ他の九界を具えるということを知るはずがない。倶舎宗・成実宗・律宗などは阿含経によって教義を展開し、地獄界から天界までの凡界(迷いの世界)の六界を明らかにするが、声聞・縁覚・菩薩・仏の聖界(さとりの世界)たる四界を知らない。南方系の上座部仏教(小乗)では、歴史上の釈迦牟尼仏一人だけを仏陀と尊敬して他の諸仏を認めない。したがって、倶舎宗などはそのような十方の世界の中に釈迦牟尼仏の一仏だけがましますと説き、それぞれの世界にそれぞれの仏陀がましますということを明らかにはしないのである。まして大乗仏教が主張する「すべて生きとし生けるものに、悉く仏性をそなえている」ということを説くわけがない。このように、たとえ一人の者にすら仏性の具有を認めないのである。それなのに、律宗・成実宗などが「十方に仏陀がまします」「(衆生に)仏性が有る」などというのは、仏陀入滅後、中国の学僧が大乗仏教の教義を自分の宗旨にとり入れてしまったためであろう。
たとえば、中国の外典やインドの外道などに思いをめぐらすと、釈尊が出現する以前の外道は、まだまだとらわれが浅い。ところが釈尊が出現されてから後の外道は、仏教を見聞して自分たちの教義の欠陥を知り、巧妙に繕う態度が顕われて仏教の教義を自分たちの教義として取り入れてしまうから、邪見が非常に深いことになる。仏法に添って外道の説を立てる者を「附仏教」といい、仏法を学んで外道の説を立てる者を「学仏法成」というが、それはこうした人たちである。
外典についても同様である。漢土(中国)に仏法がまだ渡来しなかった時の儒学者や道教家は、ゆったりしていて乳児のように幼稚であったが、後漢の明帝の永平十年(西暦六七年)に仏教が渡来して道教家との間で論争が行なわれてからのち、仏教がだんだんと世間に行き渡るにしたがって、仏教の僧侶が戒律を破ったためにもとの俗人に戻ったり、あるいは俗人に心を合わせたりする者が、儒教の中に仏教を巧みに採り入れたりした。天台大師は摩訶止観第五巻にいう。「今の世に多くの悪魔の僧がいる。彼らはいったん出家した僧が戒律を守れずにもとの俗人に帰り、処罰されるのを恐れて、再び道士(道教家)に戻るのである。さらに名利を求めて荘子や老子を自慢して語り、仏教の教義を巧みに取り入れて仏教に対立する儒教・道教などの典籍を解釈し、高い教えと卑しいものとをごっちゃにして、概(とかき)の棒でかきならしてしまう」。妙楽大師の摩訶止観輔行伝弘決には、以上の文章を解釈して次のようにいう、「僧の身となりながら、かえって仏法を破滅に陥れる者がある。〈いったん出家した僧がもとの俗人に帰り〉というのは、若くして出家しながら、後に俗に還り、周武帝に廃仏を上申した衛の元嵩らのようなものである。彼は俗に戻って仏法を破壊した。彼は仏教の正しい教えを偸(ぬす)み取って邪典である道教の典籍にそれを添加した。〈高い教えと卑しいものとをごっちゃにして〉というのは、道教家の立場で仏教と道教とをかきならしてしまい、邪なるもの・正なるものを一緒にしてしまったということである。本来、そのようなことはあり得ないのに、かつて仏法の門に入った知識を悪用して、正しい教えを偸(ぬす)み取って邪(よこし)まなものを助け、八万四千の法蔵・十二部経からなる仏教の高い教えを、わずか五千余言、上下二篇の道教の低い教えに押し込んで、道教の邪しまでいやしい教えを解釈した。それを、高い教えと卑しいものをごっちゃにする、というのである」。この解釈を見よ。これらは前に述べた仏法盗用の例である。
このようなことは仏教の内部でも行なわれた。後漢の明帝、永平十年に中国に仏教が渡来して、邪典たる道教が破られて仏教が立てられた。ところが、仏教において揚子江の南に三人の学僧、北に七人の学僧が現われて仏教解釈に対立が生じて、蘭菊が葉腋ごとに段をなして咲くように、それぞれの学説は異なるけれども、陳・隋の代に天台大師が出現して、それら江南・河北の十人の学僧の異なる見解を平定してしまったので、ここに仏教は再び一切衆生を救うことになったのである。
〔第三章〕 諸宗はなぜ批判されねばならないか
その後、法相宗・真言宗が天竺(インド)から中国に伝えられ、華厳宗も中国で再興された。これらの各宗の中で、法相宗は「一乗方便 三乗真実」を標榜して「三乗方便 一乗真実」をかかげる天台宗を批判している宗旨であって、両宗の教義は水と火のように対立している。ところが、玄奘三蔵とその弟子の慈恩大師窺基は天台大師の法華経の解釈を見たところ、自分たちの解釈が間違っていたことに気付いたためか、法相宗を捨てはしないが、その心は天台宗に帰伏したように見られる。華厳宗と真言宗とはもともとは実経実宗を明らかにするための経過的な経典に立脚する宗旨である。真言宗の祖、善無畏三蔵・金剛智三蔵は天台大師の一念三千の教義を巧みに真言宗の肝要に取り入れ、その上に印と真言という事相(じそう)を加えて、真言宗は天台宗より勝れていると主張する。そうした詳細を知らない学者たちは、もともとインドにおいて大日経の解釈に一念三千の法門が織り込まれていると思い込んでいる。華厳宗は、第四祖清涼(しようりよう)大師澄観の時に、華厳経の夜摩天宮自在品(やまてんぐうじざいほん)の「心は森羅万象を巧みに描く画家のように、すべてを写し出す」という経文の解釈に天台大師の一念三千の法門を巧妙に取り入れたのである。ところが後世の人はこのことを知らないのである。
わが日本国には華厳宗等の六宗が天台宗・真言宗が伝来する以前に伝えられた。華厳宗・三論宗・法相宗はそれぞれ一乗・三乗、空(くう)・有(う)などを主張して論争を展開し、お互いの主張は水と火のように相容れなかった。ところが、伝教大師最澄がわが国に現われて、南都六宗のまちがった理解を批判しただけでなく、真言宗が天台宗の法華経の教理を巧みに盗みとって、真言宗の基幹としていることをはっきりとさせたのである。伝教大師は各宗の学僧の見解にとらわれることなく、ひたすら経文を拠りどころとして批判を加えたところ、伝教大師が唐から帰国した延暦二十四年九月十六日、勅によって戒を受けて公験(くげん)(証明書)を与えられた南都六宗の八大徳、さらに十二人の高徳、また延暦二十一年正月十九日、和気弘世(わけのひろよ)の請によって高雄山寺で開かれた天台法華講会に列した善議・勝〓・奉基・〓忍・賢玉・安福・勤操・脩円・慈誥・玄耀・歳光・道証・光証・観敏の十四人をはじめとする三百余人、ならびに弘法大師空海らはその論議に帰服したので、ここに日本国中のすべてが天台宗に帰依して、南都六宗・真言宗の中心である東寺、さらに日本全国の山寺は皆すべて比叡山延暦寺(ひえいざんえんりやくじ)の末寺(まつじ)となったのである。また、漢土(中国)においても諸宗の元祖たちが天台宗に帰服して、正法を誹謗(ひほう)するあやまちを免れたことも明らかになったのである。
ところが、その後、だんだんと時代が衰退して人の智慧が浅くなるにともなって、このような天台宗の深遠な教義は見失われていってしまった。それに比べてその他の宗がそれぞれ宗旨を守ろうとする執心は強くなるばかりで、そのためにだんだんと南都六宗、それに真言宗を加えた七宗によって天台宗は貶(おと)しめられ、弱体化していったためであろうか、結局、南都六宗やそれに真言宗を加えた七宗にも及ばないこととなり、論議の対象にもならないはずの禅宗や浄土宗よりも低く見られるようになってしまい、はじめはその檀信徒たちがだんだんと禅宗や浄土宗に心を移していき、結局は天台宗の高徳な僧と仰がれている人々が皆、禅宗・浄土宗というまちがった宗旨を助けることになった。こうして、南都六宗、それに天台・真言の平安仏教二宗を加えた八宗の寺領が皆、禅宗・浄土宗の二宗のものとなってしまい、正しい仏法は見失われてしまうこととなった。そのため、日本国の守護神である天照太神・八幡大菩薩や比叡山に祀られて正法を守護する山王権現といったもろもろの大善神も正法(法華経)の滋味を嘗めないために威光勢力を失われたのか、もろもろの大善神が正法を失った国土を見捨てて去ってしまったためか、悪鬼がその代わりに入り込んでしまい、国がまさに破れようとしている。
〔第四章〕 二乗作仏論
ここに私(日蓮)の理解で釈尊一代の教化のうち、法華経以前に説かれた四十数年間の諸経と最後の八箇年に説かれた法華経との相違を考察してみると、その間の相違は数多くあるが、まず世間の学者も認め、私自身も充分に納得できることは、法華経の前半の主要課題である「二乗作仏」と、そして後半の主要課題である「久遠実成」とであろう。
具体的に法華経の経文を拝見すると、(譬喩品第三で)舎利弗尊者は将来の世に華光如来として成仏することが保証されている。次いで(授記品第六で)迦葉尊者が光明如来に、須菩提尊者が名相如来に、迦旃延尊者が閻浮那提金光如来に、目連尊者が多摩羅跋栴檀香如来にというふうに将来世において成仏することの記〓(きべつ)(保証)が与えられる。さらに(五百弟子受記品第八で)富楼那尊者は法明如来に、(授学無学人記品第九で)五百・七百の比丘・阿羅漢はすべて普明如来に、阿難尊者は山海慧自在通王如来に、羅〓羅尊者は蹈七宝華如来に、学・無学二千人の声聞はすべて宝相如来に、(勧持品第十三で)摩訶波闍波提比丘尼と学・無学の比丘尼六千人らは一切衆生喜見如来に、耶輸陀羅比丘尼は具足千万光相如来にというように、相次いで将来世において成仏をなしとげるという記〓が授けられている。
これらの方々は法華経を拝見すると尊い方のように思われるのだが、法華経が説かれる以前の諸経典をひらいてみると興ざめになることが多い。なぜかというと、世間・出世間にわたって尊敬される釈迦牟尼仏は真実の言葉を語る聖者である。だからこそ聖人(しようにん)とか大いなる人とよばれるのである。外典や外道の中で賢人とか聖人(せいじん)とか天仙などとよぶのも、真実の言葉を語るという意味で名づけられたものであろう。外典・外道のこれらの人々とは比較しようがないくらいに最も優れているからこそ、仏陀釈尊を大いなる人と尊称するのである。この大いなる聖者・釈尊は「諸仏世尊はただ一大事の因縁を以ての故に世に出現なされる」(法華経方便品第二)ことを明らかにされている。(法華経は真実を明らかにする経典であって)すでに無量義経説法品第二で「これまでの四十余年間の説法の間には真実を説きあらわしていない」と言い、方便品第二には「世尊は長い間の説法の後にかならず真実を説くであろう」「正直に方便を捨ててただこの上なき道を説き明かす」などと述べ、見宝塔品第十一では多宝如来が多宝塔とともに宝浄世界より来って、法華経が真実の法(おしえ)である旨の証明を加え、また如来神力品第二十一で釈尊の十方分身の諸仏が広長舌相を示してそれを讃歎している。このように真実の教えであることが説かれている経典において、舎利弗尊者が将来に華光如来となって人々を救い、迦葉尊者が将来、光明如来となるとの将来世の保証(授記)に誰が疑問を起こすであろうか。
しかし、法華経以前の諸経典もまた仏陀が語った真実の言葉である。大方広仏華厳経には次のように述べられている。「仏陀の智慧を大薬王樹に譬えるならば、この樹は二カ所では生長することができない。それと同様に声聞・縁覚はなすすべもない広く深い坑(あな)に堕ちてしまうし、また善根を破壊し、仏法を信奉することに堪えることのできない人間は大いなる邪見と貪愛の水に〓れてしまう」と。この経文の意味は、ヒマラヤの山に大樹があって、「はかり知れない根を持った樹(無尽根)とよばれた。これを大薬王樹とよび、この世界のもろもろの木の中の大王であった。この木の高さは十六万八千由旬である。この世界のすべての草木は、この木の根の張り具合や枝葉の茂り具合、華の咲き具合、果実の実る具合に準じて、その草木の華が咲き、果実が実るという具合であった。この木は仏陀の示す仏たらしめる本性(仏性)に譬えられている。そして、すべての人々をすべての草木に譬えている。ただこの大樹は火の坑(あな)と水の輪の中では生長しない。つまり、声聞・縁覚の二乗の心の中を火の坑に譬え、また一闡提(仏性を持っていない人間)を水の輪に譬えているのであって、これらの二類は永久に成仏することはできないことを示す経文なのである。
大集経には次のように述べられている。「二種類の人は死んでから決して生き返ることがなく、結局、恩を知ることも報ずることもできないのである。その一は声聞(自己のさとりのみを得ることに専念し、利他の行を欠いた出家修行者)であり、その二は縁覚(師なくして独自にさとりを開いた自己中心的な修行者)である。たとえば深い坑に堕ちてしまった人があるとしよう。この人は自力で坑から出ることもできず、また他人を助け上げることもできない。声聞や縁覚もまたこれと同様で、修行者自身の解脱(煩悩の束縛から解放されて自由な心境となること)だけにとらわれてしまうという坑に落ちてしまって、自らを助けることもできず、また他人をも助けることができないのである」と。
外典(儒教の典籍)には三千余巻が数えられるというが、その結論に二つある。すなわち孝と忠とである。そして忠もまた孝の思想から出ているのである。孝ということは高いということである(「孝」と「高」とは同音であるから、「孝」とは「高い」という意味を兼ね具えている)。天が高いといっても孝の徳より高いことはない。また孝とは厚いということであって、大地がどれほど厚いといっても孝の徳より厚いことはない(「孝」は大地よりも「厚い」のである)。儒教の説く聖人と賢人との二種類の人は「孝」を重んじる思想を根幹としている。だから、まして仏法を学ぼうとする人は恩を知って恩を報ずることが根本になければならないはずである。すなわち、仏弟子はかならず父母の恩・一切衆生の恩・国王の恩・三宝の恩という四つの恩を知って、「恩を知り恩を報じる」という命題に応えなければならない。そのうえ、舎利弗尊者・迦葉尊者ら声聞・縁覚は、比丘(男性の出家修行僧)がたもたねばならない二百五十戒をたもち、三千にも及ぶ修行者としての威儀を少しも欠けることなく整えて、静慮(じようりよ)に味着の心を残す境地(これを味の静慮という)、浄心にして味着を離れた境地(浄の静慮)、四諦(苦・集・滅・道の四つの基本的真理)を観じる聖者の禅定(無漏の静慮)という三静慮を体得し、阿含経が説くところを究めて、欲界・色界・無色界という迷いの世界(三界)の道理上の迷い(見惑)と感情的な迷い(思惑)を断ちきったのである。これは「恩を知り恩を報ずる」人の手本であるはずである。ところが釈尊は彼らに対して、恩を知らない者であると決めつけられた。その理由は、父母の家を出奔して出家の身となるのは何のためかといえば、結局のところ父母を救うためである。しかるに声聞・縁覚となった舎利弗・迦葉らは、自分自身では迷いから解き放たれる(解脱を得る)と思っているかも知れないが、他人を救いに導く利他の行ないに欠けている。彼らにたとえそれ相応の他人への救いの導きがあったとしても、父母たちを永久に成仏できない道に導き入れてしまったために、逆に恩知らずの者となってしまったのである。
維摩経の如来種品には次のように述べる。「維摩居士がまた文殊師利に質問した。『如来(仏陀)の種となるのはどのようなものなのか』と。答えて言う。『すべて心をまどわす煩悩の類(たぐい)こそ如来の種なのである。たとえ殺父・殺母・殺阿羅漢・破和合僧・出仏身血という無間地獄に堕ちる五つの罪を犯した者であっても、なお悟りを求める意(こころ)をよく起こすことができるのだ』」と。また言う。「たとえば良家出身の息子よ! 高原の乾燥した土地には青蓮華や芙蓉(蓮華)の香華は生育できない。逆にじめじめした汚い田圃(たんぼ)においてこそ蓮華の花が咲くのである」と。また言う。「すでに阿羅漢となってそれなりに真理を体得してしまった者は、さらに無上道を求める菩提心を起こして真実の仏法を身に具えることはできないのである。それはあたかも眼・耳・鼻・舌・身という五根に支障を生じた人が、色・声・香・味・触の五欲の楽しみを受けることができないと同様なのである」と。つまり経文の意図するところは、貪(むさぼり)・瞋(いかり)・痴(無痴)などの三毒を持っていたとしても、仏陀と成る種となることが可能であり、また殺父などの五逆罪などを犯したとしても仏種のはたらきは失われることがない。高原の陸土には青蓮華が生ずるであろう。だがしかし、声聞乗・縁覚乗という二乗の悟りに固まっている者は仏陀の覚りを得ることができないのである。その意味するところは二乗の善と凡夫の悪とを比較して、悪にまとわりつかれている凡夫が仏陀の覚りを得ることができたとしても、それなりの善に安住してしまった二乗は仏になることができないということなのである。さまざまな小乗経では悪を誡めて善を讃めたたえており、それが普通である。ところがそれに対して、この維摩経では声聞・縁覚の二乗の善を非難して、逆に凡夫の悪を讃めたたえている。かえって仏教の経典とも思えないほどである。異端を説く仏教以外の法門のようにも見えるけれども、結局は二乗が永く成仏しないということを決め付けているのであろう。
方等陀羅尼経に次のように述べる。「文殊師利が舎利弗に語る。『枯れた樹にもう一度、花が咲くことがあろうか。また山間を流れる水が再び水源に帰ることができるであろうか。いったん割れた石がもとどおりになることがあるだろうか。一度〓った種から芽がでることがあろうか』。舎利弗が言うには、『そのようなことはいずれもあり得ない』。文殊師利が言う。『もしあり得ないというのならば、あなたはどうして私に、菩提を得ることの保証を得られるかなどと問い質(ただ)して、心によろこびを生じさせようとするのか』」と。経文の意味は、枯れた木に花が咲くことはないし、山間を流れる水が再び水源に帰ることはないし、いったん割れた石がもとどおりになることはないし、一度〓った種から芽が出ることもないのであって、声聞乗・縁覚乗の二乗もまたこれと同様に、心を固く閉ざして仏種を〓ってしまったのである。
大品般若経の問住品に言う。「もろもろの天の子よ! 今まだ無上等正覚(この上ない覚り)を求める心を起こさない者は、当然菩提心を起こすであろう。もし正しく声聞の位に入った者であるならば、この人は無上等正覚を求める心を超こすことができないであろう。なぜならば、声聞の悟りが却って生死を起える道の障害となるからである」と。経文の意味は、声聞乗・縁覚乗は心を閉ざして菩提心を起こさないから、私(須菩提)は喜ばない。もろもろの天は菩提心を起こすから、私は喜ぶのである、ということである。
首楞厳経にいう。「仏教徒として犯してはならない五逆罪を犯した人は、この首楞厳三昧を耳にするならば、無上のさとりの心を起こすから、かならず仏陀となることができよう。世尊! それに対して、煩悩が尽きてしまった阿羅漢(声聞)は、あたかも毀(こわ)れた器のように、永久にこの三昧を受けるに堪える器量がないのである」と。
浄名経(維摩経)の弟子品にいう。「汝らに施しをする者は善き行為の種子を蒔いて功徳の収穫を得る福田とは名付けることはない。汝らに供養を差し出す者は地獄道・餓鬼道・畜生道という三悪道に堕ちるのだ」と。経文の心は、迦葉・舎利弗ら聖僧とあがめられる方々に供養を捧げる人や天はかならず地獄・餓鬼・畜生という三悪道に堕ちるであろうというのである。これらの聖僧は釈尊を除いては人天の眼(まなこ)であり、すべての人々の導師であると思ってきたのに、人天が大勢集まっている釈尊の説教の満座の中で、このようにたびたび、「声聞・縁覚の煩悩を断じ尽してしまった者はかえって菩提心をとり戻すことができない。仏道を真に完成することはできない」と批判なさったことは、(迦葉や舎利弗らにとって)やるせない思いであったろう。結局のところ、釈尊はご自分の弟子たちを責め殺そうとしたのではないかとさえ思われてくる。
このほかにも、牛乳とロバの乳とのような優劣がある(大智度論)とか、壊れた素焼きの器は価値がなくなってしまうが金や銀の器は壊れても本来の価値を失うことがない(清浄毘尼方広経(しようじようびにほうこうきよう))とか、太陽の光と蛍(ほたる)の灯では違いがありすぎる(維摩経)、などなどのさまざまなたとえによって声聞・縁覚を叱りつけた。それも一言・二言や一日・二日や一箇月や二箇月の期間にとどまらず、一年・二年や一つの経典や二つの経典だけで終ってはいない。(法華経が説かれる以前の)四十数年の間に数限りなく説かれた経典のなかで、しかも無量の人々に対して、一言とてやさしい言葉を添えることもなく叱責されたのである。釈尊は決して偽りの言葉を述べられないと自らも信じ、人も信じ、天の神も信じ、地の神も信じているが、それほどに強い叱責なので、一人・二人だけでなく百千万人、欲界・色界・無色界という迷いの三界にいる人間と天人・竜神・阿修羅、そしてインド全体、東・西・南・北の四州、六欲天、色天と無色天、十方の世界から雲のごとく集まった人間と天人、声聞・縁覚や大菩薩たち――これらの方々のすべてが、釈尊が声聞・縁覚を叱責した様子を知り、聞いた。その上にそれらの方々が十方世界の国々へ帰って、娑婆世界での釈尊の説法の様子をそれぞれの国々で詳細に語ったのであるから、十方の無辺の世界のすべての人々のことごとくが、迦葉や舎利弗ら声聞・縁覚は永久に成仏できない者であって、だから彼らを供養してはならないと認識するに至ったのである。
ところが、釈尊一代の説法五十年のうち、最後の八年間に説かれた法華経において、それまでの所説を訂正して、声聞・縁覚の二乗が将来仏陀となるであろうと釈尊がお説きになったのであるから、そこに集うた多くの人間と天人はただちにその言葉を信じることができようか。とても信じることができないどころか、却って法華経以前・以後の諸経典に対しても疑問を持ってしまい、その結果、釈尊五十余年の説教が皆、そらごととなってしまったことであろう。そうであるとすれば、法華経以前の四十余年にはいまだ真実を説き顕わしていないという経文はあり得るのであろうか、あるいはまた天魔が仏陀の姿となって出現して、釈尊五十年の説法のうち最後の八年間に法華経を説いているのだろうかなどと説法の座に集うた人間と天人たちが疑問を起こしているところに、まことしやかにこれこれの劫(時代)、これこれの国に、これこれの仏陀の名で、声聞・縁覚が仏道を完成するであろうと保証(記〓)を与え、教化を受ける弟子などをお定めになったので、教主釈尊のお言葉は前に言ったことと後に言ったことが違ってしまった。自語相違というのはこのことである。仏教を否定する外道が釈尊を大妄語の人(大いに虚妄の説を吐く人)だと笑ったのはまさにこのことである。こうして、人間・天人ら、説教の聴集全体が興ざめになっていたところ、そのときに東方の宝浄世界から来た多宝如来が、高さ五百由旬、広さ二百五十由旬という七宝に彩られた大宝塔の中に坐って出現なさった。つまり、教主釈尊が説教聴聞の人天大会(にんでんだいえ)(人間・天人らの聴衆)に自語相違ではないかと責められて、ああも言ったりこうも言ったりして、いろいろとお述べになったのだけれども、人々の疑問はなお晴れずに、もてあまされておられたときに、大宝塔が釈尊の前に大地から涌くように現われて中空に昇ったのである。それはあたかも暗闇の夜に満月が東の山から出たように感激的であった。大七宝塔は中空にとどまり、大地の上に降りるのでもなく虚空に高く消えるのでもなく、中空に留まって、宝塔の中から多宝如来が仏陀の三十二相好のうちの梵音声(ぼんのんじよう)(清浄なるお声)を出して法華経が真実であると次のように証明したのである。「そのときに宝塔の中から大音声を出して歎めておっしゃった。『よいかな! よいかな! 釈尊はよく平等にして大いなる智慧、菩薩を教える法、仏陀に護り念ぜられる妙法蓮華経を多くの人々のためにお説きになった。かくのごとくである、かくのごとくである。釈尊の所説は皆これ真実なのである』」と。
また如来神力品において十方の世界で法を説く釈尊の分身の諸仏の讃歎が次のように語られた。「そのときに、釈尊は文殊師利菩薩をはじめとする無量百千万億のこの娑婆世界に旧(ふる)くから住している菩薩たちや、その他、人々や半神・鬼神などすべての方々の前で大神力(大いなる不思議な力)を現わされた。すなわち、広く長い舌を出して、はるか上方の梵天の至らせ、身体中の毛孔から無量無数の色の光を放って皆ことごとく遍(あまね)く十方の世界を照らし出された。もろもろの宝樹の下の師子座の上にましますもろもろの仏陀もまた同様に広く長い舌を出し、無量の光を放たれたのである」と。次にこれをうけて嘱累品において釈尊は次のように語られた。「(その時に釈尊は)十方の世界から来り集まったもろもろの分身仏をして、それぞれの本土に帰っていただこうとして、このように仰せられた。『もろもろの仏陀がた! それぞれ安んじるところに随って下さい。多宝如来の七宝の塔は、もとのように閉じて下さいますように』」と。
大いなる覚りを開いて世間・出世間の方々から称讃される釈尊がブッダガヤの宝樹下の金剛宝座で初めて成道を遂げられたとき、それを見てもろもろの仏陀が十方に現われて釈尊をなぐさめられたうえ、もろもろの大菩薩を使いとして遣わされた(法華経方便品)。般若経を説法なさったときには釈尊が長い舌を伸ばして三千世界を覆い、千仏が十方に出現なさった(摩訶般若経舌相品)。金光明経の説法のときには四方の四仏が出現なさった(金光明経寿量品)。阿弥陀経の説法のときには東西南北の四方と上下の六方世界の諸仏が舌を出して三千世界を覆われた。大集経の説法のときには十方の諸仏や菩薩がことごとく集まり来って、欲界と色界の中間の大宝坊に集まられた(大集経瓔珞品)。
これら諸経の所説を法華経と対比して考察すると、黄色いだけの無価値の石と黄金と、白い雲と白い山と、白氷と銀鏡と、黒色と青色との違いを、かすみ眼の人、すが眼の人、片方を失明した人、正しく見ようとする眼を持たない人は、はっきり認識することが困難であるに違いない。華厳経は最初に説かれた経典で、前後の経典との比較がないから、仏陀の語として相違というものはなく、どこからも大きな疑いが出て来るはずがない。大集経、大品般若経、金光明経、阿弥陀経などは、さまざまな小乗経の声聞・縁覚が小乗に滞ることを叱り責めるために十方に浄土があると説いて、凡夫・菩薩をして敬い慕わせ、声聞・縁覚を思いわずらわせた。小乗経と大乗経との間にはいささかの違いがあるからこそ、あるいは十方に仏陀が出現され、あるいは十方の世界から大菩薩を使いとして差し向け、あるいは十方の世界においてこの経を説くゆえんを示し、あるいは十方の世界からもろもろの仏陀が集まられた。あるいは釈尊が舌を伸ばして三千世界を覆い、あるいはまた諸仏が舌を広く長く伸ばして(この経を)讃めたたえるゆえんを説かれた。これはもっぱらもろもろの小乗経が、十方世界の中で眼前の釈迦牟尼仏だけがたったお一人の仏陀であると説いている考えをうち破るためであった。法華経はその後のさまざまな大乗経典と大きな教理の違いを持っているために、舎利弗らもろもろの声聞・大菩薩や人・天(人間界と天上界)らが、「この法華経は実は魔が釈尊の姿となって現われて説いているのではないか」と大疑問を起こしたが、今述べていることはそのような重大な事ではない。ところが、華厳宗・法相宗・三論宗・真言宗・念仏宗らのかすみ眼の人たちは、彼らが信奉するそれぞれの経典と法華経とは同じ内容であると思い込んでいる。まことに愚かな認識というほかないのである。
ただし、釈尊がインドに出現し、説法したときには、法華経以前の四十数年間に説かれた経典を措(お)いて、法華経の教えに帰敬した人も或いはあったことだろう。しかし、釈尊の入滅後にこの法華経を聞き見て信奉することは非常に困難であろう。なぜならばまず第一に、法華経以前の諸経典は言葉の数が圧倒的に多いのに対し、法華経はわずかに一言。また、法華経以前の諸経典は数が圧倒的に多いのに対して、法華経はその中でわずかに一経である。また、それぞれの諸経典は長い年月にわたって説かれているのに対して、この法華経はたった八年間だけ説かれたのである。こうして見ると、仏陀は大妄語の人で、永久に信じることができないことになる。そのような不信感をそのままにして、強いて信じようとするならば、法華経以前の諸経典は信じられるかも知れないが、法華経は永久に信じることができない。今の世を見ても、法華経を皆が信じているようであるけれども、それは本当に法華経を信じているのではない。なぜかといえば、法華経と大日経とが、法華経と華厳経とが、そして法華経と阿弥陀経とが同じような内容であると説く人に喜んで帰依し、法華経が諸経典を超えて格段に優れた内容をもっていると主張をする人を支持しないのである。たとえそれを受け容れたとしても、不本意なことだと思っているからである。
日蓮はこれに対して決然として言う。「日本に仏教が渡来して、すでに七百年余も経過しているが、その間、たった一人伝教大師だけが法華経を正確に理解している、と私が明言しているのにその意見を用いない」と。ただし、法華経の見宝塔品を見ると「もし世界で最高の須弥山を手にとって無数の他方の世界に抛り投げたとしても、まだまだむずかしいことのうちには入らない。(中略)それに対して、もし釈尊の御入滅後、悪い世の中において困難を押し切ってこの法華経を説くこと、このことは大変むずかしいことなのである」と説かれている。こうしてみると、日蓮の強い主張こそ法華経の経文にぴったり一致する。法華経の教義を布衍(ふえん)する涅槃経に「末の世になると正法を誹謗する者が十方の大地のようにたくさんになり、正法に従う者は爪の上に載った土ほどに少なくなってしまう」と説かれているのを、どのように解釈したらよいのであろうか。日本の諸人が爪の上の土ほどに少ない正法護持の者なのか、日蓮は果たして十方の大地のように数多い正法の誹謗者であるのかをよくよく考察しなさい。賢い国王が世を治めているときには道理が勝つ世の中となるであろうし、逆に愚かな国主が世を治めるならば道理にはずれることがまかり通るであろう。そして智慧が広大で、慈悲心の深い聖人が出現した時代にこそ法華経の真実義が明らかにされるであろうことを心得ねばならない。二乗作仏という法門(教え)を明らかにされた法華経の迹門と、法華経以前の諸経とを先ほどのように対比してみると、法華経以前の諸経の所説の方に分があるように思われる。(けれども)もし、法華経以前の諸経の方が強く真実であるということになると、舎利弗をはじめとする声聞・縁覚たちは永久に成仏することのできないことになってしまう。そうなれば、それらの方々はどれほどお嘆きになることであろうか。
〔第五章〕 久遠実成論
第二には、教主釈尊は、四劫のうち大世界が成立して行く成劫(じようこう)に次いで、人間や動物たちが暮らせるようになる住劫という時期のうち、第一から第十までの増劫の後、減劫に転じて第九の減劫という時代にお出ましになった。人間の寿命が百歳の時代に、師子〓王の孫、浄飯王の嫡子として生を享け、童子の頃の名は悉達太子、一切義成就菩薩(悉達はシッダルタで、すべての教えを完成するという意味)である。(大智度論によると)御年十九歳で宮殿から出奔して修行をかさね、三十歳で成道(さとりを開き)なさった釈尊は、そのさとりを開いたガヤ城の南にある菩提樹の下の道場で華厳経を説き、中道実相観によって得た実報土に毘盧遮那仏(びるしやなぶつ)の願行(がんぎよう)によってかざられた蓮華蔵世界を現わした。そして、「十玄門」と「六相円融」の教えを説き、法界はそれぞれの立場にありながら、互いに融けあって妨げのない世界にあること、はじめから微妙を極めた大いなる法であることを明らかにした。その時、十方の諸仏もその場に出現し、すべての菩薩も雲が湧くように相い集うたのである。そのように華厳経の説法は、国土についても、法を聞く機の高さからいっても、諸仏が相い集うた点からしても、釈尊がおさとりを開いてから始めての説法である点からしても、法をすべて説き明かす条件が整っていて、いかなる点からしても大いなる法を秘密にしておく必要はない筈である(日蓮聖人は教・機・時・国・師〔または序〕の五義によって法華経が勝れていることを明らかにした。このような観点から国土=国、機=機、諸仏=師、始=時、法=教の各方面から華厳経の内容を検討する)。
だから華厳経の入法界品には、「自在なる力を顕現して円満なる経(完全無欠な経典)を演(の)べ説きたもう」と述べる。これによれば、華厳経六十巻は一字一点も欠けるところのない完全な経典である。たとえば如意宝珠というものは、意の欲するままに珍宝を出す珠であるから、一つの珠があっても、無量の珠があっても同じことである。つまり、一つの如意宝珠もかずかずの宝物を出し尽すのだし、数えきれないほど多くの如意宝珠があったとしても、同様に教えきれないほど多くの宝物を出すことにおいては全く同じことになる。つまり華厳経は一字であっても万字であってもその教えの尊さはただただ同じ事なのである。「心と仏と衆生とこの三には差別がない」という経文は、ただ華厳宗の肝心な教えであるだけでなく、法相宗・三論宗・真言宗・天台宗にとっても肝要の教えなのである。これほどまでに尊い御経である華厳経に一体どのような事を隠す必要があるだろうか。しかしそれにしても、声聞乗・縁覚乗の二乗と一闡提(無性の有情)とは成仏することがないと説かれたのは、せっかくの素晴らしい宝玉に疵(きず)があるように見えるうえ、三カ所までも「釈尊は始めて正覚(さとり)を開いた」と言って、釈尊がすでに久遠の往昔において成道を成し遂げたことを説く法華経の如来寿量品と同じ内容をお説きにならなかった。それではせっかくの宝玉にひび割れがあるようなもの、満月に雲がかかってしまったようなもの、太陽が日〓になってしまったようなもの。不思議なことであった。
華厳経が説かれたのち、阿含経、方等部の諸経典、般若経、大日経などは、仏陀の説きたもう教であるから尊い教えであることは当然ではあるが、華厳経と比較したならばとりたてて言うほどのこともない。したがって、華厳経に秘密にした内容が阿含経以下の経典に説かれるわけがない。だからもろもろの阿含経には「初めに成道して」などとあり、大集経の瓔珞品には「釈迦如来が始めて成道してから十六年を経て」などと説かれ、維摩経(浄名経)の仏国品には「始め菩提樹の下(もと)に坐って、禅定の力で魔を下した」と言い、大日経の具縁真言品には「われは昔、道場に坐して」などといい、仁王経の序品には「前にすでに我等大衆(だいしゆ)の為に二十九年、摩訶般若波羅蜜を説きたもう」と述べられた。これらについてはとやかく言うまでもないことである。ただわが耳を疑い、目を疑うことは、法華経の開経(序説)である無量義経に、華厳経の「あらゆる存在は心の変現であって、心がすべてを顕現する」と説く唯心法界(ゆいしんほうかい)の法門や、大方等大集経の「海中にあらゆる存在の影を写すように、仏の智慧の海にすべての法を印現する専念作用を説く」という海印三昧の法門や、般若経の「あらゆる存在は因縁によって生じるところであって、本来の自性はないから、差別すべきものはない」と説く混同無二の法門などの勝れた哲学的内容を含む法門を列挙して、すべて「これまでの四十余年間の説法はいまだ真実を顕らかにしていない」と言い、「方等・十二部経・摩訶般若(まかはんにや)・華厳海空(けごんかいくう)を説いて菩薩の歴劫修行を宣べ説く」などと言って、諸経を批判して攻めている無量義経であるのに、「われ釈尊はすでにブッダガヤの菩提樹の下の道場で端坐すること六年、この上なき覚りを達成したのである」と述べて、前に否定した初成道の時に華厳経に「始めて菩提(さとり)を達成した」と説いた経文と同じ内容を説いていることである。これは不思議なことだなという思いにかられるところではあるが、まだこれは法華経の前段の説であるから、本論の大切なことを言わないということもあると考えてよいのであろう。
ところが、法華経の正宗分に入ってからも、「略して三乗を開会して一乗を顕わす」、また「広く三乗を開会して一乗を顕わす」という法華経の開会の法門が説かれるとき、「唯、仏と仏とのみがいまし能く諸法実相を究め尽したもう」、「世尊は法を説くこと久しき後に、かならずまさに真実を説くであろう」、「正直に方便を捨てて、ただ無上道を説く」などと説き、さらに多宝如来が大宝塔に乗って出現して、迹門の方便品から授学無学人記品までの八品(八章)を指して、「今まで説いてきた内容は皆真実である」と証明なさって、もはや釈尊は何事も隠すことがないはずである。それなのに釈尊が久遠(永遠)の寿命をお持ちでいらっしゃることは胸に秘められて、「われ釈尊は始め道場に坐して、菩提樹を観じ、またその周囲を静かに歩き廻られた」と語っているのは、最も第一の不思議である。
だからこそ、法華経以前の四十余年の間、全く見たこともない大菩薩たちが突然従地涌出品の説法の場所に現われ、釈尊が「これらの大菩薩たちを教化して菩提心を起こさせたのだ」などと説かれたの対して、弥勒菩薩は疑って次のように言ったのである。「釈尊がまだ伽毘羅国(かびらこく)の太子であったとき、釈迦族の宮殿を出て伽耶城にほど近いブッダガヤの菩提樹の下(もと)の道場に坐して無上等正覚を達成なさった。それから始めて四十余年を経過したとはいえ、しかし、釈尊はどうしてこのようなわずかな間に、これほど大いなる教化をなさることができたのでしょうか」と。教主釈尊は、弥勒菩薩が代表して申し上げたこの疑問に答えるために如来寿量品を説こうとして、法華経以前の諸経典・法華経迹門の聴衆の理解を挙げて、その答えを明らかにした。「すべての世間の天や人々、そして阿修羅は、一様に、今の釈尊は釈迦族の宮殿を出て伽耶城にほど近い菩提樹の下の道場に坐して無上等正覚を達成なさったと思っている」と。釈尊はまさしくこれに答えられる。「それにもかかわらず、良家の息子たちよ、われ釈尊は実に仏道を完成してから無量無辺百千万億那由他劫という無限の時間を経過しているのである」と。
華厳経から般若経、大日経に至るまでの諸経は声聞乗・縁覚乗の二乗がやがて菩薩道にめざめて成仏をとげることを意図的に説かなかったばかりでなく、釈尊が無限の過去から永遠の救済をつづけていることを明かす久遠実成の意義もわざと説き明かさなかった。これら法華経以前の諸経典には二つの過失がある。このことを妙楽大師の法華玄義釈籤には次のように要約している。その第一は、「段階や区分を重んじるために、まだ十界はそれぞれ隔てられたものという仮の教えのままにとどまって」おり、迹門の一念三千をまだ隠している。第二には「釈尊がブッダガヤの菩提樹下で始めて成道なさったとして、久遠実成の釈尊の垂迹であることを明らかにせず」、法華経の本門に説かれる釈尊の久遠をまだ明らかにしていない、と。この二乗作仏・久遠実成という二つの大法は、釈尊の一代の説法の脊髄であり、すべての経典の心髄である。
法華経の迹門の中心をなす方便品は、一念三千の教えと二乗作仏(声聞乗・縁覚乗に在る者も真の仏道を達成できるという仏陀の導き)を説いたので、法華経に至る前段階の経典がもっている二種類の失点のうちの一つをまぬがれることができた。しかしそうはいっても、まだ迹門の教えをひらいて本門の主旨を顕らかにしていないから、真実の一念三千も明らかにされるに至らず、したがって、せっかく説かれた二乗作仏の根底が明確にされないから、決して定まったことにはならない。あたかもそれは、水面に浮かんだ月の影を見るようなものであり、根無し草が波の上に浮かんでいるようなものである。しかし、本門に至って、釈尊はたまたまブッダガヤの菩提樹の下で覚りを開いたのではないことが明らかにされれば、釈尊の教えは蔵教(ぞうきよう)・通教(つうぎよう)・別教(べつきよう)・円教(えんぎよう)という四つの教えに集約されると理解してきたことは、表面的なものであることがはっきりし、それらの四教による限りでは釈尊の覚(さと)りを示すには充分でないことが明確にされるならば、四教が示した覚りに至る修行の道筋も否定されることになる。こうして、法華経の前段階の諸経典や法華経の迹門に説かれた「十界の因果」は充分に確立していないとし、仏界の確立を中心とする「本門の十界の因果」が説き明かされた。これがすなわち本因(ほんいん)・本果(ほんが)の教えである。ここにおいて地獄界から菩薩界に至る九界は無始の仏界(永遠なる仏界)に包まれ、仏界も無始の九界(永遠の衆生)の中におのずから備わっている救済の様相が示され、真実の十界互具・百界千如・一念三千が明らかにされるに至ったのである。
このようにふりかえって見ると、蓮華台上で華厳経を説く毘廬遮那仏とすべての事象は真実の智を説く仏(解境の十仏)、菩薩が成就し得た仏身(行境(ぎようきよう)の十仏)、阿含経を説く一丈六尺(約四・八メートル)の肉体を持つ釈迦、方等部諸経典や、般若経や、金光明経や、阿弥陀経や、大日経などを説く仏陀はいずれも権(かり)の姿であって、この法華経の如来寿量品を説く久遠実成の釈尊が天空に浮かぶ月であるとすれば、権の姿の仏陀はかりそめにその影を大小の器の水の上に浮かべるように姿を現わしたにすぎないのであるのに、諸宗の学者たちはそのことを知らないで、近くは自分が信奉する宗旨のとりこになっていたり、遠くは法華経の如来寿量品の説示を知らないために、水面に浮かんだ月(権仏(ごんぶつ))を本当の月(実仏)だと思い込んだり、はては水の中に入ってそれを取り押さえようと思ったり、縄でしばってつなぎとめようとするのは同じようなことをしているのである。天台大師智〓が法華玄義巻七上に、「(迹因にとらわれて本因と思い込むのは、迹も知らないし、また本も知らないということであって)天に浮かぶ月を知らずに、ただ池に映った月を本当の月と思って観ているようなものである」と述べているとおりである。
日蓮が心配に思うのは、法華経迹門に説かれる二乗作仏ですら、なお法華経以前の諸経の方に分があるように思われることである。法華経本門に明らかにされる久遠実成は、それにもまして法華経以前の諸経に分があるように思われるに違いない。それはなぜかといえば、法華経以前の諸経典と法華経とを比較してみると、法華経以前の諸経典の方が分がある上に、法華経以前の諸経典だけでなく、法華経の前半=迹門の十四品(十四章)もまったく法華経以前の諸経典に同意している。後半=本門の十四品(十四章)も、従地涌出品第十五、如来寿量品第十六の二品(二章)以外は皆、釈尊がブッダガヤで始めてお覚りを開いたことを述べている。釈尊入滅の地・クシナガラで説かれた最後の経典大般涅槃経四十巻、そのほか法華経前後に説かれたもろもろの大乗経典には法身が法性の理体身であるから無始無終であると説いているが、一言として応身の釈尊が久遠の報身の応現であることを明らかにしていない。どうして、広く説かれている法華経以前の経典、法華経の迹門と本門、涅槃経などの諸大乗経典の説述を否定して、ただ従地涌出品・如来寿量品の二品(二章)の説示に従えよう筈があろうか。
だから法相宗という宗を考えると、西方のインドで釈尊が涅槃に入られて九百年後に無著菩薩という大論師が居られた。夜は都率天の内院に昇って、弥勒菩薩に対面して釈尊一代五十年間に説かれた聖(とうと)い教えについて疑問点を解決し、昼間には阿輸舎国で法相宗の教義を弘められた。そのお弟子は、かの世親・護法・難陀・戒賢らの大いなる論師たちである。それに対して中インドの曲女城の王である戒日大王は頭を垂れて帰依を表明し、東・西・南・北・中央のインドの異流の人たちも旗印を降ろしてこの教えに帰依した。中国の玄奘三蔵は(大唐西域記によって知られるように、貞観三年(六二九)八月、長安を発って)大月氏国に到達してから十七年の間にインド百三十余カ国の国々を見聞して、同十九年三月、長安に帰り、諸宗を振り切ってこの法相宗を中国の地に伝え、太宗皇帝と呼ばれる賢い国王にこの教えを授けられた。そして、神肪(じんぼう)・嘉尚(かしよう)・普光(ふこう)・窺基(きき)を弟子として養成し、大慈恩寺をはじめとして三百六十余カ国に弘められた。日本国では、第三十七代の孝徳天皇の御代に、道慈・道昭らが法相宗を学び伝え、山階の地に興福寺を創建してこれを崇めた。インド・中国・日本の三国において第一の宗であろう。この法相宗が主張するのには、「最初の華厳経から最後の法華経、涅槃経に至るまで〈本来、仏性を身にそなえていない者〉と、そして〈最初から声聞・縁覚の世界に止まることを決定されている者〉は、決して成仏できない」という。仏陀の言葉に二言は有り得ない。一度、永久に成仏することができないと決めつけられた以上、たとえお日様やお月様が大地に堕ちたとしても、大地がひっくり返っても、決してこれを変更されることはないであろう。だから、法華経、涅槃経の中でも、法華経以前の諸経典において嫌った〈仏性を本来、身にそなえていない人々〉〈はじめから声聞乗・縁覚乗にしか到達することができないと決定している者〉に対してはっきりと指示して、成仏できるとは説かれていない。まず、眼を閉じてしっかり考えてみよ! 法華経、涅槃経において〈はじめから声聞乗・縁覚乗にしか到達することができないと決定している者〉〈仏性を本来、身にそなえていない人々〉が今までの解釈を百八十度回転して、まさしく一仏乗(真実の仏道)を達成するというならば、インドの大仏教思想家である無著や世親、そして中国において経・律・論の三蔵に通暁して学僧である玄奘・慈恩といった方々が、これを見知らないことがあるだろうか。このことを書きとどめないでおくことがあるだろうか。このことを伝えないはずがあろうか。弥勒菩薩にその疑問をぶつけないということがあろうか。(そんなはずはない。)あなたは法華経の経文を文証としているようであるけれども、ただ天台・妙楽・伝教の道理に合わない見解を信じきって、その見地から経文を見ているから、法華経以前の諸経典と法華経との主張の違いは水と火のように異なっていると見ているのではないか(と、法相宗は言う)。
華厳宗と真言宗とは、法相宗や三論宗に似ても似つかないほどはるかに勝れた宗旨であると、それぞれ主張している。彼らは言う。「二乗作仏・久遠実成という教えは法華経だけに限ることなく、華厳経や大日経に明らかなとおりである。中国華厳宗の宗祖から第四祖までの列祖、杜順・智儼・法蔵・澄観、そして真言宗の善無畏・金剛智・不空といった方々は、天台大師や伝教大師とは比較にならないほど位の高い人とされ、そのうえ善無畏三蔵らは大日如来から由緒正しい奥義の相承を受けている。人々を教え導くために仏陀が権(かり)に姿を現わしているこれらの方に、どうして誤りがあるだろうか。だからこそ、華厳経の入法界品(にゆうほつかいほん)には、『あるいは釈迦が仏道を成じおわって不可思議劫という長時間を経過したのを見る』などと述べ、大日経の漫荼羅行品(まんだらぎようほん)には『我(毘盧遮那世尊=大日如来)はすべての本初(根源)である』と述べている。どうして久遠実成が法華経の如来寿量品にだけ説かれているというのか。そのように思うのは、たとえば大海を見たことがない井戸の蛙の所見のようなもの、都を知らない山に住む木樵(きこり)の考えのようなものである。あなたはただ如来寿量品だけを見て、華厳経、大日経などのもろもろの経典を知らないのか。重ねて言えば、インドおよびその周辺、中国や朝鮮半島の新羅(しらぎ)国・百済(くだら)国などでも、一様に二乗作仏・久遠実成は法華経だけが言っているとされているのか、大いに疑わしい」。
こうした見解に従えば、釈尊が晩年の八年間に説かれた法華経は、それ以前の四十数年間に説法されたさまざまな経典と比較して、一段と勝れた内容を持っているといっても、また一般社会の法制の常識に従って、前に約束した証文と後から訂正した証文とでは、後からの証文を用いるのが当然だといっても、法華経以前の方に分(ぶ)があるように思うであろう。また、ただ釈尊がインドで説法していらっしゃった時には、前の証文よりも後に訂正した証文に拠らねばならないことが理解されたであろうが、釈尊の入滅後に活躍したインド・中国の学僧たちの多くは、法華経以前の諸経を拠りどころとしたのである。このように法華経は信じがたいうえ、時代もだんだんと衰えてくると、聖人・賢人は社会の中枢から遠ざけられ、真理を確かめることのできない人々がだんだんと多くなってくる。それらの人々は、一般社会の常識的な事ですら誤った理解に陥りがちなのである。まして出世間の深い意義を内包する仏法を誤りなく理解することができるであろうか。犢子や方広は聡敏だったけれども、それでも大乗経典が小乗経典に勝れることを見定めることができなかった。また無垢論師は説一切有部(せついつさいうぶ)を学びながら世親(せしん)の学派をのけものにして大乗を否定したために狂乱のうちに死し、摩沓婆は数論(すろん)学派(外道の一)を究めて名誉を得て、のち法論に破れて死んだが、彼らも勝れた機根を持ちながら、いずれが権教(ごんきよう)(方便教)であり、実教(じつきよう)(真実教)であるかをわきまえることができなかったのである。釈尊入滅の後、正しい法が流布している一千年の間は釈尊の生存中から時間も経過していないし、彼らはインドや周辺の国で学んでいたにもかかわらず、もうこんな状態であった。まして仏教が中国から日本などへ伝わって来れば、国の状態も変化し、言葉も変わり、法(おしえ)を聞く人の機根も衰えてくる。それに、寿命も短くなり、仏教で三毒として戒めている貪(むさぼ)り・瞋(いか)り・無知も倍増してくる。かくして釈尊が世にあらわれた時代から遠ざかって年月を重ね、仏教経典の理解が皆誤ってくる。このようなとき、いったい誰の理解が正しく法を受けたものといえるだろうか。釈尊は涅槃経に末世の将来を予言して、「末の代には正しく法を受けとる者は爪の上に載った土のように少ないのに対し、正しい法を誹謗(ひぼう)する者は十方に広がる土のように多い」と述べている。また、法滅尽経には、「正しい法を誹謗する者はガンジス河の沙ほど多く、正しい法を受け継ぐ者は、その中にある一つ二つの小石のようにごく稀である」と予告しておられる。こうした聖語を聞くと、千年・五百年に一人ほども正しい仏法を受け継ぐ人はいないのではないか。世俗で罪を犯したために悪道に堕ちる人は爪の上の土ほども少なく、仏法を誹謗する罪によって悪道に堕ちる人は十方に広がる土のように多い。そして、世俗の人よりも出家した僧の方が、また世俗の女性より出家した尼僧の方が多く悪道に堕ちるのであろう。
〔第六章〕 受難を覚悟しての発願
ここに日蓮は案じて言う。時代はすでに末法に入ってもはや二百年余(釈尊入滅後二千二百年余)、インドから見れば辺境の地・日本に生を享(う)けたのである。そのうえ、下賤で貧道の身としてである。過去世をふり返れば、迷いの六道を輪廻している間には人間や天人の大王として生まれて、万民がちょうど大風に吹かれた小さな木の枝のようになびいたときにも、仏道を達成することはなかった。大乗経・小乗経を勉強して、仏道修行に入った初歩の修行者(外凡)、ある程度まで修行が進んだ修行者(内凡)がやがて大いなる菩薩となり、涯(はて)しなく永い時間を一劫と数えて、一劫・二劫どころか、無量劫という気が遠くなるほど永い時間を経過する間に菩薩の修行を誓い、仏道を修行し、もはやそれまでに得た功徳を失わない位に当然入るはずであるときにも、あまりにもつよい悪縁におとしめられて仏陀となることができなかった。法華経化城喩品(けじようゆほん)に照らせば、かつて大通智勝仏のとき、十六王子が法華経のあらましを覆講(ふつこう)したときに、法華経の永遠の救いに縁を結びながら、その場で得道できずに仏陀の入滅後に得道するように予定されている第三類の者であったが、釈尊在世の時代に得道できず、末法の今やっと法華経に出会えたのであろうか。または法華経如来寿量品に照らせば、五百塵点という久遠の往昔に仏種を受けた者が、途中で修行の志を見失ったが、今、末法の世に生まれてきたのであろうか。
法華経を修行してきたために、世間の悪縁や国王からの迫害、外道からの迫害、小乗経を信奉する人からの迫害などは耐えしのんできたものの、権大乗や、実大乗の奥深い教えに通暁した中国浄土教の二祖道綽、三祖善導、そして日本の法然らのように真実が見えなくなった者が、法華経を強く褒めあげながら、その高い教えには人々の機根が堪えることができないとし、「法華経の教理は深いが、凡人の理解はその教えの高さには程遠い」(道綽の安楽集)といい、「(法華経の悟りを)いまだ一人も得た者はない」(同書)、「浄土教以外の雑行(ぞうぎよう)を修行する者は、千人の中に一人も得道する者がない」(善導の往生礼讃偈)などと誤って誘われて、一生・二生どころか無量生も生まれ変わっている間、ガンジス河の砂粒ほどに無数の間、何度もだまされて権経に堕ちてしまったのであった。いや、権経どころか、もっと後戻りして小乗経に堕ちてしまい、さらに仏教に及ばないインドの宗教の思想や中国の儒道の思想にとらわれて、遂には悪道に堕ちてしまったと深く知るに至ったのである。
日本国でこれらのことを知っているのは、ただ日蓮一人だけである。〓このことをたとえ一言(ひとこと)でも言い出せば、父母や兄弟や師匠に国主からの王難がかならずふりかかることとなろう。かと言って、知っていながらそのことを口にしなければ仏陀(みほとけ)や菩薩が衆生をあわれむ心に背くことになってしまうのではないか〓とあれこれ考えた結果、法華経や涅槃経などの教えに照らして言うべきか、言わざるべきか、二つの道を考え合わせると、〓知っていて言い出さなければ、今の人生では何事も起こらないにしても、後の世に生まれ変わったとき、かならずや八大地獄のうちもっともきびしい無間地獄に堕ちてしまうことになろう。そしてまた、もし言い出したならば、正道を妨げる煩悩障・業障・報障という三障や、衆生を悪道にひき入れる煩悩魔・五陰魔・死魔・自在天魔という四魔がかならずつぎつぎと起こってくるであろう〓と知った。もしそうであるならば、〓二つの道のうち、苦難を恐れずに(日蓮が知った真実を)言い出す道に身を任せよう〓という考えと〓しかし国王からの迫害が現実となったときに当初の信念を失ってしまうのであるならば、始めから思いとどまるべきであろうか〓と何度も思いめぐらすうちに、〓なるほど、法華経の見宝塔品第十一に、足の指で大千世界を動かして他国に投げとばすなどのとても困難なことを九例挙げ、それらはまだ易しいことであって、法華経の教えを末法の時代に信じ行なうことはそれとは比較にならないほど困難なことであると六回もくり返して釈尊が語り示したのは、今、日蓮が二つの道のうちどちらを選ぶべきかに悩んでいるようなことを指すものである〓と、はじめて納得したのである。「私たちのような力のない者がたとえもし須弥山を投げとばすようなことがあったとしても、私たちのように神通力を持っていない者が乾草を背負ってこの世界を最後に燃やし尽くす劫火のなかに入って焼けないことがあったとしても、私たちのような無智の者がガンジス河の砂粒ほどの無数の経典などを読誦したり暗誦したりしたとしても、法華経のたとえ一句であれ一偈であれ、末法の時代に信奉することは困難である」と説かれていることはこのことを語っているものであることを痛切に体験した。だからこそ、〓今度こそはつよい真の仏道を求める心を起こして決して信念をゆるがすまい〓と誓いを立てたのである。
〔第七章〕 法華経の予言の色読
(日蓮は)これまで二十数年間にわたってこの法華経の教えを弘めてきたが、その間、日をかさね、月をかさね、そして年をかさねるごとに法難がつづいて襲ってきた。ちょっとした法難は数えあげたらきりがない。危険が大きかった法難は四度に及んだ。(鎌倉松葉谷の草庵焼き打ちと故郷安房の松原大路での襲撃との)二度の法難はしばらく措くとして、鎌倉幕府の権力を直接行使した法難(伊豆への流罪、そして相模竜口(たつのくち)でひそかに断罪されようとした竜口法難)は二度にわたっている。このたび、竜口(りゆうこう)法難での断罪ができずに佐渡島に流罪されたことは現に日蓮自身の身命を断とうとする企てであった。そのうえ、日蓮の弟子に対しても信徒に対しても、さらにただ日蓮の教えを聞きに来た一般の人に対しても重罪の処置をしている。さながら幕府に対して謀反を起こした者に対する処罰のようなきびしい態度で接しているのである。
法華経の第四巻、法師品(ほつしほん)第十には「しかもこの法華経を説けば、釈尊が世にましました時代ですら、なお、うらみやねたみが多かったのである。まして釈尊入滅の後にはうらみ、ねたみをかけられるのは当然なのである」という。同第二巻、譬喩品(ひゆほん)第三には「この法華経を読誦し書写して持つ者を見て、軽しめ、いやしみ、にくみ、ねたみ、恨みをいだくことであろう」などとある。同第五巻、安楽行品(あんらくぎようほん)第十四には、「すべてこの世の中はうらみが多く、(真実の教えを)信じにくい」。また、勧持品第十三には、「さまざまな無智の人が悪口を言ったり、ののしったりすることであろう」などと、俗衆増上慢(ぞくしゆぞうじようまん)の姿を述べ、また「国王や大臣やバラモンや居士や、さらに仏教の他の比丘たちに対して、法華経を説く行者(ぎようじや)が邪(よこし)まな見解に立っていると非難し誹謗を加え、自分たちの誤った教えを主張することであろう」、また「(法華経を説く人が)しばしばその国から追放されるであろう」などと説かれている。また、常不軽菩薩品(じようふきようぼさつほん)第二十には、「杖や木や瓦や石などで法華経の行者を打ちなぐることであろう」。涅槃経の〓陳如品(きようじんによほん)には、「そのときに、大勢の外教(げきよう)(外道)が連合してマガダ国の阿闍世王のところに行き、〓今、唯一人の大悪人がおります。それはほかでもないゴータマ・ブッダ(釈尊)であります。すべて世の中の悪人は、自分に都合のよい利益を得るためにゴータマの所に集まり、その近侍となってさっぱり善いことを行なわず、呪術の力で迦葉や舎利弗や目連らバラモンの修行者たちをとりこにしております〓」などと説かれている。
天台大師智〓は法華文句巻八上に(前掲の法師品の「況滅度後」の経文を解釈して)「(この法華経に対して、釈尊が在世の時ですら怨嫉を抱く(敵対する)者があった)まして釈尊入滅後の未来に敵対者が出現するのは当然であろう。というのは、人々が法華経の真実に目覚めることがむずかしいためである」などと説いている。妙楽大師湛然は法華文句の注釈書の法華文句記巻八の三に「怨嫉」という経文の言葉について「障害をまだ取り除いていないことを『怨』といい、聞くのを喜ばないことを『嫉』と名づける」と解釈している。中国の南北朝時代に、揚子江以南、黄河以北のそれぞれ高名な三人の学僧、七人の学僧をはじめ、中国の多くの学者たちは天台大師智〓を怨敵とした。法相宗の学僧、得一(徳一)が天台大師智〓に対して論難した言葉が、伝教大師最澄の守護国界章のなかに引用されている。「つたないかな、智公(天台大師智〓)よ、君はいったい誰の弟子なのかね。わずか十センチほどにも及ばない舌の根で、釈尊がその舌で自身の顔を覆ってその真実を表わした解深密教の教えを誹謗するのかね」などと。
東春沙門智度の天台法華疏義〓(ほつけしよぎさん)には、「問う。釈尊がましましたとき、、多くの怨嫉を受けられた。釈尊が入滅して後、この法華経を宣布するときに、どうしてまた受難が多くあるのか。答えて言う。俗に〓良薬は口に苦し〓というではないか。この法華経は、人にはそれぞれ器量があり、人乗、天乗、声聞乗、縁覚乗、菩薩乗の機類のうちどのさとりに到達できるかは最初から決定しているといった偏った考え方を否定して、誰もが一乗のさとりに到達することができるのだといい、その道に向かわしめるために凡夫が真理追求に真剣でないことを非難して、聖者が小乗に停滞するのを叱り、大乗をしりぞけ、小乗を破り、天魔を毒虫と名付け、外道(外教)を悪鬼と言い、小乗に執着するのは貧しく賤しいことだと戒め、菩薩に対しては、やっと新しい道を訪ねあてただけではないかと己れの拙なさを自覚させるのである。だから、天魔はその法華経の所説を聞くことをきらい、外道は聞くことをいやがり、声聞乗・縁覚乗の修行者は驚き怪しみ、菩薩はおびえてしまうほどである。これらの人々は、すべて法華経を説く者を迫害する。(法華経法師品の)『怨嫉が多い』という経文は決して空文ではないのである」などと説いている。
伝教大師最澄は顕戒論にいう。「(南都奈良の六宗の僧綱(そうごう)の位にある僧たちは、最澄が嵯峨天皇に奏した『四条式』に対して反論する中で)『中央アジアの西夏という国には鬼弁婆羅門がおり、東方の国には巧みに言葉をあやつる禿頭の沙門があった。彼らは悪魔の類を呼び集めて、世間をたぶらかしている』などと述べて最澄を批難している。それに対して最澄は反論していう。『昔、斉の時代、四分律の祖である慧光が国統となり、光統律師と呼ばれたが、達磨大師との論争にたえかねて、菩提流支らとともに彼を毒殺しようとしたという。今またわが日本国の南都奈良の六宗の僧綱が最澄との論争に破れて、かえって最澄を迫害しようとしている。法華経法師品に〓(釈尊ご自身もご在世に迫害を受けられたが)まして釈尊が入滅された後に法華経を弘めようとする行者が数々の怨嫉を受けるのは当然である〓(という経典の言葉はまさに真実の言葉である)』」と。伝教大師最澄はさらに法華秀句に、「時代を語ればすなわち像法(仏教が像(かたち)としてだけ伝えられる時代)の終わり、末法(仏法が滅尽しようとする時代)の初め。場所を問いただせばすなわち唐の国の東、羯の国(中国の東北部に分布していた古族)の西。そこに住む人はすなわち五濁(ごじよく)が充ち満ちている悪い世の中に生を享け、お互いに闘争をかさねている時代である。法華経法師品の〓(如来の現在すら)なお、怨嫉多し、いわんや滅度の後をや〓という経文には深い意味がある」と語っている。
そもそも、子どもにお灸を据えれば、子どもはきっとお灸を据える母を憎む。重い病気の者のために良い薬を与えれば、かならずや苦くて飲めないと嘆く。(仏教についても同じで)釈尊がこの世にお出ましになり法華経を説かれた時ですら怨嫉が多かったのであるから、まして仏教が像(かたち)だけ伝えられ、また滅尽しようとする時代、さらに中枢の国ではなく辺境の国においては、仏の教えを素直に受け入れることはなかなかむずかしい。あたかもそれは、山々が連なっているようなもの、波の後に波が押し寄せてくるようなもので、法難は次々とかさなり、悪いことがかさなるばかりであろう。像法の中頃には天台大師智〓一人だけが、法華経をそこに集約されるすべての仏教経典と合わせて仏陀のみこころの通りに読んだのである。揚子江以南の三人の学僧、そして黄河以北の七人の学僧の末流らが天台大師に怨嫉を加えたけれども、陳(ちん)の文帝、隋(ずい)の武帝と煬帝(ようだい)らの賢明な帝王たちが、自分の識見によって良いこと悪いことを判定したので、天台大師に敵対する人はついにいなくなった。像法の末の時代には伝教大師最澄一人だけが、法華経とそこに集約されるすべての仏教経典と合わせて仏陀のお示しのとおりに読んだのである。それに対して、南都奈良の七大寺がいっせいに立ち上ってこれを否定しようとしたけれども、桓武天皇や嵯峨天皇などの賢王が自身の見識によって正邪を判定したので、格別のことは起きなかった。
今、末法の始めから二百余年(釈尊入滅後二千二百余年)を経過した時点に立っている。法華経法師品の「いわんや滅度の後をや」の予言のとおりに闘争が起こって来なければならない時代となったのであるから、道理にはずれたことが行なわれ、五濁の充満する悪世である証拠に、公的に国王の前で意見を開陳する機会も与えられることなくして、一方的に流罪され、のみならず一身を失う危機にもさらされたのである。さよう、日蓮の法華経の智解は中国の天台大師や日本の伝教大師に比較すれば千万分の一にも及ぶことがないけれども、しかしながら、法難を耐え忍び、一切衆生を救わんとする慈悲においては何ものにも劣るはずがないことは日蓮自身が恐れおののくほどである。(これは日蓮自身の力によるものではなく)かならず諸天のおはからいにもあずかり守護を受けることであろうと思うけれども、まだいささかのきざし(前兆)もない。それどころか、ますます重い罪に処せられるのみである。逆にこのような意味を顧みると、日蓮の身が法華経の行者でないのであろうか。または、諸天善神らがこの国を見捨てて去ってしまって、そのために法華経の行者に対する加護がないのであろうか。あれやこれや疑問に思われることである。
それにもかかわらず、法華経第五巻、勧持品第十三の二十行の偈頌(げじゆ)は、もし日蓮がこの国に生まれなければ、ほとんど釈尊は大変なそらごとを語ったこととなってしまい、勧持品で釈尊入滅後に法華経を伝道することを誓った八十万億那由佗という大勢の菩薩たちも、あの提婆達多(だいばだつた)のように、人を欺く罪に陥ってしまったことであろう。勧持品二十行の偈には、菩薩たちが「(ただ願わくは慮(うらおも)いしたもうべからず。仏の滅度の後、恐怖悪世(くふあくせ)の中において我ら皆まさに広く説くべし)諸(もろもろ)の無智の人、悪口罵詈等し、及び刀杖を加うる者あらん。(我ら皆まさに忍ぶべし)」と悪世の弘教(ぐきよう)を誓っているのである。
今の世を見ると、日蓮以外の僧たちの中に、いったい誰が法華経のために諸人に悪口を言われたり、罵(ののし)られたり、刀杖などを加えられている者があろうか。日蓮がいなければ、勧持品のこの一偈による釈尊入滅後への予言はそらごととなってしまう。また、この偈(げ)につづく「悪世の中の比丘(僧)は邪智にして心諂曲に(いまだ得ざるをこれ得たりと謂(おも)い我慢の心充満せん)」「(利養に貪著(とんじやく)するが故に)白衣(びやくえ)のために法を説いて世に恭敬せらるること六通(仏・菩薩が禅定・智慧の力によって得る六種の無礙自在なはたらき)の羅漢のごとくならん」などという経文は、今の世の念仏者や禅宗などの法師が法華経を弘める日蓮を妨害することがなければ、釈尊はまた大変な妄語の人となってしまうことになる。そしてまた、「(この諸の比丘らは)常に大衆の中に在って我らを毀(そし)らんと欲するが故に、国王・大臣・婆羅門・居士および余の比丘衆に向かって(誹謗して我が悪を説いて、これが邪見の人、外道の論議を説くといわん)」という経文は、今の世の僧たちが日蓮のことを幕府に讒言して流罪にすることがなければ真実でなくなる。さらにまた、「数々擯出せられ(塔寺を遠離せん)」という経文は、日蓮が法華経を弘めるために、たびたび流罪にされることがなければ、「しばしば(数々)」という文字をどのように理解したらよいか分からなくなる。この「数々」という二字については、中国の天台大師も、日本の伝教大師も、まだ体験をしておられない。ましてそれ以外の人が体験していないことはいうまでもない。末法という悪世の始めに生まれたあかしとして、勧持品二十行の偈のはじめの「恐怖悪世の中において」という仏陀の語(ことば)が末法の今の現実と一致したから、ただ日蓮一人だけがこの経文を体現したのである。例えば、釈尊が付法蔵経(付法蔵因縁伝)に予言して「私の入滅後百年の後に阿育大王(アショーカ王)という国王が出現するであろう」といい、摩訶摩耶経には「私の入滅後六百年に竜樹菩薩という人が南インドに出現するであろう」といい、大悲経には、「私の入滅後六十年に末田地という人が大地を竜宮に築くであろう」と言われる。これは皆、釈尊の未来への予言のとおりに実現しているのである。もし、釈尊の予言の通りにならなかったならば、いったい誰が仏教を信じることがあるだろうか。ところで仏陀釈尊は、正法華経(しようほけきよう)と妙法蓮華経とに、(この法華経が弘められる時を)「恐怖悪世において」「しかるに後の未来世において」「末世の法滅せんとする時」「後の五百歳において」などと定められているのである。
今の世に法華経勧持品第十三に予言する俗衆(ぞくしゆ)増上慢(在俗の信徒で思いあがっている者)、道門増上慢(出家の身で思いあがっている者)、僭聖(せんしよう)増上慢(生き仏(ぼとけ)のようにあがめられながら、思いあがっている者)という三類の強敵(ごうてき)が具体的に出現しなければ、いったい誰が仏陀の教えを信じることだろうか。もし日蓮が現われなければ、いったい誰を法華経の行者として仏陀の予言が証明されるであろうか。中国の天台大師の仏教理解に敵対した南三北七の末流、日本の伝教大師に対立した南都奈良の七大寺らは、やはり像法の時代の法華経に敵対する者とされるから、まして今の世の禅宗・律宗の僧や念仏信奉者らは法華経の敵対者としてみなされることから脱(のが)れることができようか。法華経の経文(勧持品二十行の偈)に日蓮の行動は勘合符のようにぴったり一致する。幕府からとがめを受けることは、ますます喜びとするところである。例えば、まだ煩悩を断ずることができない小乗の菩薩が、「願って業(ごう)を兼ねる」といって、つくりたくない罪を犯して、願って地獄に堕ち、父母たちの受けていたつらい苦しみを受ける様子を知って、形通り罪を犯して願って地獄に堕ちて同じように苦しみを受け、父母たちの苦を代わって受けることを悦びとするのであるが、まるでそのようなものである。日蓮も今また同様のことを願っている。今の世で三類の強敵による法難には堪えられるかどうか疑問であるけれども、将来、悪道から脱れることができると思えば、今苦しい法難を悦びをもって受けとるのである。
〔第八章〕 諸天はなぜ法華経の行者を守護しないのか
ただ、世間の人々が疑問をもつことであろうし、自分自身でも疑問を持つことであるが、どうして諸天は日蓮に助けをもたらさないのであろうか。諸天などの守護神は仏陀釈尊の前で誓いを立てている。(そのようなことからすれば)法華経の行者には、そのように疑問をもつことになろうとも、法華経の行者と呼んで、早々と仏陀の前で誓った言葉を実現しようとこそ思うべきであるのに、その正しい筋道が実現しないのは、日蓮が法華経の行者でないためなのか。この疑問は本書、開目抄のきわめて重要な論点であり、日蓮の生命に代えて大切なことであるから、くりかえしこのことを書くだけでなく、疑問を強く立てて答えを組み立てて行こう。
季札という人がいた。(季札が使者となって徐の国を通ったとき、徐の国の君主が季札が奉持していた剣を気に入っていたのを知り、口には出さなかったが使者の役割を果たしてから後に徐の国の君主に贈ろうと決心した。ところが帰国の途中、徐の国を通るとすでに君主は死んだ後であった。しかし、季札は)心で約束したとおりに実行しようと、王の重宝である剣を徐国の君主の墓の上に懸けたのであった。また、王寿という人は河の水を飲んで、そのお礼として金貨を水中に投げ入れたというし、公胤(「史記」では弘演)という人は(使者として外国に出ている間に主君の衛の懿公(いこう)が北狄に攻められて殺され、肝だけが捨てられていた。帰国した公胤は)自分の腹を割いて、主君懿公の捨て置かれた肝をその中に収めた。これらは賢人であり、主君の恩に報いた例である。
まして舎利弗や迦葉ら大いなる聖人は、比丘(出家僧)が守るべき二百五十戒、さらにいえば大比丘三千威儀という作法を完全に身につけ、見惑(けんわく)(道理上の迷い)と思惑(しわく)(感情的な迷い)を断ち切って、欲界・色界・無色界という六道輪廻の迷いの世界を超越した聖人である。梵天や帝釈天など諸天を仏教に導く師であり、すべての人々の精神的よるべである。しかるに釈尊が教えを説き始められてから四十数年間は、彼らは永久に真の仏道を達成することはできない人たちであると嫌われ捨て果てられていたのであるが、法華経という、いわば不死の良薬となる教えをなめたところ、〓(こ)げてしまった種なのにそこから芽が出たように、一度割ってしまった石が不思議にもとどおりになったように、枯れ木に花が咲き果実が実ったように、仏道を達成することができると保証されたにもかかわらず、いまだに仏陀のように八相成道を遂げてはいないけれども、どうしてもこの法華経の重い恩に対して恩返しをしなければならないはずである。もし報恩がなければ、前述した中国の賢人たちにも劣り、恩知らずの者、人の心を持たない動物と同様になってしまう。(昔、晋の毛宝将軍は白い亀をあわれんで、助けて江に放ってやった。のち、毛宝が〓城(ちゆじよう)で戦に敗れて江に沈んだとき)毛宝が昔助けた白亀はその恩を忘れることなく、(白亀の背に毛宝が載せられて岸に運ばれ、命を助けられたという。また、漢の武帝が昆明池という大きな池で鉤をふくんだ大魚をあわれんで、これを取り去って放ったところ)その昆明池の大魚は命を救ってもらった恩返しをしたいと思って、ある夜中に明月珠という宝玉を捧げたという。動物ですらこのように恩返しをするものだ。まして、大いなる聖人が報恩を行なうのは当然のことであろう。阿難尊者は斛飯王の次男であり、羅〓羅尊者は(斛飯王の長兄である)浄飯王からすれば孫になる。高い家柄の出身として人々に尊ばれ、その上、小乗の阿羅漢の証果(さとり)を得たにもかかわらず、釈尊の弟子となって〈さとり〉を得ようとしたのに、容易に仏道を完成することは困難であるとされていたのだが、法華経が八年間にわたって説かれた霊鷲山の席上で、(授学無学人記品第九に至って)阿難は将来、山海慧自在通王如来(せんかいえじざいつうおうによらい)という仏と成るであろうと記〓(保証)を授けられ、また羅〓羅は将来、蹈七宝華如来という仏と成るであろうなどと授記された。
もし法華経が説かれなければ、どんなに名家の出身のりっぱな大聖人であろうと、誰か敬う者があるであろうか。夏国(かのくに)の桀王・殷国の紂王は天子の位につき、その国の人民に信頼されなければならなかった。ところが、桀王・紂王はともに国の治め方が悪く世をほろぼしてしまったので、今でも悪い手本として「桀紂のようだ、桀紂のようだ」と言われるようになってしまい、身分の卑しい者や癩病の者も、「桀紂のようだ」と言われれば、悪口を言われたといって腹を立てるのである。(五百弟子品の)千二百人の声聞をはじめ、無量の声聞は、法華経が説かれなかったならば誰もその名を知る者とて、その声を習う者とてないし、それらの声聞が、のちにすべての経典を集成し、編集したとしても、それを見向く人とてないであろう。ましてこれらの人々を絵像に描いたり、木像に彫ったりして本尊と仰ぐであろうか。ただただ法華経の御力があってこそ、すべての羅漢(声聞)は人々から尊ばれ帰依される存在なのである。すべての声聞は、法華経の教えから離反してしまえば、魚が水から飛び出し、猿が木を失い、乳児が乳を失い、民衆が国王から離れてしまったと同然である。(こう考えてくると、声聞たちは法華経の恩を報じないわけにはいかない)どうして法華経の行者を見捨てることができようか。
もろもろの声聞は、法華経以前の経典では凡夫のもつ肉眼の上に、色界(しきかい)の天人のもつ天眼と、声聞・縁覚が真空無相の理を照らし見る慧眼を得たが、法華経に至って始めて菩薩が衆生を救うためにすべての法門を照らし見る法眼と、仏陀の身中に前の四眼をもつ仏眼を備えることができ、十方の世界の隅々まで照らし見ることができるようになったのであるから、娑婆世界の中で法華経の行者が活躍していることを知見しないはずがあるであろうか。たとえ日蓮が悪人であったとして、一言・二言、あるいは一年・二年、あるいはきわめて長い時間を一劫と数えて、一劫・二劫、百千万億劫の間、これらの声聞に対して悪口を言ったり罵ったり、さらに刀や杖で振りかかろうとするような様子が見えたとしても、すべての声聞は法華経をさえ信じている行者であるならば見捨てるはずがない。たとえば、幼児(おさなご)が父母に悪口を言ったとしても、父母がこの幼児を見捨てるであろうか。ふくろうの子は成長すると母を食べてしまうというが、それでも母はわが子を捨てないという。また、破鏡という虎の類の獣は父を殺害してしまうのだが、父はこれに抵抗しないのである。人の心を持たない動物ですらこのようなありさまであるという。まして、仏教を修行した大いなる聖人たちが法華経の行者を見捨てるはずがあるであろうか。
はたして、(法華経の信解品第四で)四人の偉大なる声聞が釈尊の説法をこのように理解しましたと、次のように述べたのである。「わたくしたちは今、本当の意味の声聞となりました。すなわち、仏道の声を一切衆生に聞かしめます。わたしたちは今、真の意味で修行者の到達することのできる最高位を得ました。ですから、もろもろの世間、天や人間や魔王や梵天の普きその中で供養を受けます。世尊には大恩があります。めったに示されない教化をなさって、私たちをあわれみ教化し、仏陀の位を完成する利益をあたえてくださいました。そのお導きのご恩は、無量億劫の間かかっても十分に報いることができるでありましょうか。たとえ手足をもって給仕をし、頭(こうべ)を地に着けて礼拝し、すべてを捧げて供養したとしても、誰もそのご恩に報いることはできますまい。あるいは足(みあし)を手の上に捧げ、両肩にになって、心を尽くして敬いを表わし、さらにまた、ご馳走を盛ったお膳や数限りない立派な衣やさまざまな寝具や種々の薬を捧げ、牛頭栴檀という最高の香木(こうぼく)やもろもろの珍しい宝で仏塔を起て、立派な衣を地面に敷くなどして、一劫をガンジス河の砂粒に倍するほど長い間にわたって供養を捧げたとしても、決してまた仏陀の大恩に報いることは困難なのです」などと。
もろもろの声聞たちは法華経が説かれる以前、すなわち(1)華厳経・(2)阿含経・(3)方等部(大乗)諸経典・(4)般若経などの経典では、たびたびお叱りを受け、人間界と天上界の方々の集(つど)うた説法の場ではどれほど辛い思いに堪えたことだろうか。だからこそ、迦葉尊者が(維摩経の不思議解脱の教えを聞いても充分に理解できず、菩提心を起こすことができないと歎いて)号泣する声は三千世界に聞こえたということであるし、須菩提尊者は(維摩居士のところに托鉢(たくはつ)に行ったところ、維摩は須菩提の鉢に飯を盛り、飯はこれ諸法であるとして、大乗の教える空の理を説いて邪見をいましめたばかりか、汝に施す者は三悪道に堕ちるときめつけられ、そのために)茫然としてしまって言葉もなく鉢を置いて去ったのであった。また舎利弗は(仏陀から不浄の食(じき)を摂ったといわれたと伝え聞いて、ただちに)食べたものを吐いた(そして今後とも人の請を受けないことを誓ったという)。また富楼那は(維摩居士から「禅定に入って人の心を観察して説法せよ」)「高貴な宝器に汚れたものを置いたようなものだ」と誡められたという。釈尊ははじめに鹿野苑において阿含経をお説きになり、二百五十戒を守って修行するようになどと、ねんごろにお説きになったのに、今また、いつの間に(打って変わって)御自分のお説きになったことを、このように非難なさることになってしまったのか。それでは、前後で言うことが変わってしまうと非難される過失になってしまう。
一例を挙げれば、釈尊が提婆達多に向かって、「お前は愚かな人間である。見よ、人の唾を食ったではないか」と罵(ののし)ったところ、提婆達多は毒矢が胸に射(う)ち込められたような屈辱を感じてうらんで言った。「ゴータマは仏陀ではない。私は斛飯王の長男であり、阿難尊者の兄であるのだから、ゴータマとは一族の親しい間柄である。たとえどんなに不都合なことがあったとしても、内々で教えさとせばよいことではないか。これほど多くの人間界・天上界の方々が集まった場で、これほどのひどく不吉な言葉をきびしく投げかける者が大いなる人、仏陀といわれるなかに数えられるであろうか。思えば若いときにはゴータマに妻となるべき女性を奪い取られ、今また満座の中で恥をかかされた。今日からは生まれ変わる度毎に恨みをもちつづけて大怨敵となろう」と誓ったのであった。
こうしたことに照らし合わせると、今、大声聞となっている方々は、もともとバラモン教の祭典・儀礼をつかさどる、インド四姓の最高の階級の出身である。また、さまざまな外道(インドの諸宗教)の中でも高い位に在った者であったから、諸王のみでなく、多くの帰依者たちから貴ばれた。あるいは生まれた家柄が高貴の人もあり、あるいはたいへん富裕である方々もいた。ところが、それぞれの世間的な立身出世を放抛し、自分のみ尊しとする慢心を捨て、それまでの衣服を脱ぎ捨てて、ぼろ衣(きれ)を世間で正式に用いる色とは違った色に染めなおした糞掃衣(ふんぞうえ)を身につけ、高い身分の者が持つ白毛の払子(ほつす)や弓矢をうち捨てて、托鉢に用いるただ一つの鉢(容器)だけを手にするだけで、貧しく物乞いのような姿で釈尊に随侍したのであった。風雨を防ぐ家とてもなく、生命をささえる衣食とてわずかという苦難に堪えて来た。中インド・東・西・南・北インド(インド全体)というだけでなく、インドを囲む四つの海に住む人々は皆、バラモン教の弟子や、信徒であったから、仏陀釈尊ですら九回にわたって不条理な災難をお受けになった。すなわち、提婆達多が崖から落とした石によって釈尊の足が傷つけられ、阿闍世王が酒を飲ませて追いやった象によって、釈尊や弟子たちが危害を加えられようとし、釈尊と弟子たちが托鉢に行ったところ阿耆多王は馬に食べせさる麦を供養するとして食べさせ、釈尊が婆羅門城に行ったとき老女から欠けた素焼きの陶器に臭い米をといだ淀み汁の供養を受け、旃遮婆羅門女が木の鉢をお腹に入れて釈尊の子種を宿したと吹聴したこと、などなどである。釈尊ですらこのような災害を受けたのであるから、弟子たちがそれ以上にさまざまな迫害を受けたありさまは容易に想像できよう。好古梵志(こうこぼんじ)にそそのかされてカピラ城を攻撃したコーサラ国の毘瑠璃王によって、釈迦族の人々は皆殺しにされ、足を地中に埋めた上を暴れ象を放して踏み殺させ、提婆達多が山の上から石を落として釈尊を殺そうとしたとき、それを非難した華色比丘尼は提婆達多になぐり殺され、姦通したことを知られたと思ったバラモンの女性とその相手の賊によって、迦盧提尊者は殺害されて馬糞の下に埋められ、目連尊者は竹杖外道に殺害されたなどなど、数え切れないほどである。
そのうえ、六師外道は心をあわせて阿闍世王や婆斯匿王に次のように讒言した。「ゴータマは世界で第一番の大悪人であり、ゴータマが行くところには三災七難がつぎつぎ起こって来る。あたかも大海にもろもろの河川が流れ入り、大きな山に大小さまざまな樹木が成長するように。そのようにゴータマのもとにはもろもろの悪人が集まっており、ゴータマの弟子の迦葉・舎利弗・目連・須菩提たちがその代表なのである。そもそも人間に生まれた以上、忠・孝という倫理をまず行なうことが第一である。ところが彼らはゴータマにだまされて、父母の教訓を聞くことなく、家を出、国王の定めた勅宣にも背いて山林に入ってしまったのである。このような行ないをしているのだから、国内に止(とど)めおくべき者ではない。ゴータマとその弟子がいるために、天の太陽や月や星などに悪い前兆が見え、地にも多くの災(わざわい)が相い次いで起きているのだ」。そのような非難に果たして声聞たちが堪えきれるものであろうかと思わせ、また事実、伴って来る災いのために釈尊に固く従うことも困難なことであった。人間界・天上界がうち〓って聞く釈尊の説法の際に、声聞たちがしばしば叱責される声を聞けば、とても釈尊に従順であることは困難である。そのありさまを見て、どのようにしたらよいのか迷ってしまい、ただただうろたえるばかりなのであった。
その上、最大の非難は、維摩経で「汝に供養を施す者は福を得るところとは呼ばない。汝に供養を捧げる者は逆に地獄界・餓鬼界・畜生界に堕ちて行くのだ」という経文である。すなわち、菴摩羅女が釈尊に奉った中インドの菴摩羅樹園(あんまらじゆおん)で、梵天、帝釈天、日天、月天、欲・色・無色の三界の諸天、地神、竜神など多くの方々が集まった説法の場で、維摩居士が「須菩提らの比丘(僧)たちに供養を捧げる天上界・人間界の者は地獄界・餓鬼界・畜生界に堕ちるであろう」と言ったのである。こうした非難を聞いた天上界や人間界の人たちは、果たしてこれらの声聞に供養を捧げるだろうか。結局、釈尊のお言葉を用いて多くの声聞・縁覚などの仏道修行者を殺害なさろうとされたのかとすら思われるし、心ある人々は釈尊から遠ざかってしまったことであろう。そういうことだから、これら声聞・縁覚の人々は、釈尊に対しての供養のついでに、僅かばかりの供養を分かち与えられて、その身命を永らえたのであろうか。
しかれば、具体的な現われの背後にある心を推察すると、釈尊御一代の五十年の説法の中で四十数年間の諸経典だけが説かれて、法華経の八年間の説法がないままに御入滅遊ばされたならば、誰がいったいこれらの尊者を供養するであろうか。(そうなったならば)これら声聞たちは生きながらにひもじい餓鬼道の苦しみのなかにあったことであろう。
ところが、法華経以前の四十数年間に説かれた諸経典を、あたかも春の陽光がそれまで張っていた氷をすっかり融かしてしまうように、また草の葉にたまったたくさんの露を大風が吹き落としてしまうかのように、「これまでの四十数年間には、まだ真実の教えを明らかにしていなかった」(無量義経説法品)という一言で、あっという間に否定してしまった。それはあたかも、大風が吹いて黒雲を巻き散らしてしまったようであり、天空に満月が輝いているかのようであり、晴れわたった空を太陽が燦燦と照らし出しているかのようであった。そのように「釈尊は長い間教えを説いた後に、かならずまさに真実を説くのである」(法華経方便品)という教えの光を照らした。さらに諸経では成仏を許されなかった舎利弗尊者は華光(けこう)如来、迦葉尊者は光明(こうみよう)如来、その他の声聞たちはそれぞれの名で、次々と将来の成仏を保証されるに至った。そのように法華経の経文に赫々(あかあか)と輝く太陽や明るく照らす月のように、あるいは天子の鳳詔文(紹勅)のように、そして明るい鏡のように写し出されたので、釈尊が入滅して後の人間界・天上界のすべての仏教信奉者たちに彼ら尊者たちは仏陀のように崇(あが)められるようになったのである。
水面が澄めば月影が惜しみなく映し出される。風が吹けば草木がなびかないことがあろうか。法華経の行者がいるならば、これら舎利弗・迦葉らの聖者は、大火の中をくぐり抜けてでも、大石の中を通り抜けてでも、必ず法華経の行者のもとに現われて守護するはずである。迦葉尊者が鶏足山(けいそくせん)で坐禅し、禅定(ぜんじよう)の境地に深く入ったのは、将来、弥勒仏が出現するときに仏教の弘通(ぐづう)につとめるためと期待されているが、それはともかく、なぜ舎利弗・迦葉らはここに今出現しないのであろうか。言いようもないほど不審なことである。今の時代ははたして後の五百歳、すなわち末法の初めではないのであろうか。「広く宣(の)べられて流布される」という経文はむなしい言葉となるのであろうか。あるいは日蓮が法華経の行者ではないためなのだろうか。法華経は教えを伝える言葉にとどまるのであって、禅こそが言教(ごんきよう)以外に特別に仏陀からの悟りを伝える教え(教外別伝)であると主張する大妄語を語る者をお守りになるのか。(念仏宗では)浄土教以外の聖道門の教えを「捨てよ、閉じよ、閣(お)け、抛(なげう)て」と断定し、法華経を学ぶ門を閉じなさい、法華経の経巻(巻物にした経典)を投げ捨てなさいと(選択本願念仏集の木版に)彫りつけているが、法華経信奉者の依りどころである法華堂を崩壊させる人たちをお守りになるのか。諸天たちは、釈尊に誓いを立てたものの、五濁悪世の大難があまりに激しいのを見て、法華経の行者守護のために出現しないのであろうか。日天も月天もともに厳然として天にいらっしゃる。須弥山は今も崩れずにそびえ立っている。海潮も昔どおりに干潮・満潮をくり返している。春夏秋冬も正確にやって来る。それなのに、法華経の行者守護が実現しないのは、いったい何故なのだろうかと、大いなる疑いがいよいよつもるばかりなのである。
〔第九章〕 迹門の一念三千
ところで、確かにもろもろの大菩薩や天人たちは、すでに法華経以前のそれぞれの経典で将来に成仏を遂げる保証を得ているように見られているけれども、それは水中の月影を取ろうとするようなもの、影を本体と見誤るようなもので、姿形だけが似ているだけで真実の意味はともなっていない。だからまた、釈尊の御恩の深さが分かっているようで、実はそれを体得する境地には到達していないのである。
釈尊が初めて成道なさったとき、まだその教えを語ろうとされなかった。そのとき法慧菩薩・功徳林菩薩・金剛幢菩薩・金剛蔵菩薩などの六十人をも超える大菩薩たちが、十方の国で教化なさっている諸仏の国土から教主釈尊の御前に訪れて、賢首菩薩や解脱月らの菩薩の願いに応じて十住・十行・十回向・十地などの教えを説いたのである。これらの大菩薩たちが説いた教えは、釈尊から習い伝えたものではない。また、十方の世界からもろもろの梵天王たちも来て教えを説いたのであるが、これまた釈尊から習い伝えたものではない。すべて華厳経の説法の場所に参集した大菩薩や天や竜たちは、釈尊が説法する前からすでに〈不思議解脱〉という境地に安住している菩薩たちなのである。これらの大菩薩たちは釈尊が過去に菩薩の修行をしていたときのお弟子であろうか。はたまた十方の世界の釈迦仏以前に成道された仏陀のお弟子であろうか。ともかく御一代に華厳経から法華経、涅槃経まで五つの時間帯(五時)にわたってインドで仏教を説いた、始成正覚の釈迦の弟子ではないのである。
華厳経のあとに、釈尊が自ら阿含経や方等部の諸経典や般若経を説き、蔵教(ぞうきよう)(小乗)・通教(つうぎよう)(大乗仏教)・別教(べつきよう)(深奥な教え)・円教(えんぎよう)(最も優れた完全な教え)を示されたときに初めて、だんだんと釈尊から教えを習いえたお弟子が出来て来る。しかし、これらもまた釈尊が自ら説いた教えであるには違いないが、間違いなく真髄の教えが説かれたわけではない。なぜかと言えば、方等部の諸経典や般若経で明らかにされた別教・円教は、華厳経に説く別教・円教という二つの教えの趣意を超えることはないからである。しかし華厳経に説く別教・円教の二教も、教主釈尊の説いた別教・円教ではなく、法慧等の大菩薩が説いた別教・円教の段階に止まるのである。こうしてみると、これらの大菩薩たちははた目には釈尊のお弟子のように見えるのだが、むしろ釈尊の師(先生)であると言っていいくらいである。なぜなら、表面的に見るならば、釈尊は彼ら菩薩たちが口々に釈尊の悟りを讃(たた)え、教えを説くのを聞いて、悟りの境地の説き方を確かめてから後に、次々と方等部諸経典や般若経を説いて別教(深奥な教え)と円教(完全に円満な教え)をお説きになっている。こうした見方に立てば、まさにこれらの経典は大菩薩たちが華厳経で明らかにした別教・円教そのものに過ぎないということになる。とすれば、華厳経に登場するこれらの大菩薩たちは釈尊の師(先生)ということになるではないか。華厳経(六十華厳経巻四十五、入法界品)でこれらの菩薩たちを教えあげて善知識(善き友・善き師)と説いたのは、そのような意味を示すものである。善知識というのは、全面的な師(先生)というのでもなく、全くの弟子というのでもないということである。なお、蔵教・通教はまた別教・円教の分流なのであるから、したがって、別教・円教を理解する人はかならず蔵教・通教にも通暁していることになるのである。
人の師(先生)というのは、弟子が知り得ないことを教えてこそ師である。例えば、釈尊が出現する前には、すべての人間と天人、そしてインド宗教の信奉者たちは、(本書の初めに述べたように)摩醯首羅天(まけいしゆらてん)(マーハー・イーシュヴァラ)・毘紐天(びちゆうてん)(ヴィシュヌ)や迦毘羅(かびら)(数論派の祖・カピラ)・〓楼僧〓(うるそうぎや)(勝論派の始祖・ウルーカ)・勒娑婆(ろくしやば)(ジャイナ教の祖・ルシャバ)らの弟子であった。インド宗教(外道)は後にはついに九十五種にまで分派したけれども、結局は今挙げたカピラ、ウルーカ、ルシャバという三人の仙人の思想を超えるものではない。教主釈尊も彼らの哲学を学んだ外道(仏教以前の段階の宗教)の弟子であったが、わが身を痛み苦しめる修行・精神的世界を深める修行を十二年にわたって重ねた末に、「世間の現象は結局、苦であり、しかもそれは本来、空である。つまり、外道が説くような絶対的存在はないし(無常)、絶対神は存在しない(無我)」という真理を悟って、はじめて外道の世界から離れて、誰にも教えられることなく、自分自身で悟った智に安住したことを表明された。それによってまた、人間も天人もすべての者が釈尊を大いなる導きの師と尊敬するようになった。こういうふうに見るならば、華厳経・阿含経・方等部諸経典・般若経が説かれた間には、教主釈尊はまだ華厳経に登場する法慧菩薩らのお弟子であったことになる。こういったことは、(法華経序品に説くように、かの文殊師利菩薩が日月灯明仏の弟子妙光菩薩として法華経を付属され、日月灯明仏の八人の王子を次々に教化し、釈尊はその第八王子の燃灯仏を師としたところから、法華文句に)文殊師利菩薩を釈尊九代の師匠であると解釈するのと同様である。楞伽経でも大慧(だいえ)が仏陀に、「仏陀は菩提樹の下で悟りを開いてから涅槃に入るまで一字も説かれなかった」というが、これも同様な言い方である。
釈尊は御年七十二歳の年にマガダ国の霊鷲山という山で無量義経をお説きになった。そのなかで、菩提樹の下で悟りをお開きになってからこれまでの四十数年間に説き来った諸経典を、それに付随する経典を含めて全てを一括して、「これまで四十数年間に説いた教えは真実を充分明らかにするに至ってはいない」として、否定したのである。その時に、もろもろの大菩薩たちやもろもろの天人たちがうろたえて、釈尊の真実の教えをこそ聞きたいものだと請い願った状景が思いやられよう。無量義経で真実の義を明かす趣旨と思われる言葉は、たった一言(ひとこと)発せられたのだが、まだそれは充分に説き明かされるには至っていない。ちょうど月が山の端(は)から姿を現わそうとしながらも、まだ月そのものは東の山に姿を隠していて、その光は西の山に及んでいる状態のようで、誰もまだ月の姿に接していないようなありさまである。
法華経の方便品で「略して三乗を開いて一乗を顕わす」ことが説かれるときに、釈尊は簡潔に要約して釈尊の御本意である一念三千の法門を述べられた。けれども、まだ初めてのことであったので、ほととぎすの声音(こわね)を眠(ねむ)け眼(まなこ)の人が一声だけ聞いたようなもの、月が山陰から半分姿を現わしているのに、薄雲が月を覆っているように微(かす)かな光をただよわしているようなものであった。舎利弗らはびっくりして諸天や竜神、そして大菩薩たちを集めて、次のように釈尊にお願いした。すなわち、方便品第二には「諸天や竜神たちがガンジス河の砂の数ほど集まり、仏陀を求める菩薩たちは八万もの多数となった。のみならず万億国のそれぞれの転輪聖王がここにやって来て、みな合掌して心から具足の道(完全円満な教え)が釈尊の口から語られるのをお聞きしたいものだ」と請い願った状景を明らかにしている。その意味は、牛乳を精製していく五味にたとえれば、乳(にゆう)・酪(らく)・生酥(しようそ)・熟酥(じゆくそ)の四味に位置づけられ、釈尊の説法の内容を示す四教によれば、蔵教・通教・別教の三教に位置づけられる、それまで四十数年間説かれた諸経典では、いまだ明らかにされていなかった教えをお聞きしたいものだと、舎利弗が請い願ったことを述べているのである。
今掲げた経文の中の「具足の道(完全円満な教え)を聞きたてまつらんと欲す」ということは、次のような意味を示すものであろう。大涅槃経には、「薩というのは具足という意味である」とある。無依無得大乗四論玄義記には、「沙というのは六ということに究まるもの。インドでは六を完全円満な数とする」という。嘉祥(かじよう)大師吉蔵の法華義疏には、「沙とは具足と翻訳する」といい、天台大師智〓の法華玄義の第八巻には、「薩とはサンスクリット語の音写で、中国では妙と翻訳する」と解釈されている。竜樹菩薩は付法蔵因縁伝によると、釈尊から数えて付法相承の第十三番目にあたる大乗仏教の理論家であり、真言宗・華厳宗の元祖であり、一乗要決はその本地を法雲自在王如来として示し、別の名では竜猛菩薩として知られ、菩薩地の初地の悟りを得た。竜樹菩薩の著作大智度論は千巻であったのを、中国の鳩摩羅什(くまらじゆう)がそれを要約して百巻に漢訳したが、重要なこととして「薩というのは六という意味である」と述べている。妙法蓮華経というのは漢文に訳した言葉で、インドのサンスクリット語では、サダルマ(妙法)プンダリーカ(蓮華)スートラ(経)という。善無畏三蔵は法華経の肝心を示す真言として、「曩謨三曼陀(普遍なる仏陀に帰依する)〓(法・報・応の三身を具えた如来)阿々暗悪(方便品の開示悟入)薩縛勃陀枳攘(如来の知)婆乞蒭毘耶(如来の見)〓々曩婆縛(虚空が清らかな如く)羅乞叉〓(煩悩を離れ)薩哩達磨(正法)浮陀哩迦(白蓮華)蘇駄覧(経)惹(入)吽(遍)鑁(作)発(歓喜する)縛曰羅(堅固なる)羅乞叉〓(擁護)吽(遍く)娑婆訶(決定して成就する)」を示し、〔南無、常住にして普遍なる仏陀三身如来、すべての衆生に開かれ示されている仏の智慧を悟ることができれば、大空が清らかなように心の迷いを離れ妙法蓮華経の教えに入り、歓喜してその教えをかたく守ることができるであろう〕ことを明らかにしている。この真言は南天竺の鉄塔の中で竜樹が金剛薩〓から法華経の肝心を示す真言として伝授したもの。この真言の「薩哩達磨」とは正法のこと、薩とは梵語を音写した語で、「正しい」という意味、正とはまた妙(思いはかることができない真理)のことであるから、正法華経、妙法蓮華経などと漢訳された。また妙法蓮華経の上に、南無(帰依)の二字を置けば、南無妙法蓮華経の題目となる。
「妙」というのは具足(完全円満な教えを具備している)ということ。「六」とは六波羅蜜に集約されるあらゆる修行ということ。さまざまな菩薩たちが六波羅蜜をはじめとするあらゆる行を具足しているありさまを聞きたいと願うもの。「具」というのは十界互具(地獄界から仏界までの十法界が、それぞれに他の九界をも具備している)ということ。「足」というのは、十法界のそれぞれの界に十界を具備しているから、その一界に他の九界を具備していること。それが満足という意味である。そもそも、この法華経全体は八巻から成り、序品から普賢菩薩勧発品までの二十八品は、六万九千三百八十四の文字で刻まれるが、その一字一字が皆、「妙」を具備し、三十二相・八十種好がそなわっている仏陀なのである。このように、十法界のそれぞれの法界において仏法界をあらわしている。妙楽大師湛然(たんねん)は摩訶止観輔行伝弘決において、「そのうえにまた成仏という最高の結果を具備しているのであるから、それ以下(九界)の結果を具えているのも当然のことである」と述べている。
仏陀釈尊は、このこと(欲聞具足道)について、法華経の方便品に回答を示して、「(すべての仏陀は)衆生をして仏陀の円満な智慧を開かせようと望んでいる」と語る。この経文にいう衆生というのは、具体的に舎利弗らのような、仏陀の悟りに到達できないとされていた声聞乗・縁覚乗を指し、また衆生というのは救いから見放された一闡提(仏性を欠いている有情)であるといい、さらに広げていえば、衆生とは仏法界以外の九法界を意味することを明らかにしているのである。総じてこうして完全円満な仏道から遠い存在であった人々に、仏陀釈尊は真実の円満な智慧を開かれて、「衆生は無限に存在するが、そのすべてを度(すく)おうと誓う」という仏陀の誓願がここに満足するに至った。同じ法華経方便品には、「我れは本(もと)、誓願を立て、すべての人々が我れ(釈尊)と同じような悟りを得て、決して異なることがないようにと望むのである。そのように我れが昔願ったことどもは、今はもはや満足している」と述べる。法華経譬喩品において、多くの大菩薩たちや多くの神々らは、この教えを聞いて、「私たちは昔からたびたび釈尊の教えを聞いてまいりましたが、いまだかつてこれほど深くてすばらしい教えを聞いたことがありません」と自分たちの理解を語った。日本天台宗の祖・伝教大師はこの経文を解釈して、「今の文の前半の『昔から釈尊の教えを聞いてまいりました』というのは、昔、法華経が説かれる前に華厳経などの大いなる教えを説かれたのを聞いたことをいうのであり、『まだこれほど深くてすばらしい教えを聞いたことがなかった』という後半の文章は、まだ法華経に説くような一仏乗の教え(すべてのものが仏陀と成る教え)を一度も聞いたことがなかったという意味である」と述べている。(これらの経文や解釈によって)華厳経・方等部の諸経典・般若経・解深密経・大日経などのガンジス河の沙(すな)ほども数多くあるもろもろの大乗経典では、釈尊の教えの肝心である「一念三千」を明らかにする大綱(おおおづな)や、要点となる二乗作仏と久遠実成の法門を、まだ聞いていなかったと理解した。
〔第十章〕 本門の一念三千
また、法華経が説かれた今から、諸の大菩薩も、梵天・帝釈・日天・月天・四天王らもはじめて教主釈尊のお弟子になったのである。見宝塔品第十一には、これらの大菩薩を釈尊はご自身のお弟子だとお思いになったからこそ、諫めさとして、「数多くの修行者たちに示したい。わたしが入滅した後に、よくこの経典を護りたもち読誦する者があるか。その志ある者よ、今、仏陀の前で、自ら誓いの言葉を述べなさい」と、非常につよく仰せられたのに相違ない。もろもろの大菩薩たちも、「あたかも大風が小さな樹木の枝を吹き抜けるように」、また吉祥草とよばれる神聖な草が大風にそよぐように、あらゆる河の水が大海へ流れて行くように、仏陀に随ったのに相違ない。しかしながら、霊鷲山で法華経が説かれてから僅かばかりの日時が経過したばかりで、夢うつつのうちに、多宝如来のおわす大七宝塔が出現して、それまでに説いた法華経迹門の教えが真実であることを証明し、さらにこれから説かれる法華経本門の意義を明らかにし、十方世界の諸仏が、釈尊の真実の説法を聴聞するために集まり来たって、「私たちは釈尊の分身である」と名乗られたのである。そのときの状景は、宝塔(ほうとう)が虚空にかかり、そのなかに釈迦牟尼仏が多宝如来と並んで坐り、あたかも日天(太陽)と月天とが一緒に出現したようであった。説法の場に集まった人間界・天上界の方々は星を連ねたようであり、釈尊の分身の諸仏は大地の上、すなわち菩提樹の下の金剛宝座に端座しておられた。
華厳経の蓮華蔵世界は、十方の報身仏と、この世界の報身仏とがそれぞれの国土に居るとする。つまり、他方の世界の仏陀はこの土に来て釈尊の分身であると名乗ることもなく、逆に此の世界の仏陀が彼の世界へ行くこともない。そうしたなかで、ただ法慧・功徳林菩薩らの大菩薩だけが彼の世界から此の世界の説法の場へと来られたと説く。大日経や金剛頂経に説かれる、蓮華の八つの弁の上の大日如来をはじめとする仏・菩薩、金剛界曼荼羅成身会(じようしんえ)の三十七尊などは、大日如来の化身仏のように見えるけれども、法身・報身・応身という三身を円満に具足した過去世からの仏ではない。大品般若経にあげる千仏、阿弥陀経にあげる東西南北と上下との六方の諸仏も、この世界へ来集した仏ではない。大集経が説かれる大宝坊に来集した仏もまた、釈尊の分身仏とは言っていない。金光明経の東西南北の四方の四仏は化現(けげん)した仏身に過ぎない。すべて、仏教経典全体のなかで、それぞれに修行を修めた法身・報身・応身の三身を円満に具足した諸仏を集めて、それらの諸仏に対して釈尊はご自分の分身だとは説かれないのである。
このように見てくると、この見宝塔品第十一の分身来集は法華経如来寿量品第十六の遠い序分(いとぐち)なのである。そもそもインドのブッダガヤの菩提樹の下で始めて成道してから僅か四十数年の釈尊が、一劫とか十劫、あるいはそれ以前に成道された諸仏を集めて、それらの諸仏が自分の分身だと説かれている。さすがにそれは他仏も今仏も平等であるとする考えとくい違うことであって、はなはだ周囲を驚かせるものであった。そしてまた、インドで始めて成道した仏であるならば、その仏から教化を受けた弟子が十方の世界に充ち満ちるということは考えられないから、たとえ分身仏を示現する徳が備わっていたとしても、その徳を示し現わしても意味がないことなのである。天台大師は法華玄義巻九下に、「分身がこのように多いのは、まさしく釈尊が成仏してから久しい時間を経過しているということである」といっている。これはつまり、法華経の説法の場所に集まった多くの人が、分身のあまりの多さに大変驚いた状景の意味を述べているものである。
こうした人々の驚きの上に、従地涌出品第十五になると、地涌千界の大菩薩たちが大地から涌き出るように出現したのである。それらの大菩薩たちの尊き姿は、釈尊の第一のお弟子と思われていた普賢(ふげん)菩薩や文殊(もんじゆ)菩薩もとても比較にはならないほどであり、まして華厳経・方等部諸経典・般若経、そして法華経の見宝塔品に来たり集まった大菩薩たちや、大日経などの金剛薩〓らの十六人の大菩薩たちなども、今の地涌の菩薩と比較すると、猿の群れの中に帝釈天が現われたようなもの、野人の中に公〓らが入り交わったような状景であった。仏陀入滅後五十六億七千万年の後に仏教再興を命ぜられている弥勒菩薩ですらも、大いにとまどったのである。ましてそれ以下の人間や天人はいうまでもない。この千世界の大地から出現した大菩薩たちの中に特にりっぱな四人の聖者がおられた。それはすなわち上行菩薩・無辺行菩薩・浄行菩薩・安立行菩薩である。この四人の大菩薩たちの存在は、法華経が説かれた霊鷲山とその虚空(おおぞら)に居たもろもろの大菩薩たちすら、お互いに目をかわし合って理解に苦しむほどであった。華厳経の四菩薩も、大日経の四菩薩も、金剛頂経の十六大菩薩たちも、今の地涌の四大菩薩と対比すれば、視力の弱い人が太陽を見上げ、漁夫が皇帝に向かい奉ったような様子であった。あの太公望(たいこうぼう)をはじめとする尹伊(いんい)・務成(むせい)・老子らの中国の四聖が人々のなかにいるのにも似ていよう。漢の高祖の時代に商山に隠棲していた東園公・綺里季(きりき)・夏黄公(かおうこう)・〓里(ろくり)先生の四人の白髪皓眉(こうび)の老人が高祖を諫めて、若い第二祖恵帝を帝位につかしめて補佐したのにも似ている。実に上行・無辺行・浄行・安立行の四菩薩は高大で堂々として、尊く気高く、その尊さは、釈迦牟尼仏・多宝如来・十方分身諸仏を除けば、一切衆生を仏法に帰依させる指導者とも仰ぎ奉らねばならないほどであった。
そこで弥勒菩薩が心に疑問を抱いて申すのには、自分は釈尊が釈迦族の太子であられた時から、三十歳で悟りを得られ、そして今、この霊鷲山で法華経を説かれるまでの四十二年間、さまざまに経典を説かれた説法の場所で、この裟婆世界の菩薩たちだけではなく、十方の世界から来たり集(つど)った大菩薩たちをほとんど皆知っている。また十方の浄土(清らかな国土)や穢土(けがれた国土)にお使いとして行ったこともあるし、自らも衆生を救うために出向いて、それらの国々で大菩薩たちを見聞もした。ところで、今の上行菩薩等の四大菩薩を指導した師はいったいどのような仏陀なのであろうか。さぞかしこの釈迦牟尼仏・多宝如来・十方分身諸仏とは較べようもないようなりっぱな仏陀でいらっしゃるのであろう。天台大師が、法華経従地涌出品の解釈のなかで、「雨がはげしく降るのを見て、空に居る竜が大竜であると知るのであり、また蓮の花が大きく咲いているのを見て、池が深いことを知ることができるものだ」と述べているではないか。これら地涌の四大菩薩らがどのような国から来たのか、またどのような仏陀の指導を受け、いかなる偉大なる仏法を習いきわめられたのかという、疑問は数数ある。あまりにも疑わしいことばかりで、質問を発することもできないほどであったけれども、仏陀のお力を頂いたためであろうか、弥勒菩薩は釈尊に次のように疑問を申しあげた。「ここに大地から涌き現われた無量千万億のもろもろの大菩薩は、私が修行を重ねてきた昔から今日に至るまでいまだかつて見たこともない方々です。このもろもろの、大いなる威徳をそなえ、精進をかさねてきた菩薩の方々は、いったいどのような仏が教え導いて、その徳を達成させたのでしょうか。誰に従って初めて求道の志を起こし、どのような仏法をほめたたえたのでしょうか……。世間(せけん)・出世間(しゆつせけん)にわたって尊敬を受ける仏陀よ、私は昔から今日に至るまでこのようなありさまに接したことがありません。こいねがわくは、この地涌の菩薩たちの国土の名を説いてください。私は常にもろもろの国土に自ら出向きましたが、いまだかつてこのようなありさまに接したことがありません。私にはこれらの方々の中で知っている方が一人とておりません。どうか、にわかに大地より涌き出てこられたという不思議なことがなぜあるのか、そのいわれをお説きください」(法華経従地涌出品第十五)。
天台大師は法華文句にこの経文の意味を解釈して、「菩提樹の下で悟りを開いたときの華厳経から以降、今の法華経従地涌出品の説法に至るまで、説法の場には十方の世界から大菩薩たちがいつも訪れた。その菩薩の数たるや数えることができないほどだが、私(弥勒菩薩)は、五十六億七千万年の後に釈尊の仏教を継承していく智力があるので、そのすべてを見、また知っている。それにもかかわらず、この方々には一人も知り合いがいない。私は十方の世界に自ら出向き、もろもろの仏陀にお会いし、人々によく知られているのにもかかわらず……」と述べている。さらにこの文章に妙楽大師が注釈を加えて、「智ある人はこれから起きてくることを予見する。蛇がおのずから蛇を認識するのと同様に……」(法華文句記)と述べている。法華経の経文からしても注釈からしてもその心は明らかである。結局のところ、釈尊が初めて菩提樹の下で仏道を成し遂げてから、今法華経が説かれるに至るまで、この裟婆世界でも、あるいは十方の国土でも、これら地涌の菩薩を見たてまつった人はなく、その名を聞いた人もなかった、ということなのである。
釈尊はこのような疑問に答えて「阿逸多(弥勒)よ! あなたがたが昔からこれまでの間に見知ることがなかったこの菩薩たちは、私がこの裟婆世界で無上等正覚に到達してから、これらもろもろの菩薩たちを教化し示し導き、その心をととのえて道心をおこさせた菩薩なのである」と語った。また「私は伽耶城に程近い菩提樹の下で、金剛宝座に坐って悟りを開いて、最高の教えを説き、かくして人々を教化して菩提心をおこさしめ、今すべての仏弟子たちが再び悟りを求める心から退転することのない心の安定を得た。すなわち、私は永遠の過去からこれらの人々を教化してきたのだ」と述べられた。これをきいて、弥勒ら大菩薩たちは大いに疑問をいだいた。というのは、釈尊が悟りを開いてから最初に華厳経が説かれたときには、法慧・功徳林らをはじめ数多くの大菩薩たちが法(おしえ)を讃えるために集まった。それらの方々はどのような人々なのであろうかと思いめぐらせば、釈尊の善き仏道の友であるとおっしゃったほどであるから、なるほどそのような立派なお方であろうと納得したのである。その後に大宝坊で大集経(だいじつきよう)が説かれたとき、また白鷺池で大品般若経(だいぼんはんにやきよう)が説かれたときにおいでになった大菩薩も同様であろうと思っていた。それに対して、法華経従地涌出品で出現した大菩薩は、それらの方々には比べようもなく古くからの菩薩であるように見えた。さぞかし釈尊のお師匠さまであろうかと思われるほどに見えたのだが、釈尊が「これらの菩薩たちは私が教化して、初めて道心(菩提心)を起こさせたのだ」とおっしゃって、幼稚な者たちであったのを教え導いて弟子としたことを明らかにしたものだから、そこで皆はいったいそれはどういうことなのかと、大きな疑問をいだいてしまった。
日本の聖徳太子は第三十二代の用明天皇のお子である。御年六歳のときに百済・高麗ならびに唐の国から日本に渡来して来た老人たちに対して、そのとき、わずか六歳の聖徳太子がこれらは自分の弟子であると仰せられたところ、かの老人たちもまた合掌して、「太子よ、あなたは私たちの師です」と答えたと太子伝にある。非常に不思議なことである。また列仙伝という外典に伝えられる話では、昔、両川の陳転運という人が青城山下に着いたとき、三十歳ぐらいの女性が棒を持って高山の上を飛ぶように走って行ったかと思うと、いきなり百歳の老人と思われる人をなぐるのを見た。陳転運が驚いてそのわけを聞くと、女性は五百余歳であり、修練服薬をしない百十歳の老児をこらしめるのだと言ったという。今の地涌の大菩薩たちの師が釈尊であるということは、このような伝記にも似て不可解なことである。
だからこそ、弥勒菩薩たちが疑って言うには、「世間・出世間にわたって尊敬される仏陀よ! 釈迦牟尼如来がまだ釈迦族の太子であられたとき、釈迦族の宮殿を抜け出て、伽耶城に程近い(ガヤの市街から約十キロの)ブッダガヤの菩提樹下の道場で、金剛宝座に坐して無上等正覚を達成なさった。そのときから四十数年の時間が経過した。世尊よ、どうしてこの僅かばかりの間に、これほどに大いなる仏陀としての教化をなしたのでございますか」と。すべての菩薩たちは華厳経の説法から四十数年間にわたって、幾度かの説法の会座で、疑問を申し上げて、すべての人々の疑問を晴らしてきた。そうした中で、今のこの疑問こそ、第一番に解きがたい疑問であろう。無量義経説法品で、大荘厳菩薩が八万の菩薩衆とともに、釈尊に疾(すみや)かに菩提を成ずるのにはどのような修行をしたらよいかを問うたところ、釈尊はそれまでの四十余年間には久しく修行してのちに成仏を得るとする歴劫成仏を説いたのを翻して、「無量義」の法門を修行すれば疾(はや)く菩提を成ずると疾得成仏を明らかにしたが、今の疑問はそれにも超えるものである。かの観無量寿経に述べられるように、韋提希夫人の子、阿闍世王は提婆達多に欺き誘われて、父の〓婆沙羅王(びんばさらおう)を七重の室内に幽閉し、〓婆沙羅王に食物を運んだ母をも殺そうとしたが、耆婆と月光という二人の聡明な家臣の諫めによって、母韋提希は幽閉されるに至った。釈尊は夫人の心を見透して虚空から目連と阿難とを従えて夫人を訪れたところ、夫人はまず第一に「私は昔、どのような罪があったために、このような悪逆の子を生んだのでしょうか。また世尊は、どのようないわれがあって、提婆達多のような悪人と親族となられたのですか」という質問をした。ここで、「世尊は、またどのようないわれ(因縁)があって提婆達多のような悪人と親族(従兄弟)になられたのですか」という疑問は非常に大切な重大事である。転輪聖王(てんりんじようおう)は和楽の世界に生まれて、敵とともに生まれることはないというし、帝釈天王は鬼と一緒に住むことはない。まして釈尊は無量劫という大変長い間、慈悲を行なってこられた方である。それなのに、どうして大いなる怨みをもつ者と共にこの世に生を享けられたのであろうか。こうしたことと合わせて考えると、提婆達多という大怨敵と親族であるということは、かえって釈尊が仏陀ではないのではないかと当然疑うことになるのであろう。それなのに、釈尊はこの疑問にお答えにならなかった。だから、観無量寿経を読誦する人は、法華経の提婆達多品を知らなければ肝心なことを失うことになってしまう。大涅槃経の寿命品で迦葉菩薩が釈尊に三十六問の質問を重ねたことも、今の従地涌出品の疑問の提出には及ばない。したがって、釈尊がこの疑問に明快な答えを出さなければ、釈尊御一代の聖(とうと)い教えは泡沫と同じになってしまい、一切衆生は果てしない疑いの網にかかって脱れることができなくなってしまうのであろう。如来寿量品が大切であるということは、ここにあるのである。
従地涌出品の後、釈尊は次の如来寿量品で、「すべての世間の神々と人間、そして阿修羅は、今、教えを説かれる釈迦牟尼仏は王子であったとき釈迦族の宮殿を出て修行をかさね、伽耶城に程近いブッダガヤの菩提樹の下(もと)で始めて無上等正覚に到達されたと思っている」と説かれた。この経文は、始めてお悟りを開いたときの華厳経から、四十数年の説法を経て、ついに法華経の安楽行品第十四に至るまでの、すべての大菩薩たちの認識を示している。この経文につづいて「ところで、良家の息子たちよ、我れ釈尊は実は仏道に体達してから無量無辺百千万億那由佗劫という思慮を絶する永い永い年限を経ている」と述べられる。この経文の趣意は、法華経以前の諸経の所説が誤った認識に立つものとして破折することにある。すなわち、華厳経では三箇処にわたって釈尊がブッダガヤの菩提樹の下で「始めて正覚を成じた」といい、阿含経でも同様に「初めて正覚を成じた」と述べ、浄名経(維摩経)では「始めて菩提樹の下に坐って(正覚を成じた)」と述べ、大集経では「始めて正覚を成じてから十六年」といい、大日経でも「我れ毘盧遮那世尊(びるしやなせそん)(=大日如来)が昔、ブッダガヤの道場で」などと述べ、仁王般若経では「(始めて正覚を成じてから)二十九年」といい、無量義経では「我れ釈尊は先ず道場菩提樹の下に坐して修行すること六年」といい、法華経においても迹門の方便品では「我れ始め道場に坐して」といい、つまり法華経の本門が明らかにされる前は、すべて釈尊がブッダガヤの菩提樹の下で始めて正覚を成じたと述べているのに、今の法華経如来寿量品の経文は一言で〈それは大いなるそらごとである〉と否定したのである。
この如来寿量品によって釈尊が無限の過去から教化をつづけてきた仏陀であるということが明らかになったとき、すべての仏陀は皆、久遠の釈尊の分身であることが認識される。それに対して、法華経以前の諸経と法華経の迹門のときは、諸仏は釈尊と対等の立場でそれぞれに修行をかさねた仏陀であるという認識であった。だからこそ、それぞれの仏陀を本尊と仰ぐ者は釈尊をそれ以下に位置づけていたわけである。ところが、今、如来寿量品が説かれて華厳経の蓮華台上、方等部の諸経典、般若経、大日経などのそれぞれの仏陀は皆釈尊の分身であることが明白となった。釈尊が三十歳で正覚を成じられたとき、インド統治の神であった大梵天王や、欲界第六天の頂にいる他化自在天たちは、釈尊の姿に感銘し、帰伏して、神々が支配していた娑婆世界を釈尊の世界に帰伏せしめた。そして今、法華経以前の諸経、法華経の迹門では、十方の世界にこそ浄土があり、この娑婆世界は迷いの世界であるとしていたのが逆転して、この娑婆世界こそ仏国(浄土)であり、浄土とされていた十方世界は仏陀が権(かり)に姿を現したけがれた国土であることが明らかにされた。
このように釈尊は久遠の仏陀であるから、迹仏(しやくぶつ)(垂迹の仏陀)に教化された大菩薩や他方の国土の大菩薩もすべてみな教主釈尊のお弟子なのである。(だから)すべての経典の中で、この如来寿量品が説かれなければ、あたかも天に太陽や月がないようなもの、国に大王がいないようなもの、山河に珠がないようなもの、人に神(たましい)がないようなものであるとしっかり理解しなければならないはずなのに、華厳宗・真言宗など、真実に対する権(かり)の教義を伝える諸宗のなかでは智慧ある者とされている華厳宗の第四祖清涼大師澄観、三論宗の祖嘉祥大師吉蔵、法相宗の祖慈恩大師窺基(きき)、日本真言宗の祖弘法大師空海ら、ひとまず権の仏教教義を伝える人々は、一方では自分の宗派が依り所とする経典を讃えるために、それぞれ次のように述べている。すなわち、華厳宗は華厳経を説く仏陀は永年の修行の上で絶対の悟りに到達した報身の仏であるのに、法華経はこの世に肉体の身をもってお出ましになった応身の仏が説いたにすぎないとか、真言宗では法華経如来寿量品の仏陀は無明の辺境の境地にあるのに対し、大日経の仏陀は無明をすべて超克した境地にあると説く。
雲は月を隠し、誠心のない家臣は賢人を見失わせるという。人にだまされれば、ただ黄色いだけの価値のない石も宝玉に見えてしまい。へつらっているだけの家臣も賢人かと思ってしまう。今、濁悪世の学者たちは華厳宗や真言宗の僧らのいつわりの教義に隠されてしまって、せっかく如来寿量品で明らかにされた宝玉を手にとろうとしない。また、天台宗の人々もだまされて、黄金とつまらない黄色の石とを同じ価値と思い込んでしまっている。仏陀が久遠の昔に成道なさったのでなければ、教え導かれる人々も少ないということを洞察しなければならないのである。月はその影を映すことを惜しまないが、水がなければ映すことができない。仏陀は衆生を教化しようと思っても、成仏の因縁が薄ければ、八相成道を現わすことはない。たとえば、もろもろの声聞たちが別教の初地、円教の初住という悟りへの段階にはのぼったものの、彼らが法華経以前の教えによって、自己の修錬と自己の解脱だけに専心していたために、法華経の教えを受けても、やっと未来の成仏を保証されるに止まったのである。
そのように、教主釈尊がブッダガヤの菩提樹下で始めて成道したというのならば、梵天・帝釈天・日天・月天・四天王らは世界が創成されたはじめからこの娑婆世界を統治していたとしても、法華経以前の四十数年間の仏弟子でしかない。霊鷲山での八年間の説法を頂いて法華経に縁を結んだ人々も、始成正覚の仏陀が実は久成の仏陀であることに気づかず、久しくこの土に住する梵天・帝釈天らに差をつけられているようなものである。それに対して、今、久遠実成が明らかにされれば、東方の薬師如来の脇士である日光菩薩・月光菩薩や、西方の阿弥陀如来の観音菩薩・勢至(せいし)菩薩、あるいは十方世界の諸仏のお弟子、大日経、金剛頂経の金剛界・胎蔵界という両部(両界)の大日如来のお弟子の諸大菩薩すらも、実はすべて教主釈尊のお弟子であることが明らかになるのである。諸仏が釈迦如来の分身である以上、諸仏から教化を受ける者が同様に教主釈尊のお弟子であることは改めて言うまでもない。ましてや、この娑婆世界の生成の初めからの存在である日天子・月天子、多くの明星天子などはすべて教主釈尊のお弟子ではないのか。
〔第十一章〕 諸宗が本尊を見失うのを批判する
ところが久遠実成の教主釈尊という意義を知らないため、天台宗以外の各宗は本尊に迷っている。倶舎宗・成実宗・律宗は、三十四の心を経過して煩悩を断ち切り、成道をなしとげた始成正覚の釈尊を本尊としている。ちょうど天の子である皇太子が迷って自分は庶民の子であると思い込んでいるのと同じである。次に、華厳宗・真言宗・三論宗・法相宗などの四宗は大乗の宗である。その中で法相宗・三論宗は勝れた機根が見たてまつる仏身(勝応身)に似た仏を本尊とする。君主の皇太子に生まれながら、自分の父は武士であると思い込んでいるようなものである。また華厳宗・真言宗は釈尊を低い位置に下げて、それぞれ毘盧遮那仏・大日如来を本尊と定めた。これは君主である父を低い位に見下して、高貴でない者が法王の座に就いた者に随っているようなものである。次に浄土宗は、釈尊の分身の一仏である阿弥陀仏を縁の深い仏陀だと思うあまり、教主釈尊を顧みないのである。禅宗は、身分のひくい者がわずかの徳によって父母をさげすむようなものである。仏陀をさげすみ経典を軽視している。これらは皆、本尊を明確に認識していないためである。例を挙げれば、中国古代の伏羲(ふくき)・神農・黄帝という三皇の治世以前には、人はそれぞれの父を知ることがなかったから、人は皆鳥や獣と同様のようなものであったが、法華経の如来寿量品で久遠の釈尊が説き明かされた意味を認識していない諸宗の人々は、人倫を心得ない者と変わりがない。それは、ほんとうの恩を知らない者だからである。そのために妙楽大師は、「釈尊の御一代の教えの中で、いまだかつて父母の寿命の長いことを顕わした経典はなかった。……もし父の寿命の遠いことを知らなければ、また父の治めている国の由来を知ることはあり得ない。それではいかに智慧のはたらきにすぐれているといっても、人の子として責任を果たしていることにはなるまい」(法華五百問論)と述べている。妙楽大師湛然(たんねん)は唐の第六代玄宗皇帝の天宝年中(七四二―七五五)のころに活躍した天台宗六祖の高僧である。妙楽大師は三論宗・華厳宗・法相宗・真言宗などの諸宗やその依りどころとする経典について深く観察し、広くくらべ合わせた結果、それら諸宗は寿量品の久遠実成の教主釈尊を理解していないから、彼らは父の治める国の由来を知らないため、才能を持ちながら人の道を知らない者と同様であると書き記した。「才能を持ちながら」とは、華厳宗の第三祖賢首(げんじゆ)大師法蔵・第四祖清涼大師澄観、あるいは真言宗の初祖善無畏三蔵らが才能ある仏教の指導者でありながら、父のことを知らない子どものような仏教の理解にとどまっていることを指摘するものである。
〔第十二章〕 一念三千仏種論
日本仏教は総じて顕教(けんぎよう)・密教(みつきよう)として総括されるが、その元祖の伝教大師は、法華秀句下巻で、「天台法華宗以外の宗が依りどころとする経典は、実相の理を説いているから、わずかに仏を生む道理を宿すものの、母の愛だけがあって、(法華経に説く仏種が示されず)父の厳の義が不備である。それに対して法華経に基づく天台法華宗の教えには父の厳・母の愛の両面がそなわっており、まだ悟り得ない凡夫であれ、悟りの境地にある者であれ、すべて仏道を求める者、煩悩を断ちきるために修学の余地ある阿羅漢や煩悩を断ちつくした仏弟子、および悟りを求めて修行しようとする心をおこす者にとっての父である」と。
真言宗・華厳宗が依りどころとする経典には種・熟・脱という大切な三つの教義が名称すら紹介されることなく、ましてその意義が示されるはずもない。華厳宗や真言宗が依りどころとする経典などでは、今の一生の生涯の間に初地という高い悟りに到達し、この身のままで成仏が示されるなどと説かれるが、実際にはその経典は(智慧がまだ調っていない人のために)仮に説かれた教えに過ぎず、仏陀の過去の下種によってそれぞれの悟りがあることを明らかにしていない。(過去世における)下種を知らずに語る現在の解脱であるから、何ら実体があり得よう筈がない。秦の始皇帝の家臣である趙高が、帝の死後、国の実権をほしいままにしようとしたり、孝謙天皇の寵愛により法王の位を受け、帝位をも奪おうとした弓削道鏡(ゆげのどうきよう)に似た幻に過ぎない。考えてみると、諸宗はお互いに自分の宗が優位に立つと主張し合ってきた。日蓮はそのような争いの中に入ろうとは思わない。ただ経典の心にお任せするのみである。法華経が顕らかにする仏種の意義を見出して、インドの天親菩薩は法華論で種子こそ最も尊いもの(種子無上)と論じ、中国の天台大師は一念三千の法門を説いた。さらに言うならば、実は華厳経をはじめとする諸大乗経や大日経などに登場する諸尊の基(もとい)なる種子はすべて一念三千なのである。しかも実に仏教史上、天台智者大師お一人のみこの一念三千の法門を理解し、体得なさっているのである。
ところが華厳宗の第四祖澄観は、この一念三千の義をそのまま自分のものとして華厳経の「心は工(たくみ)なる画師のごとし」という経文の精神として解釈した。真言宗のよりどころとする大日経には二乗作仏・久遠実成・一念三千の法門はまったく述べられていない。にもかかわらず、初祖の善無畏三蔵がインドから中国に来て後に、天台大師の摩訶止観を見て智慧がひらめき、大日経の「心の実相」「我れは一切の本初、号して世の所依(しよえ)と名づく」とある経文を理解する精神として、天台大師の一念三千の法門を巧みにとり入れて真言宗の肝心となる教えとした。その上に誓願や功徳を象徴的に表わす印相(いんそう)、および精神内容を行者に実現せしめるための言語表現たる真言とを秘密の事相(じそう)と装い、法華経と大日経との優劣を判断するにあたって、両経とも理においては同様な高位にあるが、大日経にはさらにその上に勝れた事相をそなえていると解釈した。しかし翻って検討するに、かれらが金剛界・胎蔵界の原理と位置づけているはずの二乗作仏・十界互具の教義は果たして大日経にあるだろうか。この点に真言宗の主張の主要な誤りがある。だからこそ伝教大師は、「新しく将来された真言宗が誇る相承は、実は善無畏がもと天台宗の一行禅師をあざむき天台大師の一念三千を取り入れたという事実を隠し、旧(ふる)く渡来した華厳宗は、法華経にもとづいた天台の四教判をヒントとして法蔵が立てた五教判の事の起こりを隠している」と依憑(えびよう)天台集に述べている。えびす(蝦夷)の島などに渡って、柿本人麿の「ほのぼのとあかしの浦のあさぎりに 島がくれゆく舟をしぞ思ふ」という和歌を、実は自分が詠(よ)んだのだと言ったとしよう。えびすの様子しかしらない人々はそのとおりだと思うに違いない。漢土の学者や日本の学者も、ちょうどこれらの例のように意外と真実を見きわめていないのだ。
伝教大師の弟子智証大師円珍が入唐して開元寺で講義を受けた良〓和尚は、「真言宗・禅門・華厳宗・三論宗等は、これらを法華経などと比較すれば、人を導いて道に入れる方便の門にすぎない」と語った(授決集に円珍が良〓和尚の言葉を記録)。善無畏三蔵が幼少のとき、病気のために一時絶命して閻魔大王の責めにあったのは法華経の一念三千を盗み入れた邪見による。後に心を改め、法華経に帰信したからこそ、閻魔の責めから脱れることができたのであろう。その後、善無畏三蔵・不空三蔵らは法華経を金剛界曼荼羅・胎蔵界曼荼羅の中央に据えて大王のようにあがめ、胎蔵界の大日経や金剛界の金剛頂経を、まるで左右の臣下のように扱ったのは法華経への帰信を如実に示している。日本の弘法大師も、教相の上で論ずるときには華厳宗に心を傾けて法華経を第八住心という低い位置に置いた。しかし修法(しゆほう)・灌頂(かんじよう)などを実際に行なって実慧・真雅といった弘法大師空海の十大弟子、伝教大師最澄の弟子円澄(比叡山二祖)・光定といった人々に伝えたときには、金剛界曼荼羅・胎蔵界曼荼羅の中央に、すでに述べたように善無畏三蔵と同じく法華経を安置した。今、さまざまな例を思い起こすと、三論宗の嘉祥大師吉蔵は法華玄論十巻の中では、「法華経を天台が第五時と定めたのは誤りで、第四時とすべきである――なぜなら、声聞乗・縁覚乗の二乗を開会(かいえ)して菩薩乗とし、二乗を破折して菩薩とする経典であるから――」と述べたけれども、やがてその誤りに気づき天台大師智〓に帰伏して七年間仕え、さらに「自分の講義を解散し、自身の身体を橋として」過ちを悔い改めた。法相宗の慈恩大師窺基は法苑義林章七巻(または十二巻)で法相宗の立場から法華経を見くだして、一乗教は方便、三乗教は真実であると妄言を吐いた。ところがその弟子の鏡水沙門栖復(せいふく)は法華玄賛要集第四巻で、「だからまた法華一乗も真実であり、三乗教も真実である」と法相宗の教えをあいまいにしてしまった。表現からすれば双方の解釈を認めているようにみえるが、その心は天台大師に帰伏したものと見てよい。華厳宗の澄観は大方広仏華厳経随疏演義鈔九十巻を著わし、華厳経と法華経とを比較して法華経を目的に誘導する方便としているようにみえるが、「天台宗が十界・十如・三千の法門を実義とするように、華厳宗の思想も筋道からすれば通じるところがある」と書いていることからすると、法華経を方便といったのを悔い改めたものではあるまいか。弘法大師空海もまた、これらと同様である。鏡がなければ自分の顔を観察することはできない。敵がなければ、自分の欠点を知ることができない。真言宗などの諸宗の学者たちは自分の欠点を知らずにいたが、伝教大師に会ってはじめて自分の宗旨の誤りを知ることができたものであろう。
だから、諸経の諸仏・菩薩・人間・天上の神々たちはそれぞれの経典に導かれて仏陀となったように思われているけれども、実際は法華経に至って正覚を成じることが出来たのである。釈迦とそして諸仏の総願である「衆生は無辺なれば度(すく)わんと誓願せん」以下の四弘(しぐ)誓願は、すべてこの法華経において完全に達成されたのである。方便品に「(我れ本と誓願を立つ。一切の衆をして我がごとく等しくして異なることなからしめん。我が昔の願ぜし所のごとき)今はすでに満足しぬ」と説かれている通りである。
〔第十三章〕 三箇の勅宣と二箇の諫暁によって法華経の行者を確認
われ日蓮が、仏種が一念三千に集約されるゆえんを推察すると、華厳経、観無量寿経、大日経などを読み修行する人を、それぞれの経典の仏陀・菩薩・諸天などが守護するであろうことは疑いのないことである。しかし大日経や観無量寿経を読む行者(仏道を修行する者)たちが法華経の行者に敵対するときには、仏・菩薩・諸天らはそれらの行者をかえりみることなく、法華経の行者を守護せねばならない。たとえば、孝行な息子がいるとして、慈しみぶかい父が王の敵となったとすれば、その息子は父をかえりみず、王のもとへ駆けつける。それが孝のきわまりである。仏法もまたこれと同様である。法華経の諸仏・菩薩・十羅刹女らが日蓮を守護なさるうえに、浄土宗では東西南北と上下の無数の諸仏や、念仏を唱える衆生を護る二十五人の菩薩を説き、真言宗では金剛界曼荼羅・胎蔵界曼荼羅の千二百の諸尊などの守護があると示すが、これら真言宗と南都六宗の七宗の諸尊や守護を誓う善神たちも日蓮を守護するであろう。それら七宗の守護神がかの伝教大師を守ったように。
そこで日蓮は思案して言う。法華経が霊鷲山(りようじゆせん)から虚空会(こくうえ)で、そして再び霊鷲山の山上に戻って説法される間におられた日天・月天(がつてん)などの諸天(神々)は、法華経の行者が出現したならば、あたかも磁石が鉄を吸いつけるように、月影が水面に映るように、ただちに来訪して行者の苦難を代わって受けとめ、仏前で法華経の行者をかならず守護すると述べた誓いをなしとげねばならない筈だと思われるのに、諸天がこれまでに日蓮のもとへ来訪して守護を現わさないのは、日蓮が法華経の行者でないためであろうか。それゆえ、再び経文の趣旨を推考し、日蓮の身に照らし合わせて、わが身に過失があるかどうか検討しようと思う。
次のように疑う人がある。今の世の念仏宗・禅宗などを、いったい、どのような智慧の眼(まなこ)によって、法華経の敵対者であるとか、すべての人々の悪友だと認識できるのか。答えて言う。個人的な見解を述べることは遠慮しなければなるまい。経典とその解釈という曇りのない鏡を出して、正しい仏法を誹謗(ひぼう)する醜い素顔をそのままにうつしだし、その欠点を明らかにしよう。生まれながらにそれが見えない人には力が届かないが……。法華経第四巻、見宝塔品第十一には次のように説かれている。「そのときに、多宝如来が大七宝塔の中で半分の座をあけて釈迦牟尼仏に譲られた。……そのときに、多くの人々は釈迦牟尼仏と多宝如来とが大七宝塔の中の仏陀の坐(いま)す座の上に左右の足を互いに反対の股の上に置き脚を組み合わせ坐っていらっしゃる姿を見たてまつった。……(即時に釈迦牟尼仏は、神通力をもって多くの人々を皆虚空(おおぞら)に移し)大きな声で、すべてにわたり広く僧・尼・男女の信徒にお告げになった。『誰かこの娑婆国土で広く妙法蓮華経を説く者はあるか。今こそまさに忽(ゆるが)せにできない大切な時。我れ如来は長い時間を待つことなく、まもなく入滅する。(それゆえに)我れ仏陀は、この妙法蓮華経を伝えることを託して、将来、それが実現されるように望むのだ』」。これが宝塔品の三箇の勅宣の中の第一の仏勅(釈尊の指示)なのである。
この経文につづいて、次のように説かれる。「そのときに釈尊はくりかえしてこのことを明らかにしようと願って次のように偈を述べられた。『諸聖の主にして世に尊ばれる仏陀、多宝如来は、久しき昔に涅槃にお入りになったものの、宝塔の中にましまして、さらに仏法を未来永遠に伝えるために法華経説法の座にお出ましになった。もろびとは、どうして一生懸命に仏陀の教法のためにつとめないでいられようか。……また我れ釈尊の分身である無量の諸仏がガンジス河の沙(すな)のように無限に現われ来たって真実にして深い教法を聴聞したい……と願って、それぞれの浄仏国土で、そこにいる弟子たちや天人・竜神のいろいろな供養のことどもをさし措いて、妙法蓮華経の法を永遠(とわ)にこの世界に留め置こうと願ってこの法華経説法の場に来たり至った。……諸仏はたとえば大風が小さな樹木の枝に吹きつけるように、この巧みな手段によって真実の仏法をして久しく住せしめる。もろもろの大衆よ、我れ釈尊が入滅した後に、いったい誰がこの法華経を護持し読誦するのであろうか。今、仏陀の前で自ら誓いの言葉を述べなさい』と告げられたのである」。これが宝塔品三箇の勅宣のうちの第二の鳳詔(仏勅)なのである。
「多宝如来と我れ釈尊がよび集めた分身諸仏はまさにこの意(こころ)を知っているはずである。……もろもろの善男子よ、それぞれ真理を見極め思慮を深めよ。この未来悪世にこの経を弘通するということは大変にむずかしいこと。だが当然、大願を立てるべきである。もろもろの経典の数たるやガンジス河の沙ほど数多い。これらを説いたとしても、そんなことはまだむずかしいことのうちには入らない。もし、この世界の最高峰の須弥山(しゆみせん)を手に取って、他方の世界にある無数の仏国土に投げ置いたとしても、そのようなことはまだむずかしいことではない。それに対して、仏陀入滅後の悪世の中でこの法華経を説くこと、これこそ最大の困難なことである。たとえ、この世界を焼き尽くす劫火(ごうか)の中で乾いた草を背負って行っても焼けないでいるということすらも、まだまだむずかしいとは言わない。それに対して、我れ釈尊の入滅した後に、もしこの法華経を奉持して、たとえ一人のためにであっても説く人があろう。これこそ非常にむずかしいことなのである(以上、法華経を説くことの困難を六難として挙げ、それに比べれば、想像もできないほど困難なことも容易なこととして九易(くい)を挙げる説示のなかの一、二の例を挙げている)。もろもろの善男子よ! 我れ釈尊が入滅した後に、誰がいったいこの法華経を受けたもち、読誦するであろうか。どうか今、我れ釈尊の前で自ら誓いを表明しなさい」などと説かれる。これが三箇の勅宣のうちの第三の諫勅(いましめ)なのである。これにつづく第四・第五の二箇の諫暁(いさめ)は提婆達多品第十二に説かれるが、それについては後に述べることにする。
この見宝塔品の三箇の仏勅(ぶつちよく)の経文の心は目の前にある。あたかも青空に太陽が輝いているように。そしてまた素顔に黒子(ほくろ)があるのにも似て。けれども生まれつき視力のない人、正しくものを見ようとしない者、己れの師匠一人だけを尊しとする者、偏見を持って他の意見を受けつけない者などは、それを見ることが困難である。そこで、万難を排して仏道を求める心を持つ者に心おぼえを留めておこう。昔、漢の武帝が長命を願ったとき、西のはての崑崙山に住み、不死の薬を持つ西王母という仙女が空から現われ、三千年に一度実る仙桃(せんとう)を武帝に与えた。また世界を理想的に統治する転輪王が世に出る瑞相(ずいそう)として咲く優曇華は、三千年に一度しか花を見せないと伝える。しかし法華経に会うことはむずかしいのであって、それらのまれな事とも比較にならないほどである。また漢の〓公(劉邦)と項羽との八年間にわたった覇権闘争、源頼朝が挙兵し平宗盛を遂に滅亡させるまでの七年間、日本国中をあげての戦い、阿修羅と帝釈天との、金〓鳥と竜王との雪山(せつせん)の頂上の阿耨池での争い。これらの激しい戦いも、法華経とその他の経典と、どちらが真実を明らかにしたかをめぐる熾烈な検討には遥かに及ぶものではない。日本国でこの法華経の真実が明らかにされたことは二度。すなわち伝教大師によってと、日蓮によってであることを認識せよ。それを見据える器量のないものは疑うがよい。理解する力が及ばないならば仕方がない。この三箇の仏勅の経文は、日本・漢土・インド、そして竜宮・天上・十方世界のすべての経典についていずれに中心があるのか、その勝劣を釈迦牟尼仏と多宝如来と十方分身諸仏が相い集って決定されたものなのである。
問うて言う。華厳経・方等部の諸経典・般若経・解深密経・楞伽経・大日経・涅槃経などは、宝塔品の偈の示す九易に該当するのか、または六難のうちに入るものであろうか。答えて言う。華厳経の歴祖である杜順・智儼・法蔵・澄観ら(経・律・論の)三蔵に精通した高僧や偉大な師たちが、この六難九易(ろくなんくい)の経文を読んで言うには、華厳経と法華経とはいずれも六難の内に入る経典で、名は二つの別な経典だが、説かれるところ、つまりその理は同じである。天台大師が摩訶止観で「小乗の修行の方法に四つの門があるけれども、同一の真理の域に達する」と明かしているのと同様である、と主張している。法相宗の玄奘三蔵・慈恩大師らは、この六難九易の経文を読んで言う。解深密経と法華経とは同じように、一切の諸法は皆心識の変転であるとする唯識の法門であって、釈迦仏一代の教法(第一時有(う)教・第二時空教・第三時中道教)のうちの第三時・中道教であって、当然、六難に該当する優れた教えであると。三論宗の嘉祥大師吉蔵らはこの六難九易の経文を読んでいう。般若経と法華経とは名は異なるが説かれる法体は同じであり、二つの経典は一つの法なのである、と。真言宗の善無畏三蔵・金剛智三蔵・不空三蔵らはこの六難九易の経文を読んで言う。大日経と法華経とは理においては同じで、同じように二経は六難の内に入る優れた経典である、と。日本の弘法大師空海は六難九易の経文を読んで、大日経は六難九易の内には入らない、なぜなら大日経は釈迦が説いた一切経以外の経典であって、法身の大日如来が説いたものであるからという。またある人が言う。華厳経は、法華経が応身(おうじん)の釈迦の所説であるのに対し、報身の毘盧遮那仏の所説であって、六難九易の範疇には入らない、と。これら四宗の元祖たちは、かように六難九易を解釈したから、その流れを汲む数千の学徒たちもまた、この見解を超えることはない。
日蓮は嘆いて言う。以上に紹介した諸宗の歴祖の趣旨を簡単に誤りであると言えば、今の世の人々はきっと顔をそむけてしまうことだろう。そればかりか、不法な行為を重ねて迫害を加えるばかりか、結局は国王に讒言して日蓮の生命の危機にも及ぶこととなろう。しかしながら、われわれの慈しみ深き父、釈尊は、クシナガラの沙羅双樹(さらそうじゆ)の林で涅槃(ねはん)に入る前、最後に遺言として涅槃経を説いた中で、「教えそのものを依りどころとし、教えを説く人に依ってはならない」と語られた。「不依人」とは、比丘は低い階程から高い階程までの(1)出世の凡夫と(2)須陀〓(しゆだおん)・斯陀含(しだごん)(3)阿那含(あなごん)(4)阿羅漢(あらかん)らのそれなりの解脱を得た人を信頼して依りかかってはならないということ。たとえ普賢菩薩・文殊菩薩らの正覚に等しい菩薩が説きたもう法門であれ、経典に基づかない説法を用いてはならない。「仏法の道理が述べ尽くされた経典に基づき、そうでない経典に依ってはならない」と決めて、経典の中でも釈尊の真意を説き尽くした経典と、そうでない経典とをよく吟味して信奉しなければならないのである。竜樹菩薩の十住毘婆沙論には、「論とよばれるもののうち、経文に依らない黒(こく)論(悪しき解釈)に依ってはならず、経文に依る白(びやく)論(正しい解釈)を信頼しなさい」と説き、天台大師は「仏が説きたもう経典に合致するものは書き留めてこれを用い、文証(もんしよう)(経文としての証(あかし))もなく、その義を伝えないものは信奉してはならない」と言う。伝教大師は言う、「仏の説きたもう経典をよりどころとして、口伝(くでん)を信じてはならない」と。延暦寺第五代座主・智証大師円珍は「教えは、経文によって伝えねばならない」と言う。以上挙げてきた諸師の釈は、すべてそれぞれの経典に基づいて勝れた教え・劣った教えを区別しているようだが、皆、自分が信奉する宗旨を堅く信受するのみで先学の誤った理解を究明しないから、仏意を曲げて私情にとらわれての理非の検討にとどまっている。誤った自分の見解を飾るにすぎない法門である。釈尊入滅の後の犢子部・方広部は、仏法を巧みに取り入れた外道(異教徒)であるが、後漢の明帝の永平十年(六七)に中国に仏教が伝えられてから後の中国思想は、釈尊以前の仏法以外の異教徒の論理よりも、三皇五帝の儒教の書物よりも、仏教理論を悪用した誤った論理で強化された、よこしまな教えを巧妙に組み立てている。(仏教内においても)華厳宗・法相宗・真言宗などの中国・日本の学僧たちが、天台宗の正しい道理をうらやみ憎むために、「真実を説く法華経の文を曲げて解釈し、仮に説かれた経典の義に順(したが)わせようとする」ことが盛んである。しかしながら、仏道に帰依する心が強い人は、片寄った見方にとらわれずに、自分が帰依する宗旨であるとか、他人が帰依している宗旨だとか言って勝ちを争ってはならないし、人をあなどってはならない。
法華経法師品第十に、「我が説く所の経典、無量千万億、已(すで)に説き、今説き、当(まさ)に説かん。しかもその中においてこの法華経、最もこれ難信難解(なんしんなんげ)なり」と説く。妙楽大師は法華文句記にこれを注釈して「たとえ諸経の王だという経典があっても、法華経のように已今当の三説を超えた第一の経であるとは言うことはない」といい、また法華玄義釈籤には「法華経は已説・今説・当説の三説を超えた妙法であるのに、これに迷って法華経を誹謗すれば、その罪によってはるかに永い間、地獄の責め苦をうけなければならない」とある。このような経文とその解釈に驚き、一切経ならびに中国・日本の学僧の注釈書を見ると長年の疑問が氷解する。今、真言宗の愚者たちは印相や真言という事相があるのを力と頼み、真言宗が法華経に勝れていると思い込み、あの慈覚大師らも(天台の座主でありながら)真言が勝れていると言われたのであるから、などと思い込んでいる有様ではあれこれ言う価値もない。
大乗密厳経の言葉。「十地経(華厳経十地品)、華厳経、大樹緊那羅経、神通経、勝鬘経その他の経典は、すべてこの大乗密厳経の系統をひくもの。このような大乗密厳経こそは一切経の中で最も勝れた経典である」。
大方等大雲経(または大方等無想経)の言葉。「この経はすなわち多くの経典のなかで、王の中の王である転輪聖王のような存在である。なぜかといえば、この経典の中で衆生の本性と仏性とが永遠不変なるものの教説を含蔵していることを宣(の)べ伝えるからである」。
六波羅蜜経の言葉。「いわゆる過去無量の諸仏によって説かれた正しい法(おしえ)、そして私が今説く、いわゆる八万四千のもろもろの妙法の集積を収めて五つに分類される。一には経蔵、二には律蔵、三には論蔵、四には智慧蔵、五には秘密蔵である。この五種類の蔵によって衆生を教化する。もしそれら衆生が経蔵・律蔵・論蔵・智慧蔵をたもつことができないほど機根が劣っていても、さまざまな悪業や、あるいはまた、衆生が比丘の至極の重罪である四重罪(殺生・偸盗・邪〓・妄語の四波羅夷罪)・比丘尼の重罪である八波羅夷罪(四重罪と触・八事・覆・随を犯す罪)・無間地獄に堕ちる五逆罪や、大乗経典を誹謗中傷する一闡提(仏性を喪失している有情)などのさまざまな重い罪といったもろもろの悪業をつくっていたとしても、その罪を消して速やかに煩悩から解放し、たちまちに悟りに到達せしめる。そのため衆生にもろもろの秘密蔵を説くのである。この五つの法蔵はたとえば牛乳を精製し発酵させて乳味から酪味へ、さらに生蘇味・熟蘇味、そして妙なる醍醐味に至らしめるようにである。総持門(秘密蔵)とは、たとえていえば最高の醍醐味のようなもの。醍醐の味は乳味・酪味・生蘇味・熟蘇味のなかで最も深くすぐれている味であって、よくもろもろの病気をとりのけ、もろもろの衆生をして身も心も安楽ならしめる。そのように、総持門とは経蔵の中でも最も勝れ、よく重い罪を除くものなのである」。
解深密経の言葉。「そのとき勝義生菩薩がまた仏陀に申しあげた。世に尊ばれる仏陀が初め、あるとき、バーラーナシー国(ベナレス)の仙人の集まる鹿野苑(ろくやおん)の中で、ただ声聞乗を志す者のために四諦(苦・集・滅・道)の法門によって正法を説かれていた。その法門は甚だ不思議で、甚だまれにしか説かれない教えで、一切世間のもろもろの天人たちが以前からよく法のままに説くことができないところであったが、しかもそのときに説かれた法門はなお究め尽くしたものでなく、真実の義理を明了にした教えではなく、なお議論が充分に必要なところなのである。世に尊ばれる仏陀が、昔、第二段の説法の時間帯の中でただ志をおこして大乗菩薩行を修行する者のために、一切の法は皆、無自性であり、生ずることも滅することもなく、本来寂静であり、自性は涅槃にあるという真理によって、ひそかに正法をお説きになった。さらに甚だ不思議で、そのうえ甚だまれなことだったが、そのときに説かれた法門もまた究め尽くしたものでなく、なお真実の義理を明らかにした教えでなく、議論が許される場所であった。そして世尊は今、第三段の説法の時間帯の中であまねくすべて仏の教えを求めようと志す者のために、一切の法は皆、無自性であるから、生ずることも滅することもなく、本来寂静であり、自性は涅槃にあるのであって、無自性の性なのであるという真理によって、明らかなすがたで正しい仏法を説かれたのである。最も不思議で、最もまれなことである。今、世尊がお説きになる法門は最上のもの、もはや何ものをも寄せつけないところであって、これこそ真実に仏法の義理を明了にしつくした教えである。もはやさまざまな議論を許す余地のないところである」と。
大般若経の言葉。「聴聞するところの世間・出世間(しゆつせけん)を超越する仏法(おしえ)にしたがっても、皆よく手だてをもってこの般若(空の智慧)という甚だ深い理にひき入れられ、さまざまにはたらく世間の事業もまた般若をもって法性にひき入れられ、一事として法性から離れて存在するものを見ない」と。
大日経の第一巻(入真言門住心品)の言葉。「秘密主(金剛薩〓)よ、大乗の行がある。法にとらわれない心を起こして、諸法は空であって我性(我れという主宰者)がないと見る。なぜならば、その昔、このように修行していた者のように、万法の本体と思われる阿頼耶識を幻のようなものだと見究めたのである」と。またいう、「秘密主はこのような無我の認識を捨て、心の主は自在であって自分の心がもともと不生不滅であることを知った」と。またいう、「いわゆる空性というものは、眼・耳・鼻などによる認識を離れているから、相(すがた)もなく、それを限定する世界もなく、さまざまな無駄な議論を越えて虚空と同じなのである。つまり極めて無自性なのである」と。またいう、「大日如来は秘密主に告げていう、〈秘密主よ、菩提とは何か〉。それに対していう、〈実の如くに自心を知ることである〉」と。
華厳経にいう、「すべての世界の多くの人民の中で、仏の教えを聞き悟ることを願って声聞の道を求める者は少ない。仏の教えによらず、自ら道をさとることを願って縁覚の道を求める者はますます少ない。大乗菩薩乗を求める者は甚だまれである。しかし、大乗を求める者に会うことはまだたやすく、充分にこの華厳の法を信じることは甚だむずかしい。まして十分に受持し、正しく心にきざんで忘れることなく、教えの通りに長い修行をし、真実に理解する人を確かめることは非常に困難なことである。三千大千世界を一劫という長い間、頭の上に捧げて少しも身体を動かさないことなどはさほど困難なことではなく、それに比べてこの法を信じることは大変にむずかしい。また、大千世界の塵の数にも比べられるほど数多くの衆生たちに、一劫の間、生活を楽しむ品々を供養をする功徳よりも、この法を信ずる功徳こそ比べようもないほど勝れている。もし掌(てのひら)に十の仏国土(すなわち十の三千世界)を持って、虚空の中に一劫の間居たとしても、それはそれほどむずかしいことではない。が、この法を信ずることは比べようもなく大変にむずかしい。十の仏国土の衆生に一劫の間、生活を楽しむ品々を供養したとしてもその功徳がすぐれているとは言えず、この法を信じる者の功徳の方がいちだんと勝れているのである。十の仏国土の無数の如来(仏陀)を一劫の間敬って供養するよりも、よくこの経をたもつ者があれば、その功徳の方が最も勝れているといわねばならない」と。
涅槃経にいう、「もろもろの大乗の広大な経典はまた無量の功徳を達成するが、この涅槃経と比較しようとすると、どのような譬喩も及ぶことができない。即ち、この涅槃経はほかの大乗経典よりも百倍・千倍・百千万億倍どころか、あらゆる計算や譬喩によっても表現しようがないほど勝れているのである。善男子よ、たとえば牛から牛乳をしぼり、牛乳から酪を生み、酪から生蘇を生み、生蘇から熟蘇を生み、熟蘇から醍醐を生むのであって、醍醐はこの上もない最高の味である。以上を五味という。もしこれを食すれば、あらゆる病気はなくなる。なぜなら、すべてもろもろの薬もことごとくその中に含まれているようなものだからである。善男子よ、仏陀もこのような尊い方である。仏陀によって十二部経が説かれる。十二部経から修多羅(小乗経)を生み、修多羅から方等経(大乗経)を生み、さらに方等経から般若(波羅蜜)経を生み、般若経から大涅槃経を生んだのだが、その大涅槃経は今述べた五味のうちの五番目の醍醐のように尊いのである。その醍醐というのは、涅槃経に説かれている仏性に喩えているのである」と。
以上、八つの経文を挙げたが、これらの経文を法華経法師品の已・今・当の三説超過の経文や見宝塔品の六難九易の経文と比べてみると、あたかも月と星がならんでいるようなもの。須弥山の金輪(こんりん)の上にある九つの山のそれぞれが須弥山に拮抗しようとしているようなもの(法華経が諸経に勝れていることは明白である)。ところが、華厳宗の第四祖清涼大師澄観や、法相宗の慈恩大師窺基、三論宗の嘉祥大師吉蔵、真言宗の弘法大師空海らといった、(肉眼の上に諸法の実相を明らかにする)仏眼を得ているほどの人ですら、なお法華経の已今当・六難九易の明文をよく理解できずにいるのである。まして、視力を失った人はその経文を確かめられないが、今の世の学者たちは、法華経の今の経文と諸経とのどちらが勝れ、どちらが劣っているかを区別することができないでいる。黒と白とのように明白な違いがあり、須弥山と芥子粒とのように大小の違いが明白であるような、法華経と諸経との勝劣の認識に迷っているのである。まして、虚空のように広大な理に迷ってしまうことであろう。教えが浅いか深いかを知らなければ、理の浅い・深いを区別することができる筈はない。先に引用した八つの経典の文は巻数を無視して挙げられ、また経文の前後が乱れているから愚者には教門(教相)の見分けがつきかねるだろうから、それについて述べて理解の助けとしよう。王といっても小王と大王とがあり、前述の大雲経は小王にすぎない。すべてといっても小分けを指す場合と全部を指す場合とがあり、前述の密厳経の一切とは前者の意味にとどまる。乳味以下の五味についても、仏教全体にわたって喩えるときと、仏教の一部について喩えるときとがあるから、その違いを心得なければならない。前述の六波羅蜜経は重い罪を犯した有情の成仏を説くけれども、無性有情(もともと仏性のない者)については成仏を説かない。まして釈尊の久遠実成によって一切衆生への永遠の教化による成仏を説き明かすこともない。それでは涅槃経の五味の教説にも及ぶことはない。まして法華経の迹門に説かれる二乗作仏、本門に説かれる久遠実成の教説に対抗できないことはいうまでもない。しかるに日本の弘法大師はこの六波羅蜜経の経文の理解に迷って、法華経を五味のうちの第四の熟蘇味に入れてしまっている。弘法大師は密教(総持門)を五味の第五、醍醐味に配当しているが、実はそれは涅槃経にも劣っているものである。まして法華経の醍醐味が涅槃経よりもはるかに勝れているのをどうして見失ってしまったのだろう。そのうえ、弘法大師は弁顕密二教論で「中国の学僧たちが争って六波羅蜜経の醍醐を盗んだ」といって天台大師らをその奥義をひそかに奪い取ったとして非難している。また、同書に「古(いにしえ)の学者たちが醍醐味を嘗めなかったのは遺憾なことである」といって、真言宗を自賛しているのである。
これらについては、しばらくおき、日蓮の一門の者のために書きとどめておく。日蓮一門以外の人たちは法華経の真実の教えを信じないから、(法を謗(そし)ることが、かえって仏道に入る機縁となる)逆縁の人々というべきである。海水の一滴をなめて大海の潮の味を知り、花の咲くのを見て春が来たと推察せよ。たとえ万里の海を渡って宋の国に入らなくても、三カ年という長年月をかけてインドの霊鷲山(法華経説法の地)に行かなくても、あの竜樹菩薩のように海に分け入って竜宮の七宝蔵を開き仏法をうけることがなくても、無著菩薩のように小乗仏教にあきたらず弥勒菩薩に会って大乗の空観(くうがん)(空の思想とその実践)を獲得しなくても、霊鷲山で説き始められ、虚空に場所が移され、後にふたたび霊鷲山で説かれた法華経の説法を聴聞できなくとも、しかしながら釈尊の御一生に説かれた教えの中で、どの経典が勝れ、どの経典が劣っているかは知り得ることなのである。蛇は一週間前に洪水が起きることを予知できるという。それは竜の親族だからである。また烏は年中の吉凶を知っているという。烏が過去に占いをする陰陽師であったためである。そしてまた、鳥は飛ぶ能力がある点では人よりも勝れている。(このように、それぞれ勝れた能力を持っていることになぞらえれば)日蓮は仏教の諸経典のうち、どの経典が勝れ、どの経典が劣っているかをよく知っているのであって、その点においては華厳宗の清涼国師澄観、三論宗の嘉祥大師吉蔵、法相宗の慈恩大師窺基、真言宗の弘法大師空海よりも秀れている。それは天台大師智〓、伝教大師最澄の芳躅(ほうちよく)を恋い慕うためである。それに対して今挙げた各宗の碩徳たちは、天台大師・伝教大師に帰依しなければ正法(真実の仏教)を誹謗するあやまちを免れることができるはずがないのである。今の世、日本国でまず第一に豊かさに恵まれている者は日蓮であるだろう。(それに感謝して)生命は法華経にすべて差し上げる。そして名をのちのちの代までも留めたいものである。大海の主人公となれば、海に流入する河川のもろもろの河神はそれに服従する。高い山々の王である須弥山にもろもろの山神が服従しないことがあるだろうか。(これらの例になぞらえれば)法華経の六難九易について深い理解があれば、たとえ仏教経典のすべてを熟読しなくても、法華経と諸経との勝劣は自ら判明するに違いない。
(前述の通り)見宝塔品第十一で三箇の勅宣が明らかにされたうえ、さらに提婆品で二箇の諫暁が明らかにされる。提婆達多は(釈尊に敵対し、殺害心を抱いた悪人で)善根を断ち切ってしまったのに、法華経の提婆達多品に至って、突如として釈尊から将来に成仏をなしとげて天王如来となるとの保証を得た。涅槃経四十巻は「一切衆生悉有仏性(いつさいしゆじようしつうぶつしよう)」、すなわち、生きとし生ける者は仏性をそなえていると説くが、現実に提婆達多という大悪人ですら成仏を遂げることは、提婆達多品で初めて説かれた。善星比丘や阿闍世王など、無量の五逆罪を犯した者や謗法の罪を犯した者から、一人の頭目をあげて、すべて枝葉を従えたのである。つまり、五逆罪(殺父(しいぶ)・殺母(しいも)・殺阿羅漢(しいあらかん)・破和合僧(はわごうそう)・出仏身血(すいぶつしんけつ))、七逆罪(出仏身血・殺父・殺母・殺和尚・殺阿闍梨・破羯(はこん)磨転法輪僧・殺聖人)、謗法(ほうぼう)(正法を誹謗する者)という悪業を犯した者、一闡提(善根を本来失っている者)という成仏できない者の将来成仏の保証が今この提婆達多品において天王如来の将来成仏の保証によって明らかにされたのである。毒薬も変転して美味な甘露となる。しかもその味はあらゆる味よりもぬきん出ているのである。(それと同様に)提婆達多品の後段で、わずか八歳の竜王の娘が成仏を遂げるありさまを明らかにするが、それはただ竜女一人の成仏を表わしたものではなく、すべての女性の成仏を象徴的に表わしているのである。(なぜならば)法華経以前に説かれた経典のうち、さまざまな小乗経典では女性の成仏を許さない。またもろもろの大乗経典では成仏、また浄土への往生を許しているようではあるけれども、法華経のように即座に成仏するのではなく、心を改め、発心して悪を転じた後に成仏するという段階を経なければならず、一瞬の心に三千の法界が完全に具わるという法門に到達しての成仏ではない。したがって成仏といい往生とはいっても、それは名のみで、実のないものである。「一つの事柄を挙げてもろもろの例を示す」ということがあるが、竜女の成仏は末代の女性たちがそれぞれ成仏や往生をとげる道を初めて開いたものといえよう。
儒教は父母への孝養を重んじるが、それも今の世に限定されて、父母の後生(ごしよう)をたすけないから、儒教で聖人・賢人と称賛される方々も、実際には名のみで実がないのである。外道(インドの宗教思想)などは過去世・未来世がわかっているけれども、父母の後生をたすける道を見出していない。(そのような儒教・外道に対して)仏教こそは父母の後生をたすけて成仏を実現するからこそ、名実ともに聖人・賢人と呼ばれることは真実のことなのである。しかしながら、(同じ仏教といっても)法華経以前の小乗経典・大乗経典を依りどころにする宗旨では、自分自身が仏道の悟りを開くことが困難なのだから、まして父母の成仏を実現することができようか。ただ経文に後生の成仏が説かれるだけで、成仏のみちすじがないのである。(それに対して)今、法華経の説法においてこそ、女人の成仏が明らかにされた時にわが母の成仏も現実のこととなり、提婆達多という最大の悪人の成仏が説かれた時にわが父の成仏も現実のこととなるのである。だからこの法華経は仏教の孝経である、と言える。と、このようにして提婆達多品で二つの諫暁が説かれおわった。
〔第十四章〕 未来記の明鏡
以上の通り、見宝塔品の三箇の勅宣、提婆達多品の二箇の諫暁、合わせて法華経の五つの尊いみことのりが説かれたのに驚いて、勧持品において迹化の菩薩の法華経弘通の誓いが説かれる。(その勧持品で法華経を弘める行者を妨害する三類の強敵が現われるという)末法の世を映し出す曇りのない鏡によって、今の世の禅宗・律宗・念仏の僧と信奉者が正法(法華経に昂(たか)められた仏法)を誹謗していることを知らしめよう。日蓮という法華経の行者は、去年の九月十二日の深夜(子丑の刻)に頸を刎ねられた。そして、この開目抄は日蓮の魂魄が佐渡の国に到着して、その翌年の二月、雪深い中で著わし、親しい縁に結ばれている弟子たちへ送るのであるから、恐ろしいことと思うであろうが、少しも恐ろしいことではないのだ。それにしても、開目抄を眼にする人はどんなにか恐怖心におそわれることであろう。この開目抄は釈迦牟尼仏・多宝如来・十方分身諸仏が打ち〓って、未来の日本国、つまり今の末法の世を映し出す曇りなき鏡なのである。だから、日蓮の形見であるとも理解しなさい。
法華経の勧持品第十三に、八十万億那由佗(のくなゆた)もの多くの菩薩たちが釈尊に滅後の弘経を誓って次のようにいう。「ただ願わくは、御心配なさらないでください。釈尊が御入滅になられた後、恐怖に充ち〓れた悪世の中で、私たちはまさに広くこの法華経の救いを人々に伝えましょう。たとえば、多くの愚かな人が現われて悪口を言ったり、ののしったりするばかりか、刀で切りつけたり杖でなぐりかかるでしょうが、私たちは皆まさしくそれを耐え忍びましょう(三類の強敵のうち、第一俗衆増上慢の迫害に耐えること)。また悪世の中の比丘(僧)は邪(よこし)まな智に左右されて、自分の心を曲げて他人にこびへつらい、まだ自分が体得していないことをまるで体得してしまったように思い込み、自分の才能を頼んで他人を軽んずる心で充ち満ちてしまうことでしょう(第二道門増上慢のこと)。あるいは人里離れた静寂の地に住み(阿練若住)、律に定められたとおり、使用に堪えない弊衣をつづったものを僧衣として着用し、修行に最適の場所にいて、自分こそ真実の仏道を修行していると思い込んで人々を軽んじ侮る者がいることでありましょう。自分のための貪りを求めるために、一般の人々のために法(おしえ)を説いて世間の人に敬い尊ばれるそのありさまは、六神通(神足通・天眼通・天耳通・他心通・宿命通・漏尽通)を体得した阿羅漢のように見られるほどです。しかもこの人は悪心をいだき、いつも仏道とは程遠い世間通俗のことだけが念頭にあって、自身が修行に適した閑寂の地に住していることを強調し、そうでない私たち菩薩の欠点を指摘してきます。そして、いつも人々の中にあって私ども菩薩たちを誹謗するために国王・大臣、祭祀をつかさどるバラモン・商工業者の富豪や、ほかの僧侶たちに向かって、私ども菩薩たちを悪しざまに誹謗して、『この菩薩たちは邪まな論理で仏教以外の論議を説くのだ』ということでしょう。濁乱の時代、悪世においては、さまざまな恐怖があるでしょう。悪鬼がそれら聖者とあがめられる人の身に入って、(菩薩である)私たちをののしったり、はずかしめたりすることでしょう。また、濁乱の時代の悪い僧たちは仏陀の方便を駆使しての衆生の教導を知りもせずに悪口を言ったり、眉をひそめたりして(そのために菩薩である私たちは)しばしば追放されたり、人々と共住を許されず、塔寺から遠ざけられることとなりましょう(第三僭聖増上慢)」と。
法華文句記第八巻に今の経文を解釈して次のようにいう。「文に三ある。初めに『諸の無智の人の』という一行は邪まな人を明らかにする。すなわち俗衆増上慢のことである。次に『悪世の中の比丘は』という一行は道門増上慢の者を明らかにし、第三に以下の七行は僭聖増上慢を明らかにする。この三者の中で、第一についてはまだ耐え忍ぶことができるかもしれない。第二は第一と比べると程度を越えており、第三になると最も程度が甚だしく耐えがたい。なぜなら第二・第三については後々(のちのち)の者ほど判断ができなくなってくるためである」という。東春沙門智度が著わした法華疏義〓にいう。「初めに勧持品の『諸の無智の人の』以下の五行は、第一に一行の偈は身業(しんごう)・口(く)業・意業にわたる悪を耐え忍ぶ人で、これは眼に見える悪を行なう人である。次に『悪世の中の比丘』以下の一行の偈は、勝れた法と証(さとり)を体得していないのに体得していると思いあがっている出家を意味している。第三に『或は阿練若に』以下の三行の偈は、出家のあり方の中にすべての悪人を集約しているのである」という。またいう、「『常に大衆の中に在って』以下の二行は国王・大臣などに向かって正しい法をそしり、それを伝え弘める人を誹謗する人がいる」などと。
涅槃経巻九「如来性品」にいう。「良家の息子たちよ。一闡提(善根を断じた人)がいる。彼は煩悩を断ち切ったとして世の人々から阿羅漢のように敬われ、人里離れた閑(しず)かな場所に住み、そして方正・平等の大乗経典を誹謗するのである。それなのに多くの凡人たちは、この人を真実の阿羅漢であり、大菩薩であると讃えるであろう」と。また同経の同品にいう。「そのときに、この涅槃経が世界中に広く弘まるであろう。このときに、まさに多くの悪い出家僧がいて、この経をかすめ取り、水増しをして多くの経典につくり、正しい仏法の色や香りや美(よ)い味わいをなくすことであろう。この多くの悪人はまた、このような優れた経典を読誦しながら、真理に体達した仏陀の深い秘密の巧みな意義を失わせてしまい、世俗に受けられるように飾った文章や、意義のない言葉を据え置くのである。前の方から抜き書きして後の文章に付けたり、後の方から抜き書きして前の文章に付けたり、あるいは前と後の文章を中間の文章に入れたり、中間を前と後の文章に付けたりもする。まさしく知らねばならないことは、このような多くの悪い僧こそは人の善事を妨害する悪魔の仲間なのである」と。大般泥〓経巻六の問菩薩品にいう。「(一方では)供養を受けるに値する阿羅漢のような様子をしている一闡提がいて悪い行為をする。(他方では)一闡提のように誤解されそうな阿羅漢がいて慈(いつく)しみの心を現わすであろう。ここに、阿羅漢のような様子をしている一闡提が居るというのは、こうした多くの衆生が大乗経典を誹謗しているありさまをいうのである。また、一闡提のように誤解されそうな阿羅漢は、仏陀の教誡の声を聞いて悟る声聞を否定して、広く大乗経典を説くのである。そして衆生に語って言うには、〓私とあなたがたとは倶に菩薩の道を歩む者なのである、なぜなら、すべて生きとし生ける者(衆生)は皆、如来(真理を体現した仏陀)と同様の本来の性質をもつからである〓と。それなのに彼ら衆生自身は、この阿羅漢を一闡提だと思うであろう」と。また涅槃経巻四如来性品にいう、「我れ釈尊が涅槃に入ってから後、正しい仏法が衰退した後の時代、像(かたち)だけ法(おしえ)が伝えられている時代にまさしく持戒の僧がいるであろう。彼等は戒律をその通りに践(ふ)み行なっているように見えるが、しかも経典を読誦することは少なく、飲み物・食べ物をむさぼり好み、その身をながらえ、袈裟を身に着けてはいるものの、あたかもその姿は猟師が注意深くゆっくりと獲物を狙って行くように、猫が鼠を狙っているようなものであった。しかし彼は常にこのように言う。〓私は煩悩を断ち切って阿羅漢の悟りに到達した〓と。そして外面からすると賢く仏道を修行しているように見えながら、内心に貪りや嫉妬の心をいだいている。それは無言の行を修めた婆羅門にも似ている。真実には出家して仏道を修める沙門ではないのに、沙門の形をし、道理を無視した邪まな考えにとらわれて、正しい仏法を誹謗することであろう」などと。
そもそも霊鷲山で説かれた法華経と、沙羅双樹の林で釈尊が入涅槃に際して説かれた涅槃経とは、日や月とが並んだような姿。それに加えて常州毘陵郡に住した妙楽大師湛然が天台大師の法華文句を注釈した法華文句記、さらに東春の智度法師の法華疏義〓という曇りなき鏡に、今の時代の諸宗や日本国中の禅宗・律宗・念仏者たちの醜い顔を映してみると、いささかの曇りもなく謗法の醜い様子がよく分かる。妙法蓮華経の勧持品第十三には「仏陀が入滅した後、恐怖(くふ)すべき悪世の中において」といい、安楽行品第十四には「後の悪世において」、また「末世の中において」「後の末世において仏法が滅びようとする時」などといい、分別功徳品第十七には「悪世末法の時」といい、薬王菩薩本事品第二十三には「後の五百歳において」などと、悪世末法ということがくり返しいわれている。また正法華経の勧説品には「しかして後の末世に」「しかして後に来る末世に」などといい、添品妙法蓮華経にも同様な表現が見られる。確かに、天台大師智〓は法華玄義巻十上に「像法の時代、江南に三師と、河北に七師の優れた学僧がつぎつぎと現われたが、彼らはすべて法華経への敵対者である」と述べ、日本の伝教大師最澄は顕戒論などに「像法の末の時代、奈良南都六宗の学者は皆、法華経敵対者である」などと述べているが、しかし、そうはいうものの、そうした天台大師・伝教大師の時代には法華経敵対の様相はまだまだ明らかなものではなかったといってよい。ところがここに掲げた経文は、教主釈尊と多宝如来とが多宝塔の中にさながら日と月が並んでいるように着座なさり、十方の国土より来られた釈尊の分身仏はそれぞれ菩提樹の下で星を列ねたように集まっている中で語られた言葉である。釈尊入滅後、正法(しようぼう)一千年、つづいて像法(ぞうぼう)一千年と、合わせて二千年を経過して末法(まつぽう)の始めに、法華経の救いを妨害する三類の強敵(ごうてき)(俗衆増上慢・道門増上慢・僭聖増上慢)が現われることであろうと、八十万億那由佗もの無数の菩薩たちが評定されたことが、そらごと(虚言)となるはずがあるであろうか。
今の時代は釈尊が入滅して後二千二百余年に当たる。大地を指さしてはずれることがあったとしても、あるいはまた春になっても花が咲かないことがあっても、法華経の教えを妨害する三類の強敵はからなず日本国にいるはずである。そうであるならば誰々の人が三類の強敵に該当するのか。そしてまた、いったい誰が(釈尊の予告を末法に実現する)法華経の行者なのか。待ち遠しいことである。あの三類の強敵に我らも該当することになるのであろうか。あるいはまた、法華経の行者に該当するのであろうか。心もとないことである。ところで、周の第四・昭王の御代二十四年甲寅四月八日の夜中に、突然、天空に五色の光が南北にわたり一面に広がり、まるで昼間のようになったという。大地は六種類に震動し、雨が降った形跡もないのに大きな河や井戸・池に水があふれ、あらゆる草木に花が咲き果実がなったのである。たいそう不思議なことであった。昭王は大変に驚いて、天時暦星の事をつかさどる大史の蘇由に占わせたところ、「西方の国に聖人が生まれました」という。昭王は「この国に聖人は生まれないのか」と問う。蘇由が答える、「そのような事象はございません。一千年の後に、西方の聖人の教説がこの国に渡って衆生に利益(りやく)を与えることでありましょう」と。あのたかだか儒教によって毛の先ほども見惑(けんわく)・思惑(しわく)の煩悩を断ち切っていない者であっても、一千年後のことを予見したのである。果たして仏の滅後千十五年にあたる後漢の第二・明帝の永平十年(西暦六七年)丁卯の年に、仏法が漢土に渡って来たのである。この法華経の予言は、そのような例とは比較にならない釈尊・多宝如来・十方分身の諸仏がたが一堂に会しての多くの菩薩の未来記(予言)なのである。(そう考えれば)今の時代に法華経に敵対する三類の強敵がいないはずがない。さすがに仏陀は付法蔵経に予言して、「我れ仏陀の入滅した後の正法一千年間においては、我れ仏陀が説いた正法を弘めるであろう人、二十四人が順序どおりに相続して現われるであろう」といわれた。たしかに、仏弟子の迦葉尊者・阿難尊者はさて置くとして、百年後の脇比丘、六百年後の馬鳴、そして七百年後の竜樹菩薩というふうに、仏陀の予言に少しも違うことなく、すでに出現しているのである。末法に三類の強敵が現われるということが実現しないはずはない。このことが違うことになれば、法華経全体が皆違ってしまうことになる。すなわち仏弟子の舎利弗が未来に華光如来という仏陀となるであろうとか、同様に迦葉が将来の世に光明如来となるであろうという将来成仏の保証(授記)もすべて虚偽の説となってしまうであろう。そうすると法華経以前に説かれた経典がかえって本物になって、迦葉や阿難は永く成仏することのない多くの声聞達ということになってしまい、そうなっては、たとえ犬や狼に似た野干などを供養しても、阿難らを供養することはないということになってしまう。いったいどう判断したらよいのであろうか。
法華経勧持品に三類の強敵を述べるうち、第一の「諸の無智の人有って」(俗衆増上慢)というのは、勧持品の経文の第二の「悪世の中の比丘」(道門増上慢)と、第三の人里離れた静かな場所で律に適った三衣(さんね)を着した比丘(僭聖増上慢)にとっての大いなる外護者であると考えられる。だからこそ(前述したように)妙楽大師は法華文句記に「諸の無智の人とは即ち俗衆増上慢を指す」といい、東春の智度法師は法華疏義〓に「『常に大衆の中に在って』以下の二行は国王・大臣などに向かって(正法の行者を謗る者)…」と解釈しているのである。第二の法華経の怨敵(道門増上慢)については、勧持品に「濁悪の世の僧は邪まな智恵をはたらかし、人にこびへつらって、まだ達成していないのに悟りに到達したつもりになって慢心に充ち満ちている」と述べ、涅槃経には「この経が弘まるときに悪い僧が現われ出るだろう。……彼らはこの経を読誦するけれども、仏陀の深い教えは失ってしまうだろう」という。天台大師は摩訶止観に「もし信がない者は、妙法を高く聖者の境界に推し上げて、自己の智の及ぶところではないという。もし智のない者は、増上慢の心を起こして己れは仏陀と均しいと思い上がってしまう」と、修行の上から経文の意味を解釈している。中国浄土宗第二祖の道綽禅師は「(一に大聖遥かに去るに由る)二に法華経の理は確かに深いが、凡人の理解はかすかであるから、結局、法華経の救いは凡人の救いとはならない」といい、日本浄土宗の開祖・法然房源空は「(念仏こそ正行であり)それ以外の行は末法の凡人には適合していない。なぜなら諸行が利益を与える時代ではないから」などと述べている。これに対して妙楽大師は法華文句記巻十(随喜功徳品の解釈)で「おそらく誤って理解する者は、初心の功徳が偉大であることを知らないで、功徳はきっと上位の段階にあるに違いないと推察し、この初心をないがしろにしてしまうであろう。だから今、初心の行は浅くても功徳が深いことを示して、それによって経力(きようりき)(法華経の法力)を顕わすのだ」と述べている。日本天台宗の祖・伝教大師最澄は守護国界章に「釈尊入滅後、正法の時代、像法の時代が過ぎ去って、末法の時代が大変間近となった。法華経の一乗教によって救済される機根は今正しくその時に適(かな)っているのである。どうしてそれを知ることができるのかと言えば、安楽行品には『末世、仏法が滅しようとする時である』とあるから」といい、慧心僧都源信は「日本一州が、円頓の教え(法華経)によって救われることを約束された機根のみである」と示しているではないか。このように道綽禅師と伝教大師、法然房源空と慧心僧都源信とは、まったく対立した理解を示しているが、いったいどちらの理解を信じたらよいのか。ところで道綽と法然との理解は仏教聖典のすべてに証拠とする経文がない。それに対して伝教や慧心は正しく法華経の経文を証拠としているのである。そのうえ、日本国中のすべての人にとって比叡山延暦寺の伝教大師は大乗円頓戒を授けてくれた受戒の師である。それを何故に天魔がとりついた法然に心を傾けて、自分にとってまことの仏道の門を示す受戒剃髪の師である伝教大師を、惜しげもなく打ち捨てるのであろうか。
法然が智者であるというのならば、どうしてここに引用した経論の説を選択本願念仏集に引用して、誰もが納得のいくように解釈しないのか。(それをしないのは)人の道理を隠して明らかにしない者というしかない。かくして、第二の「悪世の中の比丘」と指摘されるのは、法然らの戒を無視し、正理に違背する妄見の者を指すことが明らかである。涅槃経巻七・如来性品には「われらは(この経を聞いて初めて正見を得たのだから)今までは邪見の者であった」とあり、妙楽大師は法華玄義釈籤に「自ら蔵教・通教・別教という(円教以外の)三教を指して皆邪見と名づける」と述べ、天台大師は摩訶止観に、「涅槃経の『これよりの前は我等皆邪見の人』と名づけているが、そこにいう邪とは悪のことではないのか」といい、妙楽大師は摩訶止観輔行伝弘決でこの文章を解釈して、「邪はすなわち悪である。この故に知られることは、ただ円教のみを善とする。それにまた二つの意味があって、一には円教に順ずるから善であるし、それに違背するのを悪とする、という相待の意味である。次に執著することを悪とし、体達することを善とする(これは絶待(ぜつだい)の意)。ともかく相待においても絶待においても倶に悪を離れるべきである。円に執著するのですら悪である。ましてそれ以外に執著することがさらに悪であることはいうまでもない」という。
つまり、外道(インドの宗教思想)の善悪は小乗経と比較するとみな悪道である。小乗の善の道、総じて法華経以前の四味・三教は法華経と比較するとみな邪悪であって、ただ法華経のみが正善である。法華経以前の円は法華経の相待妙・絶待妙と比較すればなお悪道。法華経以前の円教は蔵教・通教・別教の範疇に入ってしまうから、なお悪道にあるのである。法華経以前の諸経典に説くように、それぞれの経典の極理を行ずるというのは、法華経の行に比べればなおさら悪道である。まして、観無量寿経などがなお華厳経、般若経などにも及ばない小さい教えを本(もと)として法華経の内容を観無量寿経の中に取り入れて、かえって念仏に対して(法華経を)閣(お)かしめ、抛(なげう)たせ、それに入る門を閉じさせ、その教えを捨てさせたことは、法然のみならず、教化を受けた弟子たちや信徒たちが正しい法(おしえ)を誹謗する者となってしまうのではないのか。釈迦牟尼仏・多宝如来・十方分身の諸仏は、「法をして久しく住せしめんが故にここに来至したもう」ているのである。それに対して法然をはじめとして日本国の念仏者たちは、法華経は末法の時代に、念仏よりも前に滅尽するであろうというのであるから、どうして釈尊・多宝如来・十方分身諸仏という三聖の怨敵にならない筈があろうか。
第三の強敵に関しては法華経勧持品(かんじほん)に「あるいは人里離れた場所に弊衣をまとって空閑(しずか)な所に住み、在俗の人々のために法を説いて世の人々に尊敬されるありさまは、さながら無礙自在なる六神通の妙用を身につけた阿羅漢のようであろう」という。六巻本の般泥〓経には「阿羅漢に似た一闡提(善根を断じた者)が居て悪業を行ない、一闡提に見間違えられる阿羅漢が居て慈しみの心を現わすであろう。阿羅漢に似た一闡提が居るというのは、多くの衆生が大乗経典を誹謗することを指す。一闡提と間違えられる阿羅漢というのは、小さな悟りに執われている声聞を批判して、広く大乗を説き、衆生に語って言うのには、〓私とあなたたちとは倶に菩薩なのである。なぜかといえば、すべては皆、如来の法を具えているからである〓と。しかもその衆生たちはその菩薩を一闡提と言うであろう」という。涅槃経如来性品にいう、「我れ釈尊が涅槃に入った後、像法の時代に比丘が居るであろう。彼は忠実に戒律をたもっているように見えて、実は経典を読誦することも少なく、飲食を貪ってその身を長らく養生することであろう。弊衣を綴った袈裟を身に着けていながら、あたかも猟師が細心の注意を払ってゆっくり進んで行くように、猫が鼠の様子をうかがっているような様子なのである。しかもくりかえし、私は阿羅漢の悟りを得ていると言って、外面には賢く善を修めているように振る舞い、内面では貪りと嫉妬の心に充ち満ちている。その姿は無言の行をなしとげた婆羅門などのように見える。真実には沙門ではないのに沙門のすがたを現わし、邪見をつよくして正法を誹謗するであろう」と。妙楽大師は法華文句記に「第三類の僭聖増上慢こそ最も程度が甚だしい。のちのちの者は前の二類よりもさらにその実態を知ることが難しいためである」と記す。
東春の智度法師が法華疏義〓で「第三に『あるいは阿練若にあって』より以下の三行の偈はすなわち、出家の処にすべての悪人を集約する」と言っているのは、今の日本国ではどこに当たるというのか。比叡山(ひえいざん)であるのか、園城寺(おんじようじ)であるのか。または京都の東寺(とうじ)であるのか、南都奈良の諸大寺なのか。あるいは栄西が建立した京都の建仁寺なのか、鎌倉の寿福寺なのか、建長寺なのか。よくよく明らかにすべきである。比叡山延暦寺の出家の頭(かしら)に甲胄(かつちゆう)をつけるのを指しているのか。三井の園城寺の仏道修行によって煩悩のない五蘊を具えた身(戒身・定身・慧身・解脱身・解脱知見身)に鎧(よろい)や杖を帯びているのを言うのか。しかし、彼らは勧持品の「弊衣を綴った袈裟を身に着けて閑かな場所にいる」という経文とは合致しない。また「世間から尊敬されること、あたかも六神通を身に帯びた阿羅漢」という経文の通りだと人は思うまい。また、妙楽大師の言う「のちのちの者はいっそう認識しがたい」と言えるだろうか。京都には東福寺の開祖で、亀山天皇・後深草天皇の戒師をつとめ、聖一国師の謚号を受けた弁円ら、鎌倉には良観房忍性らのことによく似ている。こういったからといって人を怨んではならない。眼があるのならば、経文に自分の身を照らし合わせて見よ。
天台大師の摩訶止観の第一に「(ここに説く)止観の智慧明らかに禅定静かなることは前代にはいまだかつて聞いたことがないところである」と。これを注釈した摩訶止観輔行伝弘決には、「後漢の明帝が仏教の伝来することを夜、夢に見てから、陳の時代に及ぶまで、かねて禅門に接して衣鉢を伝授する者があった」と。宋の従義の法華三大部補注には、「衣鉢を伝授するとは達磨を指す」と注釈。(摩訶)止観第五巻に、「またある種の禅の修行者がいた。その中で、智目行足が〓って行なわれずに、ただ坐って修行するのみで智慧を磨かない者、ただ智慧だけに関心が行って坐して禅に集中することがない者の双方とも修行が成就しない」と。止観第七巻には、「(天台独自の実践修行門の十種の特色のうち、第九の翻訳の言(ことば)については検討の余地があるが)その他の九つの特色については、世間の文字の法師や事相の禅師とは大変異なっている。ただ観心を修行する一種の禅師があるが、その知見が浅かったり、偽りであったりする。しかし、その他の九つの特色については他家には見出すことのできない天台宗独自の境地がある。これは自讃するわけでもなければ虚言(そらごと)でもない。後世の具眼の人よ、検討してみるがよい」と。これについて妙楽大師の弘決に次のように注釈している。「ここで文字の法師というのは、内面的な観心の理解が無くて、ただ法相(法義の体系)にこだわることをいい、事相の禅師というのは、観心の世界に体達せず、あたかも鼻から胸と脾(ひばら)の間に心を止(とど)めているようなものである。これらは根本的に婆羅門の煩悩におおわれたままの禅定などと同類である。また、止観に『ある種の禅師にはただ観心という一つの意(こころ)がある』というのは、これはかりそめにその主張をゆるやかに取り入れて論じたままであって、きびしくその論理性を問えば、すなわち観心の修行も学解による智慧も欠如しているといわざるを得ない。世間の禅の修行者はひたすら理法を観ずることだけを重く見て、全く教義を自分のものとして理解していない。観心によって経典を解釈し、八正道に反する八邪と、利・衰・毀・誉・称・譏・苦・楽の八風(八法)とを数え挙げて、これを具えているから丈六(一丈六尺)の仏陀と言うのだというような馬鹿げたことをいい、あるいは五陰(色・受・想・行・識)と三毒(貪・瞋・痴)を合計して八邪とするなどといい、六入(眼・耳・鼻・舌・身・意)と六通(天眼・天耳・神足・他心・宿命(しゆくみよう)・漏尽)とを混同し、四大(地・水・火・風)を四諦(苦・集・滅・道)としたりしている。このように経典を解釈するということは、偽りの中の偽りである。どうしてそんな調子で浅はかに論ずることができようか」と。
また止観の第七巻に「昔、〓洛の禅師達磨は名声を天下に轟かし、留まるところには教えを請う者が四方から雲のように集まり、去る時にはあちこちの方角から群衆が集まるというふうに、盛んで轟きわたったが、いったいどんな利益があったのだろうか。結局彼は臨終に際しその教化を悔いた」と述べている。このことを妙楽大師は弘決で注釈して次のようにいう、「〓洛の達磨禅師とは、〓(城)は相州にあるのであって、すなわち北斉が(東魏から譲りうけて)都としたところ。達磨禅師は大いに仏法を興隆して禅師の元祖となった。そしてその〓城の洛(みやこ)の地を教化したが、その当時の人々の心情をおもんばかって達磨の名を出さなかった。その洛こそすなわち(元魏によって)今の洛陽となって繁栄しているところである」。(このように、仏法を正しく受容し修行することは大変にむずかしいことである、と。)般泥〓経第六巻に「究極の処を見ないというのは、そのような一闡提のやからが犯す究極の悪い行為は、かえってはっきりと見えないことをいう」とある。妙楽大師は、法華文句記第八に「三類の強敵の中で、第三の僭聖増上慢こそは最大の敵人である。なぜかといえば、ますます(その悪業の究極を)知ることが困難だからである」と(以上の経釈の諸文により三類の強敵は明らかとなったであろう)。
真実の仏法を見る力を失った者、一面的にしか仏教を見ることのできない者、邪まな見方しかできない者は、末法の始めの時代に出現する三類の強敵を見破ることはできない。わずかながらでも諸法の実相を照らす仏眼を得ている者だけが三類の強敵を知ることができるのである。勧持品の「国王・大臣・婆羅門居士に向かって」という経文に対して、東春の智度法師の法華疏義〓は「国王等の権力者に対し法華の正法と行者とを謗ることだ」と注釈を加えている。そもそも昔、像法の末の時代には、法相宗の護命・修円らが天皇に奏状を捧げて伝教大師をそしり、訴えを起こした。今、末法の始めには鎌倉極楽寺(真言律)の良観や鎌倉光明寺(浄土宗)の念阿良忠らが偽りの訴状を作って将軍のもとに差し出した。これこそ三類の強敵ではないのか。
今の世の念仏者たちが、天台法華宗を信奉している国王・大臣・婆羅門居士らに向かって、「法華経の理は深いけれども、われわれ凡人はそれを極くかすかにしか理解することができない。法は至って深いのに対して、それを受け取る側の機根は極めて浅い」などと言って、法華経の教えを遠ざけるのは、前述の天台大師のいう「妙法を高く聖者の境界に推しあげて、私の智分ではない」とするものではないか。また禅宗の者は言う。「法華経は月をさす指であり、それに対して禅宗の教えは月そのものをつかみとらせるものである。月を得たものにとって指は何の必要があろうか。禅は仏の心そのものを求めるのに対して、法華経は仏陀の言葉を追っているのに過ぎない。釈尊は法華経などのすべての仏教経典をお説きになった後、最後に一房の華を拈(ひね)ってその場の大衆に示された。皆はそれが何のことであるか分からなかったが、迦葉尊者一人だけが釈尊の御意を悟ってほほえんで(拈華微笑(ねんげみしよう))、釈尊から付法相承を受けた。その証拠として釈尊が御袈裟を迦葉に伝え、それから次第に伝えられて第二十八祖菩提達磨に及び、中国においては達磨を初祖として二祖慧可を経て六祖慧能まで伝えたのである」と。このような念仏や禅宗の大きな虚言(そらごと)が日本国中を狂酔させてから長い年月が経っている。
また天台宗・真言宗の高僧たちはそれぞれの宗で高名を得ているけれども、その宗旨のことは充分に極めてはいない。欲望は深く、公家や武家などの世俗の権力を恐れて、こうした念仏・禅などの邪義を承知するばかりでなく、讃め歎えてしまうのである。昔、法華経の説法の場では、釈尊、多宝如来、十方分身の諸仏は、法華経が永遠に伝えられていくことを証明なさった。それに反して、今、天台宗の高僧たちは、「法華経の理は深いが、凡人の理解は微(かす)かなものでしかない」という邪説を承伏してしまった。そのようなわけで、日本国にはただ法華経の名前があるだけであって、法華経によって仏道を体得する人は一人もいないのである。そんなことでは、いったい誰を法華経の行者としたらよいのか。ふり返れば寺院や仏塔を焼失したために流罪される僧侶は数えることができない。また、公家や武家にへつらって識者から憎まれる高僧も多いことであろう。これらの高僧などを法華経の行者というべきなのであろうか。
仏陀の言葉が虚妄でないからこそ、三類の強敵はすでに国中に充満している。しかし、それに対して仏陀の金言が破られたのであろうか、法華経の行者は一向に出現していない。どのように理解したらよいのか、どうしたらよいのか。そもそも、衆(おお)くの世俗の人(俗衆)に悪口を言われたり、ののしられたりしたのは誰であろうか。刀で切りつけられたり、杖で打ちはらわれたりしたのは誰の僧であろうか。誰の僧を法華経を信奉するという理由で公家や武家に訴えたであろうか。誰の僧が「しばしば擯出せられる」と勧持品の経文のとおりにたびたび流罪の刑に処せられたであろうか。日蓮以外に日本国に該当する人はあり得ない。が、日蓮は法華経の行者ではあるまい、なぜなら法華経の行者を守護することを約束している諸天が日蓮を見捨てているから。誰を今の世の法華経の行者として確かめて、仏陀の言葉を真実の言葉と証明することができようか。そもそも釈尊と悪人の代表である提婆達多とは、身体とその影のようにいつも一体で離れることがないのだ。仏教に深く帰依した聖徳太子と仏教伝来をこばみつづけた物部守屋(もののべのもりや)とは、蓮華が花を咲かせるときにすでに蓮台に種子を宿しているような関係にあった。法華経の行者がいれば、そこに必ず三類の強敵がいなければならない。そして、まさにその三類の強敵はいる。とすれば法華経の行者とはいったい誰なのであろうか。その人を探し出し、師と仰がねばなるまい。その法華経の行者に出会うことは(法華経妙荘厳王本事品に説かれるように)一方の眼しか残っていない亀がたまたま浮木の孔(あな)に出会うようなものである。
ある人が言うのには、「今の世に三類の強敵はほぼ存在している。しかしながら法華経の行者がいない。汝を法華経の行者であると言おうとすれば大きなくい違いがある。法華経安楽行品に〈(法華経を読誦する者は)天の諸の童子が来って給使することであろう。(だから)刀杖を加えることもできないし、毒をもって害することもできないであろう〉と述べ、つづいて〈もし人がこの法華経の行者をあしざまに罵れば、その人の口は閉じ塞がってしまうであろう〉と述べている。薬草喩品には〈(法華経を聞きおわって)現世には安穏であって、後生(ごしよう)には善い処(ところ)に生まれるであろう〉とあり、陀羅尼品には〈(法華経を説法する者を悩ます者は)頭が七つにさけて、あたかも阿梨樹の枝のようになってしまうだろう〉といい、普賢菩薩勧発品には〈(後の世において法華経を受持し読誦(どくじゆ)する者は)また現世においてその福報を得るであろう〉といい、また〈もしこの経典を受持しようとする者を見て、その悪をあばき出す者がいるとしよう。それがもし実際のことであれ、あるいはそうでないことであれ、その人は現世に不治の病にとりつかれることになるであろう〉などというように、各所で法華経を受持する者に諸天等の加護があることが明らかにされているではないか」と。この疑問に答えていう。「汝の疑問は大変結構である。よい機会であるからここで不審の点を明らかにしておこう。法華経の常不軽菩薩品には〈(比丘・比丘尼・優婆塞・優婆夷の四衆の中に怒りを生じて心不浄なる者がいて常不軽菩薩を)悪口し罵詈して〉とあり、またつづいて〈(常不軽菩薩が祈りの言葉を説いたときに多くの人が)杖木・瓦石をもってこれを打擲したところ〉とある。涅槃経金剛身品には〈(飢餓を免れるために出家した禿人の輩が正法を護持する者を追い出し)もしは殺し、もしは殺害するであろう〉ということを有徳(うとく)王と覚徳(かくとく)比丘の故事を説く中で述べている。さらに法華経法師品には〈しかもこの経は如来がおわします現在の世ですら、なお怨みや嫉みが多いのであって(まして如来の入滅後には多くの困難があることは言うまでもない)〉などと語られている。釈尊は提婆達多が山の上から落とした大きな石によって足の小指に怪我をするなど、九回も大難にお会いになった。釈尊は法華経の行者ではないのか。常不軽菩薩は但行礼拝(たんぎようらいはい)(ひたすら礼拝する修行)によってさまざまな苦難を受けたが、一乗の行者と言われてはならないのか。仏弟子の目連尊者は竹杖外道に殺害された。これは法華経で将来成仏を保証(授記)された後のことである。迦葉尊者以来の付法蔵の第十四祖にあたる提婆菩薩、第二十五祖の師子尊者の二人は人に殺された。これらの方々は(殺害されてしまったために)法華経の行者ではないということになるのか。中国においても鳩摩羅什の門下で四傑の一人である竺の道生は一闡提も成仏できるといったために邪見と排斥されて蘇州の虎丘寺に流謫(るたく)された。法道は宋の〓宗(きそう)皇帝が仏教を道教化しようとしたとき、その非なることを上申したために顔に焼印を押されて江南の道州に流された。さらにいえば、菅原道真や白居易は正義にもとづいて諫言したために流謫されたが、(彼らが法華経の信仰を持っていたためにそのような行動に出たとすれば)法華経の行者とは言えないのであろうか。
〔第十五章〕 受難をふりかえり立教を宣言して以来の誓願を確かめる
このようないちいちの事象のもとにある心を考えてみると、前の世に法華経を誹謗する罪を犯さなかった者が今の世で法華経の行者となったとき、この行者を世間的なつまらない過失でせめたてたり、罪もないのに危害を加えたりすれば、たちまちにきびしい罰が現われるのではないか。修羅が国の隅々まで治める帝釈天に矢を放てばたちまち罪を受け、金翅鳥が阿耨池の竜王を食べようとして命を落とすように、必ず却ってたちまちのうちその身に損害を受けるのである。天台大師は法華玄義第六で「今の私の悩み苦しみは皆、過去世の罪に由来する。今生に積んだ福報は来世に受けることになる」といい、心地観経には、「過去世にどのような善因・悪因を積んだかを知ろうと思ったならば、それが現在にどのような結果となって現われているかを見なさい。また、来世に善い果が現われるか悪い果が現われるかを知ろうと思うならば、現世で善因を行なっているか悪因を行なっているかを考えなさい」と述べている。法華経の常不軽菩薩品には「その罪おえおわって」とある。常不軽菩薩は過去世において法華経を誹謗した罪が身にあるから瓦や石を投げつけられたと理解されている。ところでまた、来世でなければその次の生、またさらに次の生というように、必ず地獄に堕ちると決まった者は、たとえ重罪をつくったとしても現世では罰が現われない。一闡提人というのはこれに該当する。
涅槃経如来性品には、「迦葉菩薩が仏陀に申し上げた。世尊、仏陀がお説きになった通り、大涅槃の光はすべての者に及び、菩提心のない者もよく菩提の因縁をなすのである」と。またそれにつづいて「迦葉菩薩が仏陀に『世尊、まだ菩提心(ぼだいしん)を起こさない者はどうしたら菩提の因を得られるのですか』と問うた」。仏陀はこの質問に答えて次のように言う、「仏陀は迦葉にお告げになる。もしこの大涅槃経を聞いても、〓自分は菩提心を起こすなどしない〓と言って正法を誹謗する者があるとしよう。この人はたちまち、夜、夢の中で羅刹(悪鬼)が現われて恐怖を感じる。その羅刹に、〓善男子よ、君が今もし菩提心を起こさないと命を奪(と)るぞ〓と驚かされる。この人は恐怖のあまり目覚めてしまって、即時に菩提心を起こすであろう。このように菩提心を起こせば、この人は大菩薩であると知るのである」と。甚だしい大悪人でないならば、正法を誹謗すれば、ただちに夢を見ることによって後悔する心が生まれるのである。また、つづいて(一闡提の者には菩提心が起こらないものだということを)「枯れ木や石の山には水はとどまらない」「〓(い)った種は恵みの雨が降っても芽を出すことがない」「すばらしい珠玉は濁った水を澄ますというが、汚泥を澄ますことはできない」「手に傷のある者が毒薬を手にとれば毒が入るが、傷のない者は毒が入ることはない」「大雨は空にとどまることはない」などという多くの譬喩でその意趣を明らかにしようとしている。結論的にいって、一闡提の人のなかでも一番悪い者は、生まれかわっていくごとに無間地獄という脱出不可能な地底深い地獄に堕ちていくことになっているから、現世においては罰は現われないのである。たとえば、悪政の見本とされる夏の桀王や殷の紂王の治世には天変がなかった。それはあまりに重い罪があって必ずその世が滅亡することになっていたためであろうか。
そうしてみるとまた、この国を守護する神が、この国を見捨ててしまったために現実に罰が現われないのであろうか。正法を誹謗する世を守護神は見捨てて去ってしまえば、諸天もその国を守護することはない。そのような次第であるから、正法を修行している者に守護の効験が示されないで、それどころか逆に大きな法難に会うことになる。金光明経正論品には「善法を修する者が(かえって)日々に衰減してしまう」とある。悪国とか悪い時代というのはこれである。くわしくは立正安国論に論述した通りである。
要するに、法華経の行者を守護するはずの諸天も見捨てよ。あらゆる苦難よ来たれ! 法華経に身命をかけるのみである。あの智慧第一と謳われた仏弟子の舎利弗尊者が、六十劫という長期間にわたって布施(ふせ)の修行をしたのに、その長い菩薩の修行をつらぬき通せなかったのは、舎利弗に眼を施せといった婆羅門が、舎利弗のさし出した一眼を踏みつけにして、もう一眼を施せと責めたのを受け入れることができず、その衝撃で小乗の自己完成の道に転換してしまったためであった。釈尊が如来寿量品で明らかにされた五百億塵点(じんでん)の久遠の過去に下種を受けながら、また、化城喩品に説かれる三千塵点劫の過去に結縁を受けながら、今日に至るまで仏道を達成しなかったのは、悪い指導者に出会ってしまったためである。善きにつけ悪しきにつけ、法華経を捨てるということは地獄に堕ちる行為である。日蓮は(若き日に、釈尊の誓願をうけついで)本来の誓願を立てた。だから、「日本国の国主の位を譲り与えよう、その代わりに法華経を捨てて観無量寿経によって後世の安楽を祈りなさい」と言われたとしても、「父母の首を刎ねてしまうぞ、もし念仏を称えなければ」などというさまざまな大きな法難が起こったとしても、智者によって日蓮の仏教信奉の確信を説破されることがなければ、決して屈服することはない。たとえそのほかの大きな困難が出現しても、それはあたかも風の前に舞う塵のようなものでしかない。日蓮は日本の柱としてこの日本国を背負って行こう、日蓮は日本の眼目となって精神の行く末を見守ろう、日蓮は日本の大船となって人々を安穏の世に渡そうと、若き日に清澄寺で立教の宣言をしたときに誓った三大誓願を破ることはない。
〔第十六章〕 滅罪を果たして解脱を得る
疑っていう。どうして汝が流罪・死罪等に出会ったことが過去世からの因縁によるものと知ることができるのか。答えていう。銅の鏡で照らすとよく衣冠を映し出し、秦の始皇帝が使った人の心を映す鏡は現世での罪をよく映し出す。仏法の鏡は現世の苦楽の果報の原因となる過去世での善悪の行為を映し出す。般泥〓経第四巻にいう、「善男子よ、過去世においてかつて数えられないほど多くの罪やさまざまの悪業を作った。このもろもろの罪報としてあるいは軽んじられ、あるいは醜い身体の様子となり、服装も充分でなく、飲み物・食べ物も粗末で富裕とはならず、貧しい家、邪法を信じる家に生まれ、あるいは国王から刑罰を受け、さらにそのほかさまざまな人間としての苦しみの報いを受けることであろう。しかも現世においてこれらを思いのほか軽く受けるのは教えを護る功徳の力によるものなのである」と。この経文は日蓮の身と照らし合わせると、さながら割符がぴたっと合うようなもので、受難に対する深い疑いがたちまち氷解した。まことに数多くの疑難も理由のないことである。この経典の一々の句を日蓮の身にひき較べてみよう。「あるいは軽んぜられ」といい、法華経譬喩品には「軽んじ賤しめられ、憎まれ嫉まれ」とあるが、日蓮はこれらの経文の通りに軽んぜられあなどられてきた。「あるいは醜い身体の様子となり」「服装も充分でなく」というのはまったく日蓮の姿そのものであり、「飲み物・食べ物も粗末で」というのも日蓮の姿さながらであり、「富裕とはならず」というのも日蓮の姿であり、「貧しい家に生まれ」というのもそうであり、「あるいは国王から刑罰を受ける」というのもそうであって、この経文はまったく日蓮の身にそっくりあてはまっていることに疑いの余地がない。法華経勧持品二十行の偈には「度々(たびたび)追い払われ」とあるのは、前掲の般泥〓経に「種々の人間の苦報あらん(さまざまな人間としての苦しみの報いを受けることであろう)」とあるのに一致するし、「これらを思いのほか軽く受けるのは教えを護る功徳の力による」ということは、摩訶止観第五巻にも「散乱心で起こす善根は弱々しくて過去の重罪を動かすことができないが、今、止観を修行してどのような対境にもまけない心構えができれば、過去の善悪の業を動かすことができる」と説示するところであり、またそれを行なおうとすると、「正道の障害となる報障・煩悩障・業障という三障と、そして五陰(ごおん)の苦を引く陰魔・煩悩魔・死魔・天子魔の四魔が入り乱れて現われてくる」ことも警告しているのである。
(つらつら思うに)日蓮には無限の遠い過去から悪王と生まれて、法華経の行者の衣食や田畠などを奪い取ったことが数知らずあったことであろう。それは丁度、今の世に日本国のさまざまな人々が(心を〓えて)法華経を説く山中にある寺を滅ぼすのと同様であったに違いない。また法華経の行者の頸を刎ねたこともその数を知らないほどであったであろう。ところで、こうした重い罪の償いをなしとげたところもあるであろうし、まだまだ償いを果たしきれないところもあるであろう。償いを果たしきったといっても、その余残がまだまだ残っている。人が生死の迷いを離れるときには、必ずこの重罪をすべて消しつくさねばならない。しかし、功徳はわずかのものに過ぎず、それに比べてこうして重ねてきた罪は甚だ深く重い。仮に説かれた仏陀の教えを修行していた間には、まだこのような重罪が生じることはなかった。鉄を精錬する際に、高度な精錬にまで及ばなければ、疵(きず)があっても隠れて見えない。ところが精錬を重ねていくと疵がはっきりしてくる。また麻の実から油を採る際、強くしぼらなければ油がわずかしか採れないのと同様である。今、日蓮があくまで厳しく国土に正法を誹謗することのあることを追求している結果、こうした大難が現われて来るのは、過去の重罪が、今の世に仏法を護持することによって引き起こされたものであろう。鉄というものは火の中に入れられなければ黒い物体にすぎない。ところが火の中で精錬されれば赤くなる。そしてまた木で急流をかけば波は山のように高くなるし、眠っている獅子に手を出せば大声で吼えるのである。
涅槃経寿命品にいう、「たとえばここに一人の貧しい女性がいたとする。彼女とともに同居して救護する者もいないうえに、彼女は病苦と飢えに悩まされ、あたりをうろついて物乞いをして毎日を過ごしていた。たまたま宿屋にとどまり、一人の赤子を生んだ。その宿屋の主(あるじ)が彼女を追い出したために、彼女は産後間もない身体でこの赤子を抱いて他の国に行こうとしたが、その途中、非常な風雨に出会い、寒さに悩まされたばかりか、蚊(か)や虻(あぶ)、蜂や毒虫に刺された。ガンジス河を過ぎ行くのに、赤子を抱いて渡った。その河の流れは速かったけれども、しっかりと赤子を抱きしめていた。ついにここで母と子とは河の中に沈んでしまった。しかしこの女性は慈しみの心を失わなかった功徳によって、死後梵天に生まれかわったという。文殊師利よ、もし善男子が正法を護持しようとするならば、この貧しい女性がガンジス河で、赤子をいとしく思うあまり、身命を捨てて赤子を放さなかったようにしなさい。善男子よ、仏法を守護する菩薩もまたこの女性が行動したようでありたい。護法のためにはいっそのこと身命を捨てなさい。このように心掛ける人は、殊更に解脱を求めなくとも解脱におのずから到達するのであって、それはあの貧しい女性が梵天に生まれかわるように特別願ったわけではないのに、梵天におのずから到達したようなものなのである」と。この経文について、天台大師の高弟、章安大師灌頂(かんじよう)は報障・煩悩障・業障の三障によって解釈しているので、それを見るべきであろう。
さてこの譬喩の「貧しい女性」というのは、仏法の財(たから)を持っていないことを譬えているのである。「女性」というのは、わずかであっても慈しみの心を持っていることを意味する。「宿屋」というのは、煩悩に迷わされる世界のこと。「一人の赤子」とは、法華経の信心によって成仏を約束された仏子のことであり、「宿屋の主が彼女を追い出した」というのは、日蓮が流罪されたのに該当する。「産後間もなく」とは、まだ法華経を信じてから長い時間を経過していないことをいい、「非常な風雨」とは、流罪を勅命した宣旨にあたり、「蚊や虻など」とは、勧持品の「諸の無智の人あって悪口・罵詈等し」という三類の強敵(俗衆増上慢など)に相当し、「母と子とは河の中に沈んでしまった」というのは、日蓮がついに法華経の信心をつらぬき通して竜口(たつのくち)で刎頸の刑場に臨んだことに合致するし、「死後梵天に生まれかわった」というのは、仏界に生まれることを言うのである。
業を結集して次の生(しよう)において方向づける能力というものは、仏界に至るまで変わることがない。日本・中国のすべての国々のあらゆる人を殺害したとしても五逆罪・謗法を犯さなければ八大地獄の第八の無間地獄に陥ることはないのであって、それ以外の地獄・餓鬼・畜生という悪道で長年苦しみを受けることになろう。三界のうち色界(しきかい)の四禅天に生まれかわるには、あらゆる戒を持ち、あらゆる善を行なったとしても、定善でなく散乱の心で善根をつとめたのでは生まれかわることはできない。また梵天王となるには、煩悩を滅することなく、向上の心をもって人間であることを失わないという行ないの上に、さらに慈悲が加わって、はじめて生まれかわることができるのである。この貧しい女性は赤子を慈しむ心があって梵天に生まれかわったのであって、一般の本性とそのすがたの法則とは相違しているのである。このことについて章安大師灌頂は涅槃経疏巻四に、貧女の発心(ほつしん)の位について十住已前と等覚以前との二つの解釈があると述べているが、(どちらにしても)要するに赤子を慈しむ心によって生まれたというより外には何もないのである。一念の心が一つの境地に集中されるのは禅定に似ている。ひたすら赤子を思う心は慈悲にあたるから、その慈しみの心がおのずから禅定となり、子への愛情が慈悲となって、貧しい女性が梵天に生まれることとなったものであろうか。
また成仏に至る道は、華厳宗が説く唯心法界観、三論宗が説く八不中道観、法相宗の五重唯識観、真言宗の五輪観などによっては成仏を達成することができるとは思われない。ただ天台大師智〓が開示した一念三千の法門こそ成仏を指し示す道と見られるのである。この深遠なる一念三千の法門について、われわれ末代の凡人はわずかの理解力もない(したがって天台大師が示したような摩訶止観の修行を達成することは困難である)。しかしながら、釈尊が御一代の間に説かれた諸経典の中で、この法華経だけが一念三千の宝玉(ほうぎよく)を内蔵しているのである。その他の経典の法理は、表面的には宝玉に似ていても、それはただ価値のない、ただ単に黄色い石にすぎない。砂をいくらしぼっても油を得ることはできないし、子供を産むことのできない女性に子供を求めるようなことになってしまう。諸経典は、智者(智慧のある賢人)であっても、やはり成仏を達成することはできない。それに対して、この法華経は愚かな者であっても成仏の因(もと)となる仏種を植えつけるであろう。先に掲げた涅槃経寿命品の中で、「煩悩の束縛を解き、苦を離れようと殊更に求めなくとも、解脱の境地に自然に到達する」と説かれるゆえんである。
日蓮、ならびに日蓮の門下たちは、たとえさまざまな受難があっても、法華経の教えを信じて疑う心がなければ、おのずから仏界に到達すること必定である。諸天の加護が現われないことに疑問を持ってはならない。この世が安穏にならないことを嘆いてはならない。我が弟子たちに、朝に夕に、いつもこのことを教えてきたけれども、重なる受難に疑問を起こして皆捨ててしまったのであろう。愚かな者の常として、約束したことを本当に大切な時に忘却してしまうことになるのであろう。妻子がかわいそう(不憫)だと思う者は、この世で生を受けているこの肉身が死に至ることを嘆くのであろう。幾度(いくたび)も幾度も生まれ変わり、久しい時間に、なれむつんできた妻子と心から離別したのであろうか。それとも仏道のために離別したのであろうか。いつでも、同じように嘆き悲しみながら離別したのであろう。日蓮は法華経の信心をつらぬいて法華経が永遠に説きつづけられる霊山浄土に参り、その霊山浄土からこの娑婆世界に帰って人々を導くのだ。
〔第十七章〕 摂受と折伏の意義を確かめる
疑っていう。汝が念仏者や禅宗などを無間地獄に堕ちると批判するのは、闘諍の心があるからである。さだめし修羅道に堕ちることになるのではないか。また法華経の安楽行品に「説く人や説かれる経典の欠点をあげつらうことを願ってはならないし、またその他の法師を軽んじてはならない」と説かれている。汝はこの経文の示すところと相違する行動をとったために諸天に見捨てられたのではないか。
答えていう。摩訶止観巻十にいう、「そもそも仏陀は二つの説法の仕方を示しておられる。一には摂受(しようじゆ)であり、二には折伏(しやくぶく)である。法華経の安楽行品に(「名を称してその過悪を説かざれ、また名を称してその美(よ)きを讃歎(さんたん)せざれ」とあるのを法華文句に)『長短を称せざれ』と要約しているが、これが摂受の意義である。それに対して涅槃経金剛身品に『刀や杖をいつも携えて、あるいは首を斬れ』と説くのが折伏の意義である。褒めて教えの意義を明らかにする〈与(よ)〉と厳しい態度で臨んで教えの意義を明らかにする〈奪(だつ)〉という二つの導き方はその方途を異にするが、両者がともに衆生に功徳を得させるところは同じである」と。妙楽大師がこれに注釈を加えた弘決巻十に次のようにいう、「『そもそも仏陀に二つの説法の仕方がある』とあるうち、『涅槃経に、刀や杖をいつも携えて……』とあるのは、涅槃経の第三に『正法を護持する者は、五戒を受けなくとも、戒律にかなった立居振舞を整えなくとも、武器を持って恐れなく進まねばならない(昔、有徳王は破戒者を刀剣をもってこらしめ殉死したが、覚徳比丘とともに阿〓仏の国に再生した)。さらに、正法を護持するために、大乗を誹謗した婆羅門を殺害した仙予国王のことが説かれ、経の第二には『新医が毒害のある乳薬を禁じるために、もし新たに服用する者があれば、その首を断て』と説かれる。これらの経文は正法を破る人を折伏することを明らかにしている。すべての仏教経典は、この摂受・折伏の二つの法門に集約される」と。
また天台大師は法華文句第八巻にいう、「問う。涅槃経は国王に親しく付き随い、弓を持ち〓(や)を帯び悪人をくじいて服従させよと説く。それに対してこの法華経は権力者から遠ざかって謙虚に慈しみ深くあれと説くのであって涅槃経の剛に対して法華経は対照的に柔らかな態度をとる。これはどうして決定的な相違とはならないのか、と。答えていう。涅槃経はひたすら折伏を論じているけれども、同時に一人の子を愛するように、仏陀がすべての衆生を憐れむことが説かれているのであるから、どうしてまったく摂受がないといえようか。また法華経はひたすら摂受を明らかにしているけれども、陀羅尼品においては、行者に怨(あだ)をなす者は頭(こうべ)が七つに割れて阿梨樹の枝のようになると説くところを見ると、折伏がまったくないとはいえない。涅槃経と法華経とはそれぞれその一部分を挙げて時に適った方法をとるのみなのである」と。さらに章安大師の涅槃経疏に金剛身品を釈していう、「出家であれ、在家の信徒であれ、正法を護持するためには、その根本となる心のふるまいを根本とし、戒律などの事相にとらわれずに根本の教理を確立し、大いなる教えを弘めよ。だからこそ正法を護持せよといわれるのである。護法のためには枝葉末節にこだわってはならないのだ。だから戒律にかなった立居振舞を修しなくともよいと言われるのである。昔は時代が平穏でよく正法が弘まった。だから戒を守って、杖などの武器を身に帯びることが禁止された。それに対して今は険悪な時勢であって仏法が隠されてしまっている。だから護法のために杖などを持たねばならない。今のような時には戒をそのまま持っているわけにはいかない。今日でも昔であっても、険悪な時勢であればともに杖などを持ち法を護るべきである。今日でも昔であっても、平穏な時代であればいつでも戒を持つべきである。摂受と折伏のいずれを取るのか捨てるのか、その時勢によって適切な方法を見究めるべきであって、一方的な判断をすべきではない」と。汝の疑問を世間の学者はおそらくなるほど道理だと思うであろう。たとえどのように厳しい諫暁を行なっても、日蓮の弟子たちもこのような考え方をつらぬき通している。まるで一闡提の人のようにそれに固執しているのであるから、まず天台大師・妙楽大師らの注釈を提示して、世間の学者のとり違えた疑問をさえぎろうと思う。
そもそも摂受と折伏という法門は水と火のように性格を異にし、火は水をきらい、水は火を憎むように、摂受を主張する者は折伏をあざけり、折伏を主張する者は摂受とは情けないと悲しむのである。しかしながら、仏法をわきまえない無智の者や悪人が国土に充満しているときには摂受を前面としなければならない。法華経の安楽行品のように。仏法の中にあって法華経をそしる邪智の者、謗法の者が多いときには折伏を前面に立てるべきである。法華経の常不軽菩薩品のように。例えば、暑いときには冷水を用い、寒いときには火を好むようなものである。草や木は太陽の恩恵を受けるものであるから冬の月に照らされて苦しみを得るのであり、あらゆる水は月の従者であるから暑いときにはもともとの性質を失ってしまうのである。末法という時代には摂受と折伏のいずれもあるはずだ。つまり無智の者や悪人が充満する悪国と、そして邪智の者や、謗法の者が充ちあふれる破法の国という両様の国があるはずだからである。そこで、日本国の今の世のありさまは、果たして悪国であるのか、はたまた破法の国であるかを検討したうえで見極めねばならない。
問うていう。摂受であるべき時代に折伏を行ずるのと、折伏であるべき時代に摂受を行ずるのと、それぞれ衆生に利益をあたえることができるだろうか。答えていう。涅槃経第三、金剛身品にいう、「迦葉菩薩が仏陀に申し上げるには、『如来の法身は金剛石のように壊れることがありませんが、なぜそうなられたのかが分かりません。どうしてそうなったのでしょうか』。仏陀は言われる、『迦葉よ、よく正法を護持する因縁によってこの金剛身となったのである。迦葉よ、我れは昔の正法を護持した因縁によって今この永久に壊れることのない金剛身となった。善男子よ、正法を護持する者は五戒を受けることもなく、威儀を修することなくとも、しかし刀剣や弓〓を身に帯びなければならない(以上、在家の信徒のあり方を示す)。このようにさまざまに法を説いたが、しかもなお獅子のような勢いで法を説くこともできないし、仏法にはずれた悪人を降伏させることもできない。このような比丘は自ら功徳を得、他をして利益を得させることができないのである。こうした輩はなまけ怠っていると知るべきである(以上、摂受の比丘への励まし)。よく戒を持(たも)ち浄(きよ)らかな行ないを守っていても、この人は護法のために何もなすことができないでいるだろう。それに対してあるとき、破戒の者があって、この教えを聞きおわると一斉に怒ってこの法師を殺害したとしよう。この説法者がたとえそこで死んだとしても、戒を持(たも)って自らも功徳を受け、他をして利益を得させた者とされる(真に仏道を修行する比丘のあり方を示す)』と。章安大師は涅槃経疏巻八にいう、「摂受をとるか折伏をとるか、適切な判断に立って決定すべきであって、いちずに行なってはならない」と。また天台大師は法華文句巻八に「摂受・折伏は時に適うように用いよ」と述べている。たとえば、秋も終わる頃に種まきをしたり、田畑を耕したとしても稲を稔らせることはできないのであって、それと同様なのである。
建仁年間に法然房源空と大日能忍の二人が出現して念仏宗と禅宗とを盛んに弘めた。法然は選択集で道綽の安楽集の意を要約して、末法の時代に入って「法華経を信奉しても、まだ一人も得道した者もなく、千人の信奉者のうち一人として成仏も往生も実現できない」と述べている。また大日能忍は問仏決疑経の文によって「禅は言葉で語った教えを超えて、仏の悟りそのものに直結するのである」と述べたのである。そしてこのような二つの主張が日本国中に充ち満ちたのである。
ところがこれに対して、天台宗・真言宗の学者たちは念仏宗や禅宗の外護者にこびたり、おそれたりするばかりで、その態度はあたかも犬が主人に向かって尾を振ったり、鼠が猫を恐れたりするようなありさまである。そのうえ、国王や将軍などの貴人に仕えては、仏法を破るいわれ、国を破るいわれをくわしく説き語ったのである。こうした天台宗・真言宗の学者たちは、今の世では餓鬼道に堕ちているようなものであり、死後の世では阿鼻地獄に堕ちてしまうであろう。たとえ、閑寂な山林に入って一念三千の観心(かんじん)によって心を集中させたとしても、人里離れた静寂な場所を選んで真言宗の秘法を身業(しんごう)・口業(くごう)・意業の三業のすべてにわたって、漏らすことなく修行したとしても、時機を知らず、また摂受・折伏の二門を理解しなければ、どうして生死の苦からのがれることができようか。
問うていう。念仏者や禅宗の僧をさいなんでその人たちの敵となってしまって、いったいどのような利益があるのか。答えていう。涅槃経寿命品にいう、「もし善き比丘が仏法を乱す者を見て、そのまま知らん顔をして、責めさいなむこともなく、追い出すこともなく、その罪状を挙げて処分することもないならば、まさにこの人は仏法の中にあって害をなす者である。それとは正反対に、もし仏法を乱す者を見て、よく追い出し、責めさいなみ、その罪状を挙げてはっきりと処分するならば、これこそ我れ仏陀の弟子であり、真実に仏陀の声を聞いて仏教を修行しようとするものである」と。章安大師は涅槃経疏にいう、「仏法を破り乱すのは、仏法の中にあって害をなす者である。慈しみの心がないのに、嘘を言って親しくするのは、これは人を害するものである。それを見抜いて誤りをただすのは、これこそ仏法を護持する真の仏弟子なのである。その仏法を乱す者のために悪を排除することは、すなわちその仏法を乱す者に慈しみを与える親の役目なのである。そのように仏法を乱す者に対して適切に責めさいなむ者は、これは我れ仏陀の弟子なのであり、それに対してそのような者を追い払わない者は仏法の中の敵なのである」と。
〔第十八章〕 三仏の本願に目覚めよ
そもそも法華経の見宝塔品を拝読すると、釈尊と多宝如来と十方分身諸仏の三仏とがそこに打ち〓って集まられたのはどのような意図によってであったのか、(それを問い尋ねると)「仏法を久しくこの世界に弘めとどめて(衆生を利益するために)ここに来られたのだ」と説示されている。この三仏が、(仏陀の在世から見て)未来の世(つまり末法の今の時代)に法華経を弘めて、未来の世(末法の今)のすべての仏子に与えようと念願せられた御心中を推察すると、さながら一人息子のひどい苦しみを受けているのに心を痛めている父母よりも、もっともっと強い強い慈しみの心で末法の衆生を見そなわしていらっしゃるのであることが分かる。ああ、それなのに、あの法然房源空はその三仏のお気持を大切なことだとも思わずに、末法の時代の衆生には法華経は縁が遠すぎるからと、その門を固く閉じて入れまいとせきとめ、心を失った子供をだまして宝物を捨てさせるように法華経を投げ捨てさせてしまったその心こそ、無慈悲なむごいことに思われるのである。自分の父母が他人に殺されそうになっているのに、父母に知らせないでいられようか。悪い息子が酒に酔って狂い、父母を殺そうとするのを止めないことがあろうか。悪人が寺院の仏塔に放火しようとしているのを止めないでいられようか。一人息子が重病に罹ってしまった、それをどうしても治〓させたいと願ってお灸を据えてもらわないでいられようか。今、日本国の禅宗の僧や念仏宗の人の謗法の行動を見て押しとどめようとしない人があれば、このようなことを考えない人である。それが(章安大師が涅槃経疏に述べた)「慈しみの心で接しなければならないのに、仏法を乱す者に嘘を言って親しくするのは、かえって彼を害することになる」という文章の意味なのである。日蓮は日本国のすべての人々に親しい父母のような存在である。すべての天台宗の人は仏法を乱す者にとってあだなす敵対者なのである。つまり、(さきに述べた通り)「仏法を乱す者のために悪を排除することは、すなわちその仏法を乱す者に慈しみを与える親の役目なのである」という章安大師の涅槃経疏に示す役割を果たしたのである。
菩提心を持たない者が生死の迷いの苦から脱却することはない。教主釈尊ですら、すべてのインドの宗教家から大悪人とののしりを受けられた。天台大師は江南・江北の十人の学僧から批判され、後代にも法相宗の徳一から「三寸の舌をもって仏を謗り五尺の身をほろぼした」などと揶揄された。伝教大師最澄は南都六宗の学者に「最澄は中国に渡っても都も見ていない」などと〓笑をうけた。これらは皆、法華経の教えを伝えるために受けた悪口であるから決して恥になるものではない。それどころか、愚かな者にほめられるということこそ最も恥となることである。日蓮が幕府から咎めを受けて流罪されたので、天台宗や真言宗の法師たちはきっと悦ばしく思うことだろうが、そのことは一方ではいたわしいことであり、また他方では心得がたいことである。
そもそも釈尊はわざわざ娑婆世界にお出ましになり、鳩摩羅什は亀茲(きじ)国に生まれながら前秦の苻堅(ふけん)将軍によって中国に拉致され、のち、姚秦(ようしん)に入って西安で経典翻訳に一生を捧げた。伝教大師は万里の波濤を渡って中国に入り法を求めた。付法蔵第十四祖の提婆菩薩がインドの異端の宗教家に憎まれて殺され、第二十五祖の師子尊者が〓賓(けいひん)国王弥羅掘(みらくつ)よって殺害されたのも、仏道を弘めたためである。さらに法華経薬王菩薩本事品をひもとくと、薬王菩薩は過去世に仏道を求めるために精進して、舎利塔の前で臂(ひじ)を焼いて供養した。聖徳太子は自ら梵網経を書写して外題に自らの手の皮を〓いで押した。また前生譚のなかに釈尊が過去世に釈迦菩薩として修行していたとき、仏を供養せんとして我が身の肉を売ったと伝える。楽法梵志は法を求めるために魔が婆羅門に化けて説いた通りに、骨をもって筆とし、血をもって墨として偈を写したと伝えられている。天台大師は「摂受・折伏は時に適(かな)うように用いよ」(法華文句巻八)と述べた。仏法の流布は時代と適合しなければならないのである。その仏法流布の前には、日蓮の流罪などはただ、今の世で受けたわずかな苦に過ぎないから、憂うべきことではない。(過去の罪を消滅し)後の生で大いなる楽しみを受けるのであるから、大いに悦ばしいのである。